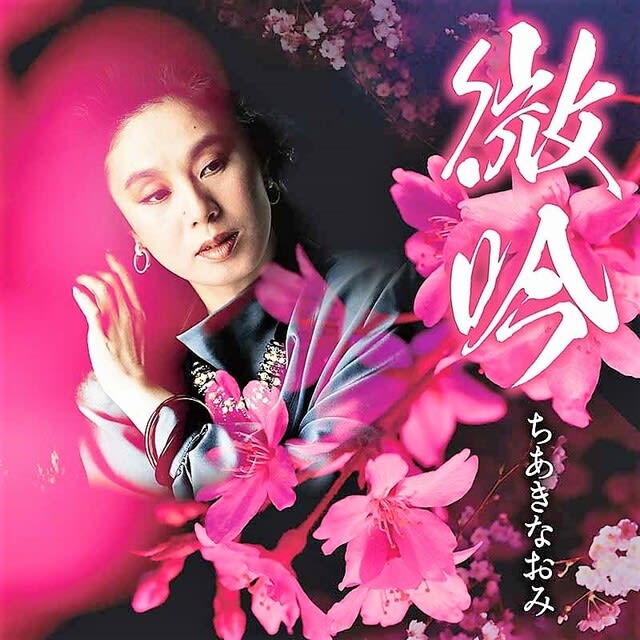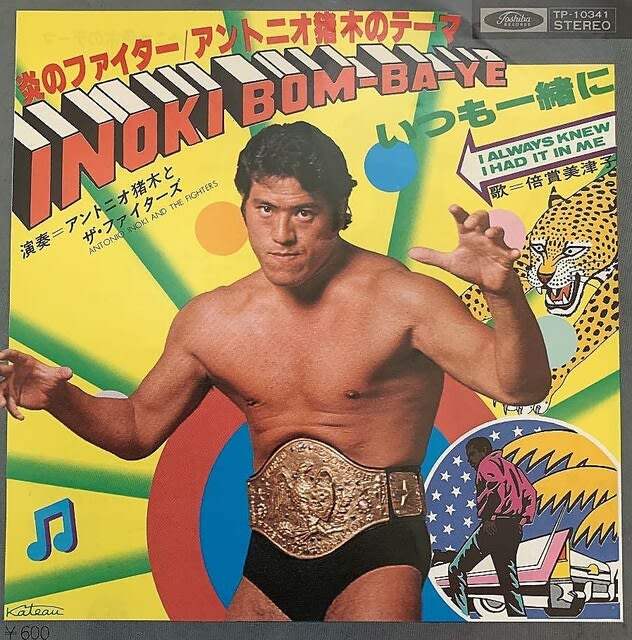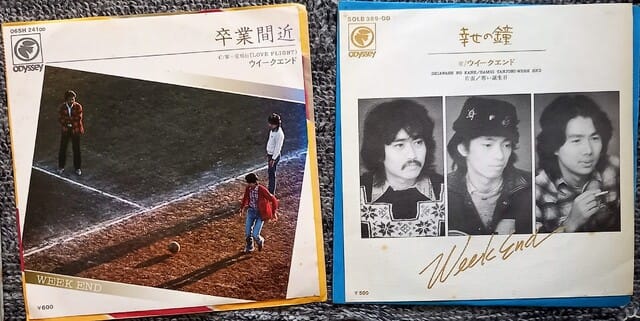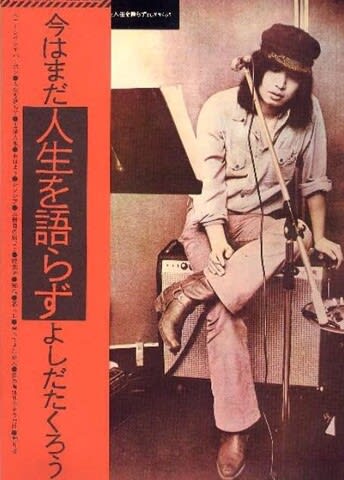あれから10年も この先10年も
行き詰まりうずくまり駆けずり回り
この街にこの朝にこの手のひらに
大切なものは何か 今も見つけられないよ
渡辺美里の「10years」。
全部を聴くと、失恋の歌だとは知っている。
だけど、いつも愛や恋とは違う思いでこの歌が聴こえていた。
自分にとっては、時間が過ぎたなあと思うとき、いつも頭の中に流れる歌だったのである。
あれから10年も この先10年も
この部分を聴くと、いつも時の流れの速さを思う。
あっという間に10年がたってしまった。
きっと同様に、この先の10年もあっという間に過ぎていくことだろう。
そんなことを思うのだ。
10年たっても、自分は何も変わっていないし、これからも大きく変わることはないだろう。
そんなことを思ってきた。
最近は、少しこの歌の聴こえ方が変わってきた。
「あれから10年も」が、時間が早く過ぎたという意味で、変わらない。
だけど、「この先10年も」を聴いて思うことが違うのだ。
この先10年、生きているのだろうか?
そんなことが、頭の隅をよぎるようになってきたのである。
私の年齢が、父の享年からあっという間に10年。
そして、母の享年まで10年を切ろうとしている。
さて、自分の人生は、いつまでだ?
確かにずっと人生は、「行き詰まりうずくまり駆けずり回り」の連続できたよなあ…。
そこに付け足して、10年といえば、娘が突然の病に倒れてからの年数にあたる。
まさに、「あれから10年」…。
そんなことなどを思うようになったから、聴こえ方が変わってきたのだろう。
生きているか?
そんなことは考えずに、この先10年も、
行き詰まりうずくまり駆けずり回りながらでいいから、ゆっくり生きていくことにしよう。
この街に この朝に この手のひらに 大切なものを1つ1つ見つけながら。