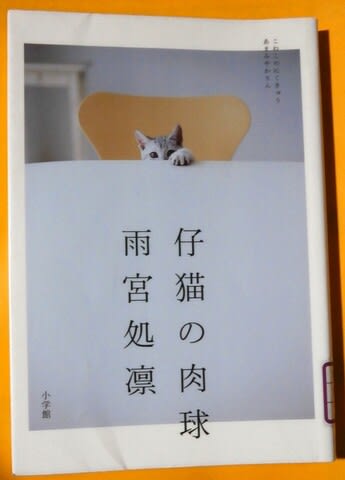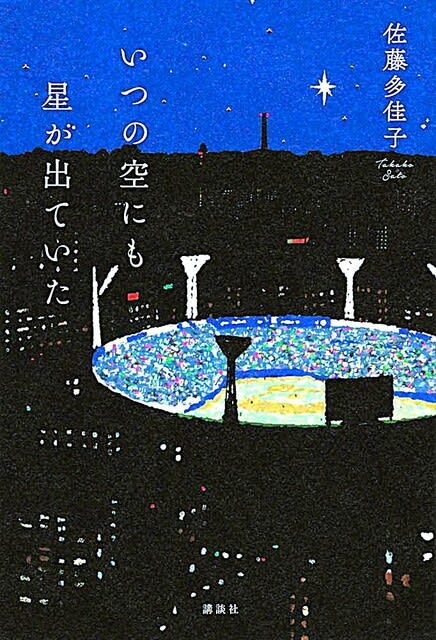柚月裕子という作家の名前は知っていたから気になってはいたが、まだ読んだことがなかった。

先日、キュンパスを使って旅をしたとき、新幹線の座席に置いてあるサービス月刊誌を開いたら、彼女の書いた旅のエッセーが載っていた。

これは、彼女の作品を読めという天の啓示だな、と思った。(そんな大げさな…⁉)
借りてみたのは、2010年に出された「最後の証人」という作品。(その後、角川文庫から文庫本が出版されている。)

法廷ものの小説だなと思って、ぺらぺらめくって見たら、章立てが面白い。
プロローグ、公判初日、二日目、三日目、判決、エピローグ。
よし、これを読んでみようと決めた。
ちなみに、本書の紹介は、以下のようなもの。
検事を辞して弁護士に転身した佐方貞人のもとに殺人事件の弁護依頼が舞い込む。ホテルの密室で男女の痴情のもつれが引き起こした刺殺事件。現場の状況証拠などから被告人は有罪が濃厚とされていた。それにもかかわらず、佐方は弁護を引き受けた。「面白くなりそう」だから。佐方は法廷で若手敏腕検事・真生と対峙しながら事件の裏に隠された真相を手繰り寄せていく。やがて7年前に起きたある交通事故との関連が明らかになり……。
プロローグでは、殺人に至りそうなシーンが描写される。
そこから物語は、法廷のことだけでなく、2つの事件を交えながら進んでいく。
1つは、医者夫婦の一人息子が車にはねられ亡くなった事件。
はねた運転手が酒臭く、信号無視をしたという目撃証言にもかかわらず、無罪となったという話。
そして、もう1つがその数年後に起きた、痴情のもつれから起きたと思われるホテルでの殺人事件。
話が進んで、「公判三日目」の章までどんな事件を巡っての裁判かはわかるのだが、被告人と被害者という表現で書かれていた。
固有名詞が出てこないのは何か変だな、と思いながら気になってさらに読み進んでいった。
そこに一つのどんでん返しがあった。
それについては、「ひょっとしたらと思ったら、やっぱりか」という思いはあった。
でも、殺人事件の真実にも、もう一つのどんでん返しがあった。
ここは、柚月氏、さすがだなと思った。
だけど、肝心なのは「最後の証人」というタイトルだ。
弁護側の証人に、佐方弁護士が誰を連れてくるか、ということ。
その意外な証人の語りから、事件のすべての真実が明らかにされていく。
「一度の過ちは誰にでもある。二度くり返せばその人の生き方だ」という表現が、ヒューマニズムにあふれていると感じた。
なるほど、主人公の佐方弁護士、すごい切れ者だなあと感心。
権力のある者たちの働きかけに左右されない、法律をもって正義で罪を裁き、事件の真相を明らかにしていくという佐方弁護士。
テレビでよく見ていた「相棒」で、罪を犯した者は裁かれなければならないと唱える右京さんと重なるところがあった。
そういう主人公のキャラ立て、どんでん返しのストーリー。
初めて読んだ柚月裕子作品。
うん、面白かった。
この佐方貞人の登場は、シリーズとなっていて、検事でしばらくあって、この作品が弁護士シリーズの最初のものだということをあとで知った。
検事にせよ弁護士にせよ、そのうち、また別な作品で佐方貞人に会いたくなりそうだ。