江戸の秋といえば、月見と紅葉狩りでしょうか。
今では、月見といえば十五夜か十三夜ですが、江戸時代には二十六夜待ち(旧暦7月26日の月)のほうが華やかだったようです。
夕方から、上野や浅草の侍乳山、湯島の台地、神田明神、九段坂上、愛宕山などの高台、あるいは品川、洲崎、高輪の浦辺に集まって月の出を待ちました。
江戸っ子は「十五夜だけして十三夜をしないのは方月見(方見月)になる」と言って忌み嫌いましたが、これは遊女が客の二度目の通いを確実に誘うための風習があったからだといわれています。
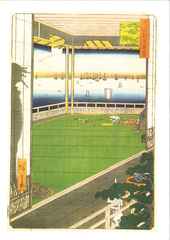
▲
月の岬(左手の障子に遊女が映っています。)
紅葉狩りでは、滝野川の金剛寺や北品川の東海寺、谷中の天王寺、下総の真間山弘法寺などが多くの人を集めましたが、江戸の市中では下谷の正燈寺境内と南品川の海晏寺が特に有名で南北の双璧といわれました。

▲
真間の紅葉手古那の社継はし
下谷の正燈寺といえば吉原がひかえていますし、海晏寺の近くにも品川の遊郭がありました。
「紅葉踏みわけるを母は悲しがり」「紅葉見にいきやしょうかと舌を出し」などという川柳がありますので、実際は紅葉狩りも方便に使われることが多かったようです。
(明日に続く。)
今では、月見といえば十五夜か十三夜ですが、江戸時代には二十六夜待ち(旧暦7月26日の月)のほうが華やかだったようです。
夕方から、上野や浅草の侍乳山、湯島の台地、神田明神、九段坂上、愛宕山などの高台、あるいは品川、洲崎、高輪の浦辺に集まって月の出を待ちました。
江戸っ子は「十五夜だけして十三夜をしないのは方月見(方見月)になる」と言って忌み嫌いましたが、これは遊女が客の二度目の通いを確実に誘うための風習があったからだといわれています。
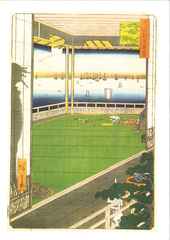
▲
月の岬(左手の障子に遊女が映っています。)
紅葉狩りでは、滝野川の金剛寺や北品川の東海寺、谷中の天王寺、下総の真間山弘法寺などが多くの人を集めましたが、江戸の市中では下谷の正燈寺境内と南品川の海晏寺が特に有名で南北の双璧といわれました。

▲
真間の紅葉手古那の社継はし
下谷の正燈寺といえば吉原がひかえていますし、海晏寺の近くにも品川の遊郭がありました。
「紅葉踏みわけるを母は悲しがり」「紅葉見にいきやしょうかと舌を出し」などという川柳がありますので、実際は紅葉狩りも方便に使われることが多かったようです。
(明日に続く。)
















