14.批評ということ ―『開かれた「構造」―遠山啓と吉本隆明の間』(柴田弘美 2014年)から
『開かれた「構造」―遠山啓と吉本隆明の間』(柴田弘美 2014年)を少しずつ読み継いでやっと読み終えた。頭が痛くなるほどカタイ本ではあったが、中途で投げ出す気にはならなかった。「頭が痛くなるほどカタイ」と言っても、また、わたしにはまだ十分な視界とまではいかないけれど、著者の説く数学的な構造に慣れてすっきりした視界を手にすればそうでもないだろうと思われる。わたしは高校生の頃たぶん『ガロアの生涯』を読んだ辺りからと思う、現代数学に関心を持ち、その後若い頃に遠山啓の諸本や野口宏の『トポロジー 基礎と方法』などなどたくさんの本を読み漁ったことがある。アインシュタインの相対性理論も関心を持ちその本を少し読んだり解説本も読んだことがあるが、現代数学同様これもあいまいさのイメージに包まれたよくわからないものであった。独学であり、またそれらは例えば海外での生活に差し迫って必要とする語学のようなものでもなかったから、中途半端のよくわからないままに終わってしまった。
読者としての一方的な言い分としては、めったにないけれども、読書を途中で投げ出すこともある。例えば菅野覚明『吉本隆明―詩人の叡智』は、終わり近くまで来て読み終えずに投げだした。吉本さんの表現をあれこれ参照しつつ細かに拾い上げてはいた。「固有時」という言葉を物理学の概念として割とていねいにたどり説明もしていた。つまり、批評対象との応対はていねいではあった。ただ、なぜ吉本隆明なのかというという対象を批評として取り上げるモチーフが希薄な感じを受けた。著者の批評のモチーフとしての生命感が感じられなかったのである。簡単に言えば、校長の話を聴かされているようでおもしろくなかったのである。
一方、本書は細かいところではいくつかアラはありそうにも感じたが、吉本さんの批評に数学的な構造(連続、基底、ベクトル空間、作用素、同型など)が一貫したものとして駆使されているのを心はやる思いとともにていねいにあとづけている。これは初めての試みではないかと思う。本書を読みながら考えたことがある。『言語にとって美とはなにか』の基軸となる二つの概念である自己表出と指示表出、そして両者が関係し合いながら表現空間に表現としてかたち成す構造、『心的現象論(序説)』の基軸となる概念の原生的疎外や純粋疎外と両者の関係する構造、こうした概念の創出やそれらの構造としての描出の背景にあるのは、吉本さんの科学的思考の修練や実験化学の具体的な修練と日々の人間的な経験、すなわち実感から来ているのではないかくらいでこれまでは済ませていた。だから、数学的な構造把握と構造的な措定とがそこまで徹底したものとして駆使されて考察されているという筆者の跡づけていく過程は驚きであった。
しかし思えば、『言語にとって美とはなにか』の数年後に刊行された『共同幻想論』の「序」では、「論理性あるいは法則性というものの抽象性のレベルというものに対する理解」ということが語られている。つまり、吉本さんの行使する論理に対する方法的な自覚と論理の世界の統一像が語られていた。その箇所は、わたしが初めて読んだ若い頃、十分に理解できないとしてもなにか大切なことが語られているぞと立ち止まってくり返し読んだ覚えがある。
だんだんこういうことがわかってきたということがあると思うんです。それは、いままで、文学理論は文学理論だ、政治思想は政治思想だ、経済学は経済学だ、そういうように、自分の中で一つの違った範疇の問題として見えてきた問題があるでしょう。特に表現の問題でいえば、政治的な表現もあり、思想的な表現もあり、芸術的な表現もあるというふうに、個々ばらばらに見えていた問題が、大体統一的に見えるようになったということがあると思うんです。
その統一する視点はなにかといいますと、すべて基本的には幻想領域であるということだと思うんです。
(『吉本隆明全集10』「共同幻想論」の序 P273 晶文社)
つまりそういう軸の内部構造と、表現された構造と、三つの軸(引用者註.自己幻想、対幻想、共同幻想のこと)の相互関係がどうなっているか、そういうことを解明していけば、全幻想領域の問題というものは解きうるわけだ、つまり解明できるはずだというふうになると思うんです。そういうふうに統一的にといいますか、ずっと全体の関連が見えるようになって、その一つとして、たとえば、自分がいままでやってきた文学理論の問題というのは、自己幻想の内的構造と表現の問題だったなというふうに、あらためて見られるところがあるわけです。そして、たとえば世の人々が家族論とか男女のセックスの問題とか、そういうふうにいっていた問題というのは、これは対幻想のもんだいなんだというふうにあらためて把握できる。それから一般に、政治とか国家とか、法律とか、あるいは宗教でもいいんですけれども、そういうふうにいわれてきた問題というものは、これは共同幻想の問題なんだなというふうに包括的につかめるところができてきた。だから、それらは相互関係と内部構造とをはっきりさせていけばいいわけなんだ、そういうことが問題なんだ、こんどは問題意識がそういうふうになってきます。
そうすると、お前の考えは非常にヘーゲル的ではないかという批判があると思います。しかし僕には前提がある。そういう幻想領域を扱うときには、幻想領域を幻想領域の内部構造として扱う場合には、下部構造、経済的な諸範疇というものは大体しりぞけることができるんだ、そういう前提があるんです。しりぞけるということは、無視するということではないんです。ある程度までしりぞけることができる。しりぞけますと、ある一つの反映とか模写じゃなくて、ある構造を介して幻想の問題に関係してくるというところまでしりぞけることができるという前提があるんです。
(同上 P274-P275)
それではなぜそういう欠陥が出てきたかといいますと、そういう人たちはおそらく論理性あるいは法則性というものの抽象性のレベルというものに対する理解がないんだと思うんです。つまり、現実の生産社会、技術の発展というものがあるでしょう、それを一つの論理的な法則、あるいは一つの論理の筋道がたどれるものとして理解する場合には、すでにある段階の抽象度が入りこんでいると思うんです。経済学でもそうだと思うんです。経済学でも、あるがままの現実の生産の学ではないのです。それは論理のある抽象度をもっているわけです。その位相というものがある。つまり水準というものがあるわけで、それがどういう水準にあるかということをよくつかまえることができないで、あるがままの現実の動き、あるいは技術の発展とか、また言語のばあいでもいいですよ、そういうものがなにか論理の抽象度というものとしばしば混同されてごっちゃになって考えが展開されるから、そこのところでひどい混乱が生まれてきてしまうということがあると思うんですよ。やっぱり全論理性というものの中でも、その抽象度というもの、あるいは抽象の水準というものをはっきりとつかまえて論理を展開していかないと、非常に簡単な未来像が描かれてしまったり、技術の発展に伴って非常に楽天的な社会ができてしまうんだというような考え方になっていってしまうけれども、それはおそらく論理の抽象度のある混同というものがあると思うんです。あるいはそれの把握しそこないがあると思います。
(同上 P279)
わたしがここで提出したかったのは、人間のうみだす共同幻想のさまざまな態様が、どのようにして綜合的な視野のうちに包括されるかについてのあらたな方法である。そしてこの意味ではわたしの試みはたれをも失望させないはずである。なぜならわたしのまえにわたし以外の人物によってこのような試みがなされたことはなかったからである。ただこのような試みにどんな切実な現代的な意義があるのかについてはひとびとのいうのにまかせたいとおもう。
(同上 P284)
ここには、黙々と荒地を耕すように論理の不毛な言葉の大地を突き進んできた吉本さんの姿があり、その自らの孤独な営為に対する自負が語られている。
ところで、柴田弘美の『言語にとって美とはなにか』への入口は次のような箇所に語られている。
吉本隆明の思想史として主要なことは、経験的実験科学に、そして少青年期を支配して来たナショナリズムの思想に、すべて絶望していた敗戦期に、遠山啓の「量子論の数学的基礎」という特別講義を聴講したことである。・・・・・・(略)・・・・・・吉本隆明は、それをもっと深く思想的基礎において受けとめたにちがいない。
・・・・・・(略)・・・・・・遠山啓氏によって触発された、単純因果律とは違う開かれた現代科学的思考は、文学、思想の場の核心となる。
(奥野健男「自然科学者としての吉本隆明」、
『科学の眼・文学の眼』、236~237頁)
奥野のこの記述によって、「もしかしたら私の勝手な思い込みにすぎないかもしれない」という迷いは少し退いた。実際、吉本の初期以来の諸論考を、このような現代数学が与えた影響とその痕跡を探るという明確な問題意識を携えて辿りはじめるや、「深く思想的基礎において」受けとめるべく模索する青年・吉本の姿に幾度もつきあたることになる。・・・中略・・・私の目には、遠山の特別講義によって与えられた現代数学の諸概念を、思想と科学の方法にもち込もうとする懸命な姿にみえる。本稿で後に幾度も触れることになるが、この試みはしだいに、そして真っ直ぐに『言語・美』へと結実していったと私は考えている。即ち、今、私にとって、『言語・美』は次のようなものとしてみえるのである―唐突、常識はずれという反発は覚悟のうえで、まず述べておきたい。
『言語・美』は量子論に数学的基礎を与えた「位相解析学」を導きの糸として、これとほとんど同型の構造をもって成立している。
この構造は、いわゆる構造主義の系譜とは大きく異なる別の出自から来ており、性質が異なる。端的に、変化、運動、ひいては歴史を扱うことができ、『言語・美』はまさしくそれを実行している。
(『開かれた「構造」―遠山啓と吉本隆明の間』P8-P9)
一つの集合に基底を与える、あるいは基底を見出す、という時、その集合を単なるものの集まりではなく、ひろがりのある空間として把握することを意味する。そしてこの基底によって、さまざまなモノの集合において、各要素の「位置」やその「変位」、「運動」を抽象的ではあるが表現し、検討できることとなった。
若き日の吉本は次のように記している。
僕は一つの基底を持つ。基底にかへらう。そこではあらゆる学説、芸術の本質、諸分 野が同じ光線によつて貫かれてゐる。そこでは一切は価値の決定のためではなく、原理の照明のために存在している。
(『箴言Ⅰ 原理の証明」、『全著作集』15、勁草書房、121頁)
一九五〇年、25歳の時にこれほどの重みを込めて書かれた「基底」は、10年の時を経て『言語・美』に甦った。「自己表出」と「指示表出」の一組である。この二つの概念によって言語の集合は方位や座標が抽象化、一般化された「基底」を与えられて、ひろがりのある空間性をもつこととなり、その内部で変位や運動を保証された。
(『開かれた「構造」―遠山啓と吉本隆明の間』P22)
吉本隆明が遠山啓の特別講義で出会い、獲得したと考えられる「構造」の世界では、「行為する人間」は「作用素」として、むろん高度に抽象化、形式かされてはいるが、その本質を保持し存在することができるのではないか。言い換えれば、いわゆる「構造主義」が捨ててきた「人間」あるいは「主体」という概念は、日常的で具体的な生身のそれとしてではなく、疎外-外化された「作用素」として、つまり「構造」という把握が成り立つレベルの抽象水準において、「構造」世界に生きぬくことができるのではないだろうか。 (『同上』P27)
今ここで述べておくべきは、この「互いに独立」という一つの関係性は先に触れた「基底」に要請される基本的な条件だということである。空間を「張る」もしくは「生成する」ために「基底」はこの条件を満たさなければならない。そして吉本は言語の空間構造把握に際して、史的必然性を担うものと、個体的な偶然性、一回きりの現存性を担うものと、二つの概念を〈互いに独立な〉「基底」として定立し、史的決定論とも、反ないし没歴史的「構造主義」ともはっきり違う理論を構成していったのだと考えられる。
(『同上』P30)
言語の自己表出は「(人間の:著者註)意識の構造にある強さをあたえるから、各時代がもっている意識構造は言語が発生した時代からの急げきなまたゆるやかな累積そのものにほかならず、また、逆にある時代の言語は、意識の自己表出のつみかさなりをふくんでそれぞれの時代を生きる」(『全著作集6,37頁』)・・・中略・・・
これらの立言を本稿の主要な関心事に即して言い換えれば、意識としての人間は言語を媒介、仲立ちとして自分自身(の意識)を作り、人間相互に(意識を)作りあい、同時に言語を表出してきたのであり、したがってある時代の人間の意識の強度の水準は、またそれを担う言語の「自己表出」の強度は、意識のまた言語の発生の当初から「連続」して転化し続けている、言い換えれば、各人はその時代の意識の強度また自己表出の水準を受け入れつつ、なお彼の意識生活の結果としての微小な増加分を付け加え続けている、と考えられる。・・・中略・・・
一方、言語の指示表出についてみてみると、「指示表出としての言語は、あきらかにその時代の社会、生産体系、人間の諸関係そこからうみだされる幻想によって規定されるし、強いていえば、言語を表出する個々の人間の幼児から死までの個々の環境によっても決定的に影響される。また異なったニュアンスをもっている」。これは言語の本質にまつわる「時代性」、類性に対する「個性としての差別性」言語本質の「対他の側面」であり、「おびただしい時代的な変化をこうむる。このような変化はその時代の社会の多様な関係、そのなかでの個別的な環境と個別的な意識性と対応し」「この意味で、言語(の対他的側面)は、ある時代の個別的な人間の生存とともにはじまり、死とともに消滅し、またある時代の社会の構造とともに生存し死滅する側面をもつ」とされた。
右のように整理した時、確認すべきことが二点ある。一つは第三節に述べた、連続性についてである。本稿は先に『言語・美』の基本的な志向を次のようにまとめておいたのだった。
作家、表現者個人の主題的意識を偶然に選ばれたにすぎないものとしてこれを遠ざけたのちになお、言語と文学表現のうちに歴史的に累積し、個々人の偶然性を越えて「連続」する何ものかを見出して、それを言語や文学の普遍的な測度(引用者註.著者の「補註(1)によれば、本稿では数学概念の「測度」は日常的な「尺度」と見なしてよいとある)として定立したい。
即ちここで、言語の「自己表出性」が時代を通じて前の時代の水準を前提的に引継ぎ何がしかの強度を付け加える(微小な増加分を付け加える)といった意味で歴史的に連続に転化するものであることを了解するなら、右のような測度としての役割が期待できることとなる。
一方、指示表出についてのまとめをみると、ある時代の言語の指示対象の全体像と別の時代の指示対象の全体像とを安易に比較することはできないと考えなければならない。つまり歴史的につながりをもたないことをみておかなければならない。また同時代にあっても、個々の人間が指示対象として切り取る現実はその人間の個体性の発露であって、他の人間のそれと比較してもしかたのないものなのだ。
・・・中略・・・
つまり言語表出や言語表現を比較較量する測度としては「自己表出性」がその可能性をもち、指示表出性は測度になりえない、という『言語・美』の全体をつらぬく原則的な考え方が示された。
もう一つは、第一章第七節に述べた史的必然性と一回きりの現在性との〈矛盾〉の問題である。右に整理したように、「自己表出性」はにんげんの類的本質力としての自己対象化の能力が発動され、その結果として自然の動物段階から人間自らを引き剥がすようにして発生し、それを前提にして後代の人間は生き、同様にして自己表出性を積み重ねていくものとして抽出されたのであるから、一方向に後戻りなしに進行する史的必然性をもっている。いっぽう、「指示表出性」はその先端的動向においては抽象性、普遍性、類性を増大させる傾向をもつけれど、その内部では各人は各々の個的事情にうながされ、また関心のおもむくまま、さまざまに対象指示を行いつつ生きるのであって、その時代の時代性、現在性、個的偶然性を示すことになる。『言語・美』が構造思想によって史的決定論に陥ることなく歴史を扱いうる、という時、このように、二つの「基底」に史的必然性と個的偶然性、一回性を振り分けて担わせ、現実の言語表出(表現)は両方を何がしかずつ同在させて実存する、という把握の仕方を指しているのである。
(『同上』P50-P53)
柴田弘美の『言語にとって美とはなにか』への入口部分に照明を当ててみた。そのことは同時に『言語にとって美とはなにか』の基本構造、いわゆる骨組みを明らかにすることにもなっている。それは柴田弘美が、吉本さんの『言語にとって美とはなにか』の具体的な現場そのものに立つことは一般的にも不可能だとしても、吉本さんの現場と同型性を持つある抽象度の水準の現場において立とうとすることを意味する。引用の後半では、自己表出の史的連続性と指示表出の時代制約的な固有性を『言語にとって美とはなにか』の構造を明らかにする大切な二つの〈基底〉として捉えている。このことによって、自己表出はその史的連続性ゆえに〈表出史〉として「表現転移論」(『言語にとって美とはなにか』 第Ⅳ章)として描きだれる必然性を持つことになる。ここでは批評は、吉本さんが『言語にとって美とはなにか』を書くに到った固有のモチーフや固有のイメージはあまり問われることなく、一挙に『言語にとって美とはなにか』の世界自体を開示しようとしている。
本書で論じられている吉本さんの『言語にとって美とはなにか』の刊行が1965年で、数学的な表現も駆使した『ハイ・イメージ論』が1989年であることを考えると、柴田弘美が本書で述べているように、吉本さんが遠山啓との出会いでおそらく数学の概念や捉え方を学び自分のものとして批評に自覚的に活かし続けてきたと言えるように思われる。
海外の思想や学者の概念や言説を紹介して、あるいはそれらに乗っかって何事かを言ったつもりになるのは、この列島の古代から今なお続く悪しき伝統である。清少納言の『枕草子』にもそんな悪しき伝統を背景とした作者の無邪気な物知りをひけらかすような描写があった。こうした連綿と続いてきているマレビト思想とでも呼ぶべきものとは無縁に、近代以降西欧の波を被ってきていることが背景としてあるとしても、抽象や論理ということが不毛なこの列島の言葉や思想の世界で、抽象レベルに自覚的で数学的な構造や概念を自分のものとして批評の世界に導入したのは、吉本さんが初めてであり、そして本書の著者は吉本さんのその現場近くに立ち合うようにして、それを追跡してゆく。このこともまた、初めて本格的に成されたものである。
〈批評〉という概念や表現がはじまり流通し出したのは、わが国では近代からである。もちろん現在からの視線で、平安期の歌合の判詞が歌の評価や批評に当たり、また歌論も歌の批評に当たると見なすことはできる。しかし、現在に通じる近代批評が本格的に始まったのは小林秀雄からである。その背景には、主要に近代以降に先鋭的に抽出され社会的に押し出されてくる個という存在がある。
ところで、わたしは〈批評〉という行為やその本質を作者(表現者)の言葉の現場に近づいて立ち合おうとすることであると捉えたことがある。その観点からすれば、本書は正しくその〈批評〉の本質にかなった批評であり、ひとつの作品であるということができる。わたしたちは、すぐれた作品(表現)に対しては、作者(表現者)の言葉の現場近くに立ち会い、その風景をていねいにたどることが、〈批評〉の前提的な本質だと思う。そうして、そのような〈批評〉の場においてこそわたしたちは、ある言葉の未知に出会うのだと思われる。つまり、自分でほんとうに考えを進めるきっかけを手に入れることになる。












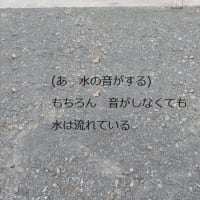







柴田弘美『開かれた「構造」』(アゴレー企画 2014年11月刊 248P 1800円 )は、アマゾンの新書でも古書でもヒットしませんね。ツイッターで、その本に関係する「模索舎」に問い合わせましたが、「在庫切れ・入荷未定」ということでした。
わたしは、まだその本を十分に読み切っているとは思えませんが、再びそれに触れることは当面ないような気がしています。そこで、以下の1.と2.を了承されたら、その下にある「★連絡方法」へ進んでください。わたしの手持ちの本をお譲りします。
1.現在は、付箋を付けながら本を読んでいますが、この本には昔からのわたしの読書法で、ほとんどのページにえんぴつで傍線が引いてあります。
2.1.を考慮して、送料含めて800円いただけたらと思います。本の到着後に郵便小為替で代金を郵送してください。
★連絡方法は、
わたしの昔からの本拠地であるホームページ「言葉の海から」の、
ht●tp://www001.upp.so-net.ne.jp/kotoumi/
表紙下の方に、「連絡用メール」がありますので、そこからあなたの発送先住所、お名前をお知らせください。
※ 上記URLがコメントで跳ねられたのでURLに丸印を入れています。