私なら…こんな選択もあるかも。
今回の診療報酬で新たに「地域包括診療料」が新設となった。
こちらは200床未満の病院と診療所が対象で、高齢者の外来における包括診療となっている。
対象患者は高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2疾患を持つ患者である。
この患者に対する服薬指導、健康診断などの勧奨と健康相談、介護保険の理解と連携、24時間の在宅医療の4つを担う。
実は、この4機能が主治医としての機能だそうだ。
当初、200床未満の病院で「地域包括診療料」を算定する場合、院内での調剤が原則となっていた。
診療所は薬剤師が居る所と居ない所があるので院外を認めるとした。
ところが最後の土壇場で病院も院外が認められた。
認められたが受ける薬局は24時間開局となっている。
こんな薬局はそうざらにはない。
24時間開局している薬局を紹介することを認めているが、そんな薬局がどこにあるのだ。
病院と薬局が遠く離れている場合などは、患者にとって恐ろしく2度手間になり、完全に無理である。
何といじわるなんだろうか。
診療所からの処方せんは、薬局の24時間体制として24時間の開局を求めてはいない。
この「地域包括診療料」であるが、初診では算定できない。
再診からの算定となる。
最近は長期処方が増えている。
患者の受診も月に1度がいいところである。
そこで、この仕組みが生きてくる。
再診料は現時点で69点(新点数:72点)である。
検査などが包括となっているが「地域包括診療料」は1503点だ。
これを再診料だとして考えると大幅な引き上げとなる。
あなたが医師ならどちらを選ぶだろうか。
さらに、200床未満の病院から処方せんが出ないように、7剤投与の減算規定の対象外となる。
現時点では院内投薬の場合、7剤を超えると薬剤費が90%に減額されている。
それが完全に出来高制となる。
90%の減額は消費税を考えると薬価から15%引きの価格に相当する。
薬価差益が少なくなったと言えども、それなりに魅力である。
200床未満の病床はどうするのか迷う。
診療所でも薬剤師が居るのであれば院内に戻る可能性がある。
対象となる4疾患は高齢者にありがちだ。
患者の多くを高齢者で占めるこれからにとって美味しそうな人参をぶら下げたものだ。
私が医師なら…うぅ~ん、悩む。
昨日、お陰様で母親の眼の手術は無事に終えたようだ。
これから病院に寄って様子を見て、今日は商店街の活性化事業に向かう。
道路の脇には2mを超えるような除雪の雪山が山脈のように連なる。
北国の春ははるかに遠い。
目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!
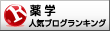
今回の診療報酬で新たに「地域包括診療料」が新設となった。
こちらは200床未満の病院と診療所が対象で、高齢者の外来における包括診療となっている。
対象患者は高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2疾患を持つ患者である。
この患者に対する服薬指導、健康診断などの勧奨と健康相談、介護保険の理解と連携、24時間の在宅医療の4つを担う。
実は、この4機能が主治医としての機能だそうだ。
当初、200床未満の病院で「地域包括診療料」を算定する場合、院内での調剤が原則となっていた。
診療所は薬剤師が居る所と居ない所があるので院外を認めるとした。
ところが最後の土壇場で病院も院外が認められた。
認められたが受ける薬局は24時間開局となっている。
こんな薬局はそうざらにはない。
24時間開局している薬局を紹介することを認めているが、そんな薬局がどこにあるのだ。
病院と薬局が遠く離れている場合などは、患者にとって恐ろしく2度手間になり、完全に無理である。
何といじわるなんだろうか。
診療所からの処方せんは、薬局の24時間体制として24時間の開局を求めてはいない。
この「地域包括診療料」であるが、初診では算定できない。
再診からの算定となる。
最近は長期処方が増えている。
患者の受診も月に1度がいいところである。
そこで、この仕組みが生きてくる。
再診料は現時点で69点(新点数:72点)である。
検査などが包括となっているが「地域包括診療料」は1503点だ。
これを再診料だとして考えると大幅な引き上げとなる。
あなたが医師ならどちらを選ぶだろうか。
さらに、200床未満の病院から処方せんが出ないように、7剤投与の減算規定の対象外となる。
現時点では院内投薬の場合、7剤を超えると薬剤費が90%に減額されている。
それが完全に出来高制となる。
90%の減額は消費税を考えると薬価から15%引きの価格に相当する。
薬価差益が少なくなったと言えども、それなりに魅力である。
200床未満の病床はどうするのか迷う。
診療所でも薬剤師が居るのであれば院内に戻る可能性がある。
対象となる4疾患は高齢者にありがちだ。
患者の多くを高齢者で占めるこれからにとって美味しそうな人参をぶら下げたものだ。
私が医師なら…うぅ~ん、悩む。
昨日、お陰様で母親の眼の手術は無事に終えたようだ。
これから病院に寄って様子を見て、今日は商店街の活性化事業に向かう。
道路の脇には2mを超えるような除雪の雪山が山脈のように連なる。
北国の春ははるかに遠い。
目指すは薬学ブログ第1位
こちらもお願いします!















