都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「国宝 伴大納言絵巻展」 出光美術館 10/7
出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)
「開館40周年記念 国宝 伴大納言絵巻展 - 新たな発見、深まる謎 - 」
10/7-11/5(全巻実物展示:10/7-15、10/31-11/5)
出光美術館の誇る至宝、「伴大納言絵巻」(12世紀・平安時代)を期間限定にて全巻展示する展覧会です。早速、初日に行ってきました。
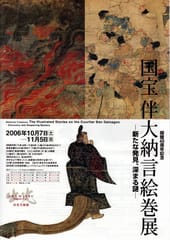
伴大納言絵巻を拝見するのはこれで二度目ですが、その全てを見るのはもちろん今回が初めてです。上、中、下巻合わせて27メートルという長大な絵巻の中に、「応天門の変」(866年)を題材とするスキャンダラスな歴史物語が圧倒的なスケールにて描かれています。精緻で生き生きとした人物描写と、巧みな場面転換、そしてドラマティックな炎上シーン。どこをとっても全く隙がありません。長さはともかく、僅か縦30センチ強の巻物が、さながら映画館の巨大スクリーンのような迫力を持って迫ってきます。この臨場感は強烈です。何百年も前の出来事だったのが、つい最近の事件であるかのような錯覚にさえ陥ってしまいます。これほど鮮やかな印象を残す絵巻物が他のどこにあるのでしょう。少なくとも私はそれを知りません。
大変高名な作品です。全体の流れや背景等は、展示や各資料などを参照していただきたいのですが、今回私が惹かれたのは、迫力ある炎上のシーンではなく、意外にも大納言や源信の登場する部分でした。ともに大胆な余白を用いて、彼らの激しい情念や静かな意思を克明に伝えています。嘆き悲しむ女房のシーンや、噂の広まる長屋の部分、それに検非違使らが勇ましく行進するクライマックスにかけての描写も当然ながら素晴らしいのですが、むしろ静寂の中に物語の核心がこめられたようなこれらの部分に釘付けとなりました。

その犯行を満足げに見届けながら静かに立つ伴大納言は、これまで「異時動図法」(ある人物を同じ場面に何回も登場させる技法。)によって大納言ではないと考えられていた人物です。今回、彼の登場場面のすぐ後ろに、失われた詞書が存在していたことが確実となり、技法は否定、あくまでも大納言であることが明らかとなりました。検非違使があたふたと駆けつけ、また人々が激しく燃え盛る応天門を見つめ騒ぐ炎上シーンからは一転、霞に包まれた幻想的な静寂の中にただ一人佇む大納言。その後ろ姿には、炎と喧噪をしっかりとこの目で見届けたぞという、何やら信念のようなものが漂っています。実際にこの光景は、天皇に讒言(源信が犯人であるとした。)した後の出来事に当たるそうですが、その肩や横顔に見る半ばリラックスしたような表現は、大きな一仕事を終えたという達成感すら感じさせました。そして霞がまるで事件の真相を包み込むかのように漂い、また不気味な静寂が今後の波乱をも予感させています。私がもう一点感銘した源信の祈りの場面とは全く正反対な、奇妙に良い意味で力の抜けた、それでいてやはりドラマの核となるべき部分が明らかにされた場面だと思いました。

自らの潔白を信じてひたすら祈り続ける源信の後ろ姿は、それこそ祈りと言うよりもまるで呪詛を唱えているかのような激しさを感じました。力強いこぶしを前に差し出し、肩を振るわせるようにして全身で祈りを捧げています。ここに見るのは無実の罪を着せられた源信の哀れさではなく、むしろ殿上人の熾烈な権力闘争の中で逞しく生きる政治家の姿です。結果的に源信はこの事件の数年後に亡くなってしまいますが、この時点ではまだ地位への執念が残っていたのではないでしょうか。喜怒哀楽を純粋に爆発させたその隣の女房たちとは対照的な姿でした。この絵巻に描写された人物の中で、最も魂を感じる部分です。
「新たな発見、深まる謎」とあるように、展示ではこの作品にまつわる様々な謎を解きほぐしています。大納言の特定や、詞書の意図的の欠落、さらには連行される大納言と良房との装束の関係。この手の政変にはいつの時代も非難や噂話が付きものではありますが、大納言は嵌められたのではないのかという、殆ど結論を出せそうもない歴史の文(あや)に思いを馳せるのも面白いかと思います。もはや真相は、積み重ねられた年月によって埋もれてしまったようです。
最後に会場について触れたいと思います。まず館内では、混乱を避けるために、ロープによって区切られた列に加わって鑑賞することが要求されます。上、中、下巻、全て別の場所に置かれていますが、それぞれの作品の前では基本的に一列、すなわち15~20人弱程度しか立ち入ることが出来ません。(遠目でも良い方は、列の外側からも進むことが出来ますが、殆ど見えないに等しいと思います。)よって入場者がそんなに多くなくとも、すぐに行列が出来てしまいます。(解説パネルの位置がその列をさらに長くしています。)そして後方からは、監視の方の「一歩前にお進み下さい。」や「立ち止まらずにお願いします。」という注意の声が引っ切りなしにかかっていました。やむを得ないことではありますが、少なくともゆっくり鑑賞出来るような雰囲気ではありません。もう少し配慮が欲しいところです。
図録も充実しています。時間に余裕を持ってお出かけなさることをおすすめします。来月5日までの開催です。
*展示スケジュールにご注意下さい。
全巻実物展示 10/7-15、10/31-11/5
中巻のみ実物 10/17-22(上、下巻は複製)
下巻のみ実物 10/24-29(上、中巻は複製)
「開館40周年記念 国宝 伴大納言絵巻展 - 新たな発見、深まる謎 - 」
10/7-11/5(全巻実物展示:10/7-15、10/31-11/5)
出光美術館の誇る至宝、「伴大納言絵巻」(12世紀・平安時代)を期間限定にて全巻展示する展覧会です。早速、初日に行ってきました。
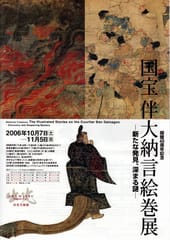
伴大納言絵巻を拝見するのはこれで二度目ですが、その全てを見るのはもちろん今回が初めてです。上、中、下巻合わせて27メートルという長大な絵巻の中に、「応天門の変」(866年)を題材とするスキャンダラスな歴史物語が圧倒的なスケールにて描かれています。精緻で生き生きとした人物描写と、巧みな場面転換、そしてドラマティックな炎上シーン。どこをとっても全く隙がありません。長さはともかく、僅か縦30センチ強の巻物が、さながら映画館の巨大スクリーンのような迫力を持って迫ってきます。この臨場感は強烈です。何百年も前の出来事だったのが、つい最近の事件であるかのような錯覚にさえ陥ってしまいます。これほど鮮やかな印象を残す絵巻物が他のどこにあるのでしょう。少なくとも私はそれを知りません。
大変高名な作品です。全体の流れや背景等は、展示や各資料などを参照していただきたいのですが、今回私が惹かれたのは、迫力ある炎上のシーンではなく、意外にも大納言や源信の登場する部分でした。ともに大胆な余白を用いて、彼らの激しい情念や静かな意思を克明に伝えています。嘆き悲しむ女房のシーンや、噂の広まる長屋の部分、それに検非違使らが勇ましく行進するクライマックスにかけての描写も当然ながら素晴らしいのですが、むしろ静寂の中に物語の核心がこめられたようなこれらの部分に釘付けとなりました。

その犯行を満足げに見届けながら静かに立つ伴大納言は、これまで「異時動図法」(ある人物を同じ場面に何回も登場させる技法。)によって大納言ではないと考えられていた人物です。今回、彼の登場場面のすぐ後ろに、失われた詞書が存在していたことが確実となり、技法は否定、あくまでも大納言であることが明らかとなりました。検非違使があたふたと駆けつけ、また人々が激しく燃え盛る応天門を見つめ騒ぐ炎上シーンからは一転、霞に包まれた幻想的な静寂の中にただ一人佇む大納言。その後ろ姿には、炎と喧噪をしっかりとこの目で見届けたぞという、何やら信念のようなものが漂っています。実際にこの光景は、天皇に讒言(源信が犯人であるとした。)した後の出来事に当たるそうですが、その肩や横顔に見る半ばリラックスしたような表現は、大きな一仕事を終えたという達成感すら感じさせました。そして霞がまるで事件の真相を包み込むかのように漂い、また不気味な静寂が今後の波乱をも予感させています。私がもう一点感銘した源信の祈りの場面とは全く正反対な、奇妙に良い意味で力の抜けた、それでいてやはりドラマの核となるべき部分が明らかにされた場面だと思いました。

自らの潔白を信じてひたすら祈り続ける源信の後ろ姿は、それこそ祈りと言うよりもまるで呪詛を唱えているかのような激しさを感じました。力強いこぶしを前に差し出し、肩を振るわせるようにして全身で祈りを捧げています。ここに見るのは無実の罪を着せられた源信の哀れさではなく、むしろ殿上人の熾烈な権力闘争の中で逞しく生きる政治家の姿です。結果的に源信はこの事件の数年後に亡くなってしまいますが、この時点ではまだ地位への執念が残っていたのではないでしょうか。喜怒哀楽を純粋に爆発させたその隣の女房たちとは対照的な姿でした。この絵巻に描写された人物の中で、最も魂を感じる部分です。
「新たな発見、深まる謎」とあるように、展示ではこの作品にまつわる様々な謎を解きほぐしています。大納言の特定や、詞書の意図的の欠落、さらには連行される大納言と良房との装束の関係。この手の政変にはいつの時代も非難や噂話が付きものではありますが、大納言は嵌められたのではないのかという、殆ど結論を出せそうもない歴史の文(あや)に思いを馳せるのも面白いかと思います。もはや真相は、積み重ねられた年月によって埋もれてしまったようです。
最後に会場について触れたいと思います。まず館内では、混乱を避けるために、ロープによって区切られた列に加わって鑑賞することが要求されます。上、中、下巻、全て別の場所に置かれていますが、それぞれの作品の前では基本的に一列、すなわち15~20人弱程度しか立ち入ることが出来ません。(遠目でも良い方は、列の外側からも進むことが出来ますが、殆ど見えないに等しいと思います。)よって入場者がそんなに多くなくとも、すぐに行列が出来てしまいます。(解説パネルの位置がその列をさらに長くしています。)そして後方からは、監視の方の「一歩前にお進み下さい。」や「立ち止まらずにお願いします。」という注意の声が引っ切りなしにかかっていました。やむを得ないことではありますが、少なくともゆっくり鑑賞出来るような雰囲気ではありません。もう少し配慮が欲しいところです。
図録も充実しています。時間に余裕を持ってお出かけなさることをおすすめします。来月5日までの開催です。
*展示スケジュールにご注意下さい。
全巻実物展示 10/7-15、10/31-11/5
中巻のみ実物 10/17-22(上、下巻は複製)
下巻のみ実物 10/24-29(上、中巻は複製)
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
| « 四季花鳥図屏... | 日本一の公立... » |










土曜日に行ってきました。
全巻揃いで見られるのは感動ものでした。
色々発見あって大満足です。
ただ、たかが30分の待ち時間を
待てずに文句たらたらの人いました。
来なきゃいいのにね。
TDL行ったらどれだけ並ぶか
分かっているのか!!と言いたくなりました。
これが放送されてしまっては混雑必至!
というわけで、慌てて開館20分前に出光へ。
その時点で既に館内にも列が出来ていたようで、
私は1階のエレベーター前に並びました。
10時の開館時には100人以上の大行列でしたよ。
美術館のお隣・帝国劇場の職員?の方も「凄い列ですねー」と
出光の警備員の方に話しかけていました。
展示。あああああ。本当に素敵。
多彩な表情、豊かな仕草、躍動感ある人物。
応天門炎上の場面など、群衆の声と炎の音が聞こえるよう。
どの場面も紙面から物語があふれ出てきていて、
吸い込まれてしまいそう。
丁寧で読みやすい詞書きの文字にも好印象。
たまらんです「伴大納言絵巻」大好き。
そして謎解きに挑戦してみました。
こんばんは。早速のコメントをありがとうございました。
>全巻揃いで見られるのは感動ものでした。
色々発見あって大満足です。
以前の名品展でちらっと拝見して以来、
ずっと気になっていた作品だったのでとても楽しめました。
三巻揃いの展示など滅多にないのでしょうね。
今年の出光は本当に当たり年です!
@菊花さん
こんばんは。ご無沙汰しております。
コメントありがとうございました。
>10時の開館時には100人以上の大行列
100人ですか!
ずらっと歩道に並ぶ感じでしょうか?
これはもの凄い人気ですね。
普段は帝国劇場の方が圧倒的に賑わっておりますが、
今回ばかりは出光の勝ちですね!
>たまらんです「伴大納言絵巻」大好き。
全く同感です。
初めから最後までこれほど惹き付けられる巻物など、
そうないですよね。
私が出向いた時は幸いにも空いていたようで、
列には加わりながら、何度もじっくりと拝見出来ました。
会期末はさらに大変なことになりそうです!(ダリも真っ青??)
@とらさん
こんばんは。
>謎解きに挑戦してみました
応天門コードですよね!後ほどじっくり拝見させていただきます!
私がいちばん興味深かったのは、子どものケンカが
発端で、うわさが広まっていくシーンでした。
謀略のようすが、些細なことから露見していくのが
ドラマチックでした。
>謀略のようすが、些細なことから露見していくのが
ドラマチック
そうですよね。
まさか子どものけんかから広まるとは思いませんよね。
噂が人を次々と経由して、
ねずみ算的に伝わっていく光景が目に浮かぶようでした。
この後ろ姿は、ちょうど紙継ぎのミステリーの場所でもありますね。
詞書を書いた後に、チェックした人(後白河法皇?)がやっぱりまずいとのことで削除と加筆を命じたのでしょうか。
300年前の事件に対する当時の関心は如何ほどだったのか。
興味が尽きません。
>詞書を書いた後に、チェックした人(後白河法皇?)がやっぱりまずいとのことで削除と加筆を命じたのでしょうか。
どうなのでしょうか。
確かに300年前のスキャンダルなのですよね。
それを人々がどう判断し、どう意味付けたのか。
現代の感覚からするとかなり謎めいていますが、
それこそ歴史の認識というのはいつの時代も難しいのかなあと思いました。
一体犯人は??
>再挑戦してみました。長くて恐縮ですがTB
いえいえ、ありがとうございます。
後ほどじっくり拝見させていただきます!