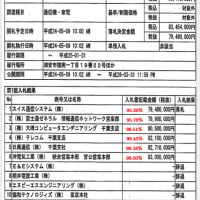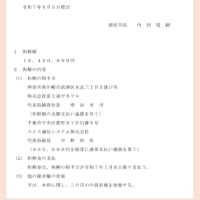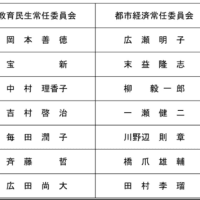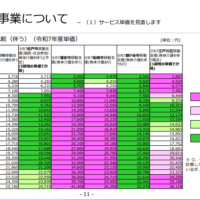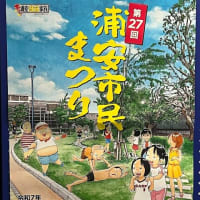浦安市は未だに以下のことをHP上に書いています。
平成23 年8 月5 日
■浦安市の現状について、(独)放射線医学総合研究所に聞きました。
Q1:現在の市内における大気中の放射線量は、どのような状況ですか。
A1:平常時の大気中における放射線量は、地上100 センチメートルで毎時0.05~0.10 マイクロシーベルト程度となっております。そのため、8 月2 日時点での浦安市の放射線量(高さ100 センチメートルの平均で毎時0.17 マイ
クロシーベルト)は平常時よりやや高めになっています。これは福島原発の事故直後に風に乗って飛来した放射性物質が、雨によって地上に落ち、土壌に付着していることが原因です。
Q2:現在も福島原発から放射性物質が飛来してきているのですか。
A2:現状では、福島原発からの放射性物質の放出はほぼ止まっていますので、千葉県までの飛来はありません。実際に、千葉県市原市のモニタリングポストでは5 月18 日以降に降下物が検出されていない状況であり、市内における大気中の放射線量は、時間の経過とともに下がる傾向にあります。
※モニタリングポストとは・・・文部科学省が放射線を定期的・連続的に監視測定するために設置した装置。千葉県内では市原市の県環境研究センター内の1ヵ所に設置。
Q3:現状の放射線量で健康への影響はありますか。
A3:現状の市の放射線量で健康に影響があるとは考えられません。国際放射線防護委員会では、「100 ミリシーベルトの被ばくで、がんの死亡率が0.5%上昇する」と推計していますが、それ以下の被ばくでは、がんの死亡率が上昇するかどうかは科学的に実証されておりません。
Q4:幼稚園の園庭や公園などにある砂場は、周りに比べて放射線量が高いと聞きますが本当でしょうか。外部被ばくもそうですが、子どもたちが砂を飲み込んでしまった場合の内部被ばくも心配です。
A4:他の場所に比べて、砂場という条件だけで放射線量が高くなることはありません。また、万が一、砂をなめたり飲み込んだりしてしまっても、放射性物質は砂に吸着したまま消化されずに排泄されますので、内部被ばくを引き起こすことはありません。
Q5:その他にも放射線量が周りに比べて高い場所があると聞きますが、何か注意しなければいけないことはありますか。
A5:現状で市内に存在する放射性物質は、セシウム134 とセシウム137 の2種類のみであり、どちらも水に溶けやすく、土壌に付着しやすい性質をもっています。そのため、雨どいの下や側溝など、雨の後に泥が溜まるような場所は、周りに比べて放射線量が高くなることがあります。しかし、あくまで校庭等の中心付近で測定した数値と比べて高くなる程度で、そのような場所に長時間いることは基本的にないと考えられるため、特に注意は必要ありません。
この内容につていは、特にQ4,5につてい大変問題を感じたので、私は何度も担当課に訂正を申し入れて来ましたが、一向に訂正する気配がないので、先日直接市がこの文面の根拠にしている放斜線医学総合研究所に出向き、真意を聞いて来ました。
その結果明らかになったことは、同研究所の見解としては「放射線は可能な限り浴びない方が良い」というものでした。そして、市に対して文面の訂正なり書きなおしなりをするように申し入れをするということを約束してくれました。
その後、実際同研究所は浦安に対して文書(メール)で申し入れを行い、続いて電話での申し入れもしてくれていますが、未だに市は訂正・変更の兆しがみられません。
何時までも、放射線医学研究所に責任あるような文面をHPに出していることは、同研究所に対しても失礼だし、市民に誤解を抱かせます。
浦安市は何時文面の訂正・変更を行う予定なのかを担当課に聞きましたが、「現在検討中」とのことでした。
検討中であれば、とりあえずあの文面はHPから削除すれば良いではないでしょうか?
誤ってであろうが、好きこのんでであろうが、砂をなめたり飲んだりしても、「放射性物質は砂に吸着したまま消化されずに排泄されますので、内部被ばくを引き起こすことはありません。」と全く根拠のないことを何時までも掲載していることが問題です。