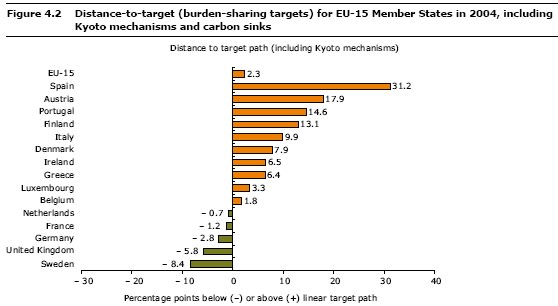ガソリンに代わるエネルギー源として注目される「バイオ・エタノール」。スウェーデンやその他のヨーロッパ諸国では数年前から実際に販売が行われ、一般のガソリンスタンドでもエタノール(E85)の給油が可能だ。
日本では2003年に、エタノールを3%まで混ぜた自動車用ガソリン(E3)の販売が解禁されているが、ほとんど普及していないという。エタノールの製造コストが高く、ガソリンよりも高くつくことが原因のようだ。それでも、石油会社のイニシアティブで、バイオ・エタノールをブラジルなどから大量に輸入し、本格な普及が図られつつある、というニュースを先週末に耳にした。
現在日本で導入されようとしているのは、エタノールをガソリンに3%混ぜたE3。エタノールがこの程度の含有量だと、普通のガソリン車でも問題なく走るという。一方、スウェーデンなどで販売されているのはE85だ。つまり、エタノールの含有率が85%なのだ。ここまでくると、一般の車には利用できない。①エタノール自動車を買う、か、②一般の車に20万円ほどかけて改造をほどこしてエタノールにも耐えられるようにしなければならない。それでも、環境意識の高まりやエタノールの値段の安さなどから、エタノールの普及は順調に進んできたようだ。
さて、まず①のエタノール車から。スウェーデンのVolvoやSaab、それからドイツ・フランスの自動車メーカー各社は「環境にやさしい車」として、「天然ガス車」と「エタノール車」に力を入れてきた。スウェーデン政府はこれらの車の普及を推し進めるために、一般の消費者の購入に際して補助金を拠出している。
②の一般車改造は、もともと法律では認められていなかったものの、2年前のガソリン価格高騰の時に、安いエタノールを給油するために勝手に改造する人が続出して、政府も追認するようになった、という経緯がある。環境の観点からも、エタノールを利用する人が増えるのは、望ましいことでもあった。
ここまで読まれて、あれっ、と思われるかもしれない。エタノールのほうがガソリンより安いの? そう、スウェーデンでは政府がエタノールの販売に補助金をつぎ込んでいるので、ガソリンよりも値段が安く抑えられている。だから、ガソリンが高騰して、エタノールとガソリンの価格差が開けば、とたんにエタノールやエタノール車、一般車改造への需要が高まるのだ。
例えば、今日現在の価格を見てみると、
一般のガソリン(Bensin 95・96・98)がリットル当たり12クローナ(210円)、ディーゼル(Diesel)が10.7クローナ(190円)なのに対し、Etanol E85は8クローナ(140円)となっている。(左の表が今日の価格。右の写真は以前撮ったもの)


しかし、そのために大きな問題もある。スウェーデンでは高まるエタノール需要に供給のほうが追いつかず、エタノールの買い入れ価格自体が上昇傾向だ。補助金をつぎ込んで、価格を抑えようにも限界があるわけで、ひとたびエタノールの価格がガソリン価格を上回った時には、エタノール車に乗っている人もガソリンを給油するようになる、という事態が生じた(エタノール車は、E85でも普通のガソリンでも走る。という点では“ハイブリッド”と呼べるのかな?)。そうなると、せっかくのエタノール導入も意味がなくなってしまう。だから、スウェーデンにおける課題の一つは、どのようにしてエタノール価格の長期的に押し留めていけるか、ということだ。
日本では2003年に、エタノールを3%まで混ぜた自動車用ガソリン(E3)の販売が解禁されているが、ほとんど普及していないという。エタノールの製造コストが高く、ガソリンよりも高くつくことが原因のようだ。それでも、石油会社のイニシアティブで、バイオ・エタノールをブラジルなどから大量に輸入し、本格な普及が図られつつある、というニュースを先週末に耳にした。
現在日本で導入されようとしているのは、エタノールをガソリンに3%混ぜたE3。エタノールがこの程度の含有量だと、普通のガソリン車でも問題なく走るという。一方、スウェーデンなどで販売されているのはE85だ。つまり、エタノールの含有率が85%なのだ。ここまでくると、一般の車には利用できない。①エタノール自動車を買う、か、②一般の車に20万円ほどかけて改造をほどこしてエタノールにも耐えられるようにしなければならない。それでも、環境意識の高まりやエタノールの値段の安さなどから、エタノールの普及は順調に進んできたようだ。
さて、まず①のエタノール車から。スウェーデンのVolvoやSaab、それからドイツ・フランスの自動車メーカー各社は「環境にやさしい車」として、「天然ガス車」と「エタノール車」に力を入れてきた。スウェーデン政府はこれらの車の普及を推し進めるために、一般の消費者の購入に際して補助金を拠出している。
②の一般車改造は、もともと法律では認められていなかったものの、2年前のガソリン価格高騰の時に、安いエタノールを給油するために勝手に改造する人が続出して、政府も追認するようになった、という経緯がある。環境の観点からも、エタノールを利用する人が増えるのは、望ましいことでもあった。
ここまで読まれて、あれっ、と思われるかもしれない。エタノールのほうがガソリンより安いの? そう、スウェーデンでは政府がエタノールの販売に補助金をつぎ込んでいるので、ガソリンよりも値段が安く抑えられている。だから、ガソリンが高騰して、エタノールとガソリンの価格差が開けば、とたんにエタノールやエタノール車、一般車改造への需要が高まるのだ。
例えば、今日現在の価格を見てみると、
一般のガソリン(Bensin 95・96・98)がリットル当たり12クローナ(210円)、ディーゼル(Diesel)が10.7クローナ(190円)なのに対し、Etanol E85は8クローナ(140円)となっている。(左の表が今日の価格。右の写真は以前撮ったもの)


しかし、そのために大きな問題もある。スウェーデンでは高まるエタノール需要に供給のほうが追いつかず、エタノールの買い入れ価格自体が上昇傾向だ。補助金をつぎ込んで、価格を抑えようにも限界があるわけで、ひとたびエタノールの価格がガソリン価格を上回った時には、エタノール車に乗っている人もガソリンを給油するようになる、という事態が生じた(エタノール車は、E85でも普通のガソリンでも走る。という点では“ハイブリッド”と呼べるのかな?)。そうなると、せっかくのエタノール導入も意味がなくなってしまう。だから、スウェーデンにおける課題の一つは、どのようにしてエタノール価格の長期的に押し留めていけるか、ということだ。