#初出2006-06-20だが、暫時トップに置く。
----
以前のエントリ:「日本という国」はプロパガンダの書だ / 2006年04月16日
まこと、『日本という国』(小熊英二 2006.4)は困った書だ。日本に赤い政権が出来た時には、副読本に指定されるだろう(笑)。前のエントリでは「広島で3万人の朝鮮人が被爆死」という数字のおかしさを指摘した(一応、当時の広島にいた25%が死亡率とみて、6千人~8千人程度が朝鮮人と推定したのが当方の結論)。
他にも逐一指摘できそうだが、それぞれ博識を必要としそうで、なかなか面倒だ。
#ただ、左巻きはあれだが、一部には参考になる情報もあった(それが知識人のやっかいさかもしれないが)。全般的には、左系トンでも本だ。
「強制的に日本国籍をもたされ」は何か妙だ。国籍は、住んでいる地域/国土が日本に併合された結果だ(併合の事情は台湾と朝鮮で若干違うが)。
「日本軍に徴兵」も何だか。それを言うなら特別志願兵制度が中心だったはずだ。徴兵は1944年から全朝鮮から計55,000人だが、訓練期間中に終戦となり、殆ど前線に動員された人はいなかったようだ(ソース)。人数的には徴用を言うべきだが、それも末期のことで、朝鮮からは「斡旋」が多かったはずだ。しかも斡旋も徴用も、殆どは終戦後に帰国した。日本に残った多くは戦前からの経済的移住者と、加えて戦後の密航者のはずだ。
「国籍を剥奪」も頓珍漢だ。韓国も(北)朝鮮も、併合に遡って不法であり、日本国籍は最初から無かったという主張だ。国籍を奪ったのは日本ではなく、韓国/北朝鮮当局と見るべきだ。いずれにせよ連合国/GHQが(三国人と)決めたのであり、日本が口出しできる話ではなかった。
「朝鮮人」を保護すべきなのは、韓国/北朝鮮だ。確か、北朝鮮はソ連とツーカーなので、かなり「帰国」したはずだ。もちろん労働力として欲しかった。韓国政府は今でも、そうした在外韓国人には冷淡だ。
以上の例はまだ分かりやすい例である。次のは困る。
探してみると、『天皇裕仁と東京大空襲』(松浦総三 1994)に、小熊著と全く同じ論理が書いてある。小熊氏の著に、色々下敷きがあるということだ(単独で突出した著ではないということ)。
まず原則論でいうと、明治憲法下の天皇は輔弼によって動く。昭和天皇は、天皇機関説の信奉者だった。立憲君主制の下で、輔弼によらざる動きは、厳に慎まれたというのが、まず前提。上記のエピソードは、天皇が恣意的な権限を持った独裁者のように書かれてあり、ミスリーディング。天皇の「拒否」はVETOのニュアンスで、実際はそんなものは無かった。
#そういうと、天皇に逸脱例やイニシアティブが常に無かったのかと問われそうだが、確かに昭和天皇の意識には大元帥としてのものがあったし(そう、昭和天皇は決して人形じゃなかったのだ)、「御下問」という形式は、何時、誰に、というだけでも、事実上の意見表明の機会だったとも言いうる。また陛下が(御下問の折に)何も返しコメントされなかったかというと、そうでもない。7人の重臣を呼び出したのも、時局を踏まえての焦燥感からで、強いイニシアティブに他ならない(どうしろ、と言ったわけではなく、どうなんだと聞かれたのだ)。
「History of Modern Japan」さんから、近衛上奏文について
近衛上奏文の核心はここだ。
当時呼び出された7人のうち、戦争終結を提言したのは近衛一人だったという。皆がてんでばらばらの意見を述べたに近い。天皇は皆の意見をよく聞いた。おいそれと、近衛に同意するわけもなかったのだ(マクロに見れば近衛の分析は卓見かもしれないが、どのみち粛軍は実行不能だ)。
当時、台湾決戦だか、沖縄決戦だか、あやふやながら、米軍に一泡ふかせてからの和平交渉が頭をよぎったのは事実のようだ。しかし3月の東京大空襲の折には、昭和天皇は被害の惨状を出向いて視察されている。昭和天皇がほんとにもうだめだと思ったのは、ドイツが崩壊した5月始めのようだ。さて、真相はかうだ↓
#『日本という国』はもっと糾弾されてよいはずだ。現在、アマゾンの歴史・地理部門42位だ。小熊英二氏が、ここまで厄介な人物だとは思わなかった。中沢新一なみだ(笑)。
##(の説)を追加。
[人気blogランキングに投票]
----
以前のエントリ:「日本という国」はプロパガンダの書だ / 2006年04月16日
まこと、『日本という国』(小熊英二 2006.4)は困った書だ。日本に赤い政権が出来た時には、副読本に指定されるだろう(笑)。前のエントリでは「広島で3万人の朝鮮人が被爆死」という数字のおかしさを指摘した(一応、当時の広島にいた25%が死亡率とみて、6千人~8千人程度が朝鮮人と推定したのが当方の結論)。
他にも逐一指摘できそうだが、それぞれ博識を必要としそうで、なかなか面倒だ。
#ただ、左巻きはあれだが、一部には参考になる情報もあった(それが知識人のやっかいさかもしれないが)。全般的には、左系トンでも本だ。
p.133 > 台湾や朝鮮の人びとは、戦前はなかば強制的に日本国籍をもたされ、太平洋戦争末期には「日本人」として日本軍に徴兵された。ところが(中略)一方的に日本国籍を剥奪された。日本に連れてこられていた、たくさんの朝鮮人も同じだった。いまの在日韓国人・朝鮮人のはじまりだ。なんか頓珍漢で、やれやれな記述だ。これが学者の書くことだろうか(でも、今の日本史学界の趨勢かもしれない)。こういう問題なら「歴史と国家」雑考さんが参考になるが、まあ今日では常識の範囲かもしれない。
「強制的に日本国籍をもたされ」は何か妙だ。国籍は、住んでいる地域/国土が日本に併合された結果だ(併合の事情は台湾と朝鮮で若干違うが)。
「日本軍に徴兵」も何だか。それを言うなら特別志願兵制度が中心だったはずだ。徴兵は1944年から全朝鮮から計55,000人だが、訓練期間中に終戦となり、殆ど前線に動員された人はいなかったようだ(ソース)。人数的には徴用を言うべきだが、それも末期のことで、朝鮮からは「斡旋」が多かったはずだ。しかも斡旋も徴用も、殆どは終戦後に帰国した。日本に残った多くは戦前からの経済的移住者と、加えて戦後の密航者のはずだ。
「国籍を剥奪」も頓珍漢だ。韓国も(北)朝鮮も、併合に遡って不法であり、日本国籍は最初から無かったという主張だ。国籍を奪ったのは日本ではなく、韓国/北朝鮮当局と見るべきだ。いずれにせよ連合国/GHQが(三国人と)決めたのであり、日本が口出しできる話ではなかった。
p.149 > …サハリンは占領された。その後、1946年に引き揚げにかんする米ソ協定が結ばれたけれど、日本政府は日本人の引き揚げだけを認め、約4万3千人の朝鮮人は置きざりにされてしまった。なにしろ相手はソ連だ。日本人の帰国しか認めなかったのは、日本ではなく、ソ連ではなかったのか。基本的には、日本とソ連、韓国とソ連、北朝鮮とソ連、それぞれ二国間交渉の問題なのだ。
「朝鮮人」を保護すべきなのは、韓国/北朝鮮だ。確か、北朝鮮はソ連とツーカーなので、かなり「帰国」したはずだ。もちろん労働力として欲しかった。韓国政府は今でも、そうした在外韓国人には冷淡だ。
p.159 > 昭和天皇は、A級戦犯が合祀されたあとは、それまで行なっていた靖国神社への参拝をやめてしまった。側近の証言によると、「陛下は、〔A級戦犯の〕合祀を聞いた時点で参拝をやめるご意向を示された」という。この件については、諸説ある。こう簡単に天皇の意向と書かれては困る。桜井よしこさんによれば、真相は次のようなものである。
天皇家は、昭和50(1975)年11月21日の昭和天皇皇后両陛下の参拝を最後に、今日まで、靖国神社には足を運ばれていない。理由の説明は一切ない。ただ、推測は出来る。天皇の靖国参拝をつぶしたのは、1975年の日本社会党なのだ。
時の首相、三木武夫氏は昭和50年8月15日に靖国神社に参拝したが公用車を使わず、肩書きを記帳せず、玉串料を公費から支払わず、閣僚を同行しないことの4条件を以て、「私的参拝」だと述べた。
同年11月21日、前述のように天皇皇后両陛下は靖国神社と千鳥ヶ淵戦没者記念墓苑に参拝された。ところが、前日の11月20日の参議院内閣委員会で日本社会党がこれを問題にした。野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が質問に立ったのだ。追及を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇の参拝は、「憲法第20条第3項(抵触=筆者・注)の重大な問題になるという考え方である」と答えた。
「信教の自由」を謳った第20条の第3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と記されている。
それでも陛下は翌日、予定どおり参拝なさった。陛下の参拝とりやめは、参拝をめぐる政治的論争がおさまらないことを懸念した宮内庁が決定したものと思われる。
“A級戦犯”が靖国神社に合祀されたのは、それから3年後の1978年秋の例大祭のときである。そのことが新聞やテレビで報じられたのはさらに半年後の翌79年春の例大祭の直前である。3年の時間差と前後関係から、陛下の靖国参拝中止と“A級戦犯”合祀を因果関係で結ぶのは無理だ。(2005年6月9日「靖国で天皇も政治利用するのか」)
以上の例はまだ分かりやすい例である。次のは困る。
p.83-84 > これについては、昭和天皇も関係している。1945年2月、元首相の近衛文麿が天皇に降伏交渉を始めることを進言した。しかし天皇は、「もう一度戦果をあげてからでないとなかなか話は難しいと思う」と述べて、それを拒否した。この時点で戦争をやめていれば、3月の東京大空襲も、4月からの沖縄戦も、8月の原爆投下も、ソ連参戦やその結果としての朝鮮半島南北分断も、なくてすんだはずだった。えっ! これは2月に重臣ら7人を別々に(数日おきに)ひそかに呼び出して御下問された際の、近衛上奏文(1945年2月14日)に関わるエピソードだ。調べてみると、Wikipediaにもそんなような主旨のことが書いてある。これは困った。
探してみると、『天皇裕仁と東京大空襲』(松浦総三 1994)に、小熊著と全く同じ論理が書いてある。小熊氏の著に、色々下敷きがあるということだ(単独で突出した著ではないということ)。
まず原則論でいうと、明治憲法下の天皇は輔弼によって動く。昭和天皇は、天皇機関説の信奉者だった。立憲君主制の下で、輔弼によらざる動きは、厳に慎まれたというのが、まず前提。上記のエピソードは、天皇が恣意的な権限を持った独裁者のように書かれてあり、ミスリーディング。天皇の「拒否」はVETOのニュアンスで、実際はそんなものは無かった。
#そういうと、天皇に逸脱例やイニシアティブが常に無かったのかと問われそうだが、確かに昭和天皇の意識には大元帥としてのものがあったし(そう、昭和天皇は決して人形じゃなかったのだ)、「御下問」という形式は、何時、誰に、というだけでも、事実上の意見表明の機会だったとも言いうる。また陛下が(御下問の折に)何も返しコメントされなかったかというと、そうでもない。7人の重臣を呼び出したのも、時局を踏まえての焦燥感からで、強いイニシアティブに他ならない(どうしろ、と言ったわけではなく、どうなんだと聞かれたのだ)。
「History of Modern Japan」さんから、近衛上奏文について
この上奏文は、首相辞任後の近衛の持論である「軍部統制派=赤色革命論」のメルクマールと見て取れ、非常に興味深い。天皇はこの上奏を受けた後、#なるほど、戦前史を皇道派(王党派)と統制派(コムニスト)の抗争と見ると、色々見えてくることがありそうだ。
「米国は我皇室を抹殺せんと云い居る由なるも其の点如何」
と近衛に下問、近衛は、
「グルー(元駐日米国大使、のち米国国務次官)及び米国首脳部の考へ方を見るに、其処迄は行かぬ様思ひます」
と答えた。また、天皇から、
「梅津(美治郎・参謀総長)は米国が皇室抹殺論をゆるめざるを以て、徹底抗戦すべしと云ひ居るも、自分も其の点には疑問を持って居る」
などと話があったが、近衛の感想としては、
「御上は極めて素直に軍の上奏を御取り遊ばされ居る故、事態を夫れ程悲観遊ばされ居らぬ様にて心配なり」
近衛上奏文の核心はここだ。
勝利の見込なき戦争を之以上継続することは、全く共産党の手に乗るものと存候。随つて国体護持の立場よりすれば、一日も速かに戦争終結の方途を講ずべきものなりと確信仕候。戦争終結に対する最大の障害は、満洲事変以来、今日の事態にまで時局を推進し来りし軍部内のかの一味の存在なりと存じ候。(中略)従つて戦争を終結せんとすれば、先づ其の前提として、此の一味の一掃が肝要に御座候。これだと戦争終結の提案ではなく、統制派追放(粛軍)の提案であり、事実上(天皇のバックアップする)クーデターの提案だ。それは無茶だ。統制派をコムニスト同然にみなすのも、当時の日本では突出した意見と言わざるをえない。
当時呼び出された7人のうち、戦争終結を提言したのは近衛一人だったという。皆がてんでばらばらの意見を述べたに近い。天皇は皆の意見をよく聞いた。おいそれと、近衛に同意するわけもなかったのだ(マクロに見れば近衛の分析は卓見かもしれないが、どのみち粛軍は実行不能だ)。
当時、台湾決戦だか、沖縄決戦だか、あやふやながら、米軍に一泡ふかせてからの和平交渉が頭をよぎったのは事実のようだ。しかし3月の東京大空襲の折には、昭和天皇は被害の惨状を出向いて視察されている。昭和天皇がほんとにもうだめだと思ったのは、ドイツが崩壊した5月始めのようだ。さて、真相はかうだ↓
近衛と面談のとき天皇はこういっている。この文章が正しければ、前述の小熊氏の記述は捏造(の説)だ。これが学者のする事なのか。
「参謀総長などの意見として、たとえ和を乞うとしても、もう一度戦果をあげてからでないと、なかなか話はむつかしいというが、近衛はどう考えているか。梅津や海軍は、台湾に敵を誘導しうれば、こんどは叩きうるといっているが......」
近衛は答えた。
「そういう戦果があれば、誠に結構と思われますが、そういう時期がはたして到来しましょうか。それも近い将来でなくてはならず、半年、一年先では役に立たぬでございましょう」(『侍従長の回想』藤田尚徳)
#『日本という国』はもっと糾弾されてよいはずだ。現在、アマゾンの歴史・地理部門42位だ。小熊英二氏が、ここまで厄介な人物だとは思わなかった。中沢新一なみだ(笑)。
##(の説)を追加。
[人気blogランキングに投票]











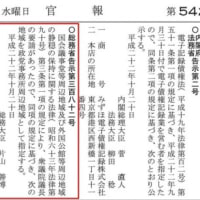




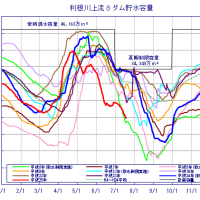

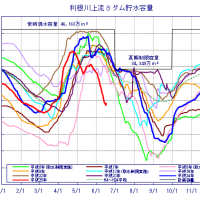
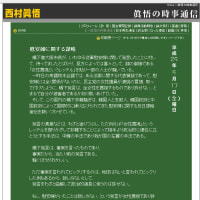
○日本の歴史
自分の沿ってる範囲で言うと
在日朝鮮人の人口は戦前すでに100万を突破していた
サハリンの4万3千の朝鮮人の多くは戦後ソ連・北朝鮮から移住した人たち