
 「Please Come to Boston」-Dave Loggins
「Please Come to Boston」-Dave Loggins
アルバム「Apprentice」-1974年-収録

奇跡の復刻盤!(?)・・・かも?

あのKenny Logginsの従兄弟であり、スリードッグ・ナイトの名曲「ピース・オブ・エイプリル」の作者としても知られるDave Logginsの1974年ビルボードTOP10の大ヒット曲「Please come to Boston」を収録したオリジナル・アルバムがCD化されました。
このアルバムが初CD化どうかは正確には自信ないですが、でもこのアルバムを聴きたいのなら今の内に是非入手しておかないと次はもうないかもしれません・・・?ちなみに私は、数年前ですが、この曲をCDで聴きたいばかりにネット検索を駆使して、やっとオーストラリアでベスト盤が出ているのを発見して即購入しました。でも当時は、このオリジナルアルバム自体は世界中どこでも発見できませんでしたよ・・・。

この曲は、アメリカをあちこと放浪する若者が、ボストンやデンバーやカリフォルニアから恋人へこちらで一緒に旅をしようと語りかける曲です。歌詞もメロディもとても素晴らしく「青春」を感じさせる超名曲です。ついこんな旅に出かけたくなってしまいます。
この曲は、彼のヴァンガードから離れてのシングル用に作られたもので、アルバムを想定していませんでした。でもこの曲がエピックから発売されて超大ヒットになってしまったため急ごしらえで制作されたのがこのアルバムらしいです。なのでこの曲にクレジットされている某プロデユーサーは他の曲には参加していませんしね(^^;。まぁアルバム全体としては、はやりそんな背景を感じる事もあり、名盤とはちょっと違うかもしれません・・・(<おいおい(^^;)。でも彼のファンであるなら必帯の盤であることは間違いありません。
悔しかったらこんな曲をヒットさせてみぃ、と今の音楽関係者に言いたい位地味なのに味わい深い名曲でです。今のビルボードでもオリコンチャートどちらでも良いけど、こんな曲がヒットできる素地はもうないですね・・・。こんな曲を評価出来る/いやヒットに結びつけるシステムが崩壊しているんだと思うな。全てが「お金・ビジネス」優先。「名曲だから取り上げよう・・・」みたいな偶然から生まれるヒットは実は現代では殆ど無いんだと思う・・・。メディアも人も限りなく音楽ビジネスにシステム化されすぎているからなぁ~。
例えば日本でも「地方から火がつきました」なんていう曲もたまにあるけどそれも話題づくり、「仕掛け」が殆どだし。今の時代、「良い曲だから」という音楽の本質で楽曲を取り上げる業界的な余裕も、また目利きのスタッフもあんましいないようだし、今の曲を流すメディア/業界にも期待できない気がする。もちろんアンコーさんのオールナイト・ニッポンみたいな良心的な番組もいくつかはあるけどね。でも殆どはもうダメかもなぁ~(^^;。
「音楽の品格」を問うてみたい時代とも言えるなぁ・・・

おっと、また愚痴ぽくなっちまったよ~(笑)
 |
アプレンティス ヴィヴィド・サウンド このアイテムの詳細を見る |
 |
One Way Ticket to Paradise Wounded Bird このアイテムの詳細を見る |
 |
Personal Belongings Vanguard Records このアイテムの詳細を見る |
 |
Please Come to Boston Sony Special Products このアイテムの詳細を見る |

























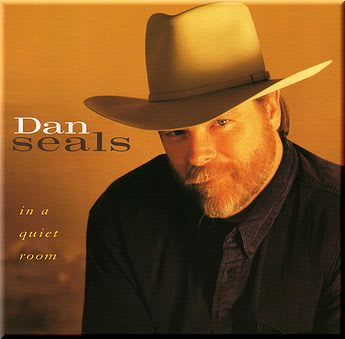
































 Michel Pornareff
Michel Pornareff

















 大笑いです
大笑いです





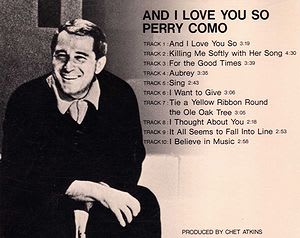

 金メダル記念
金メダル記念





