続いては、大学の部です。

《大学の部》
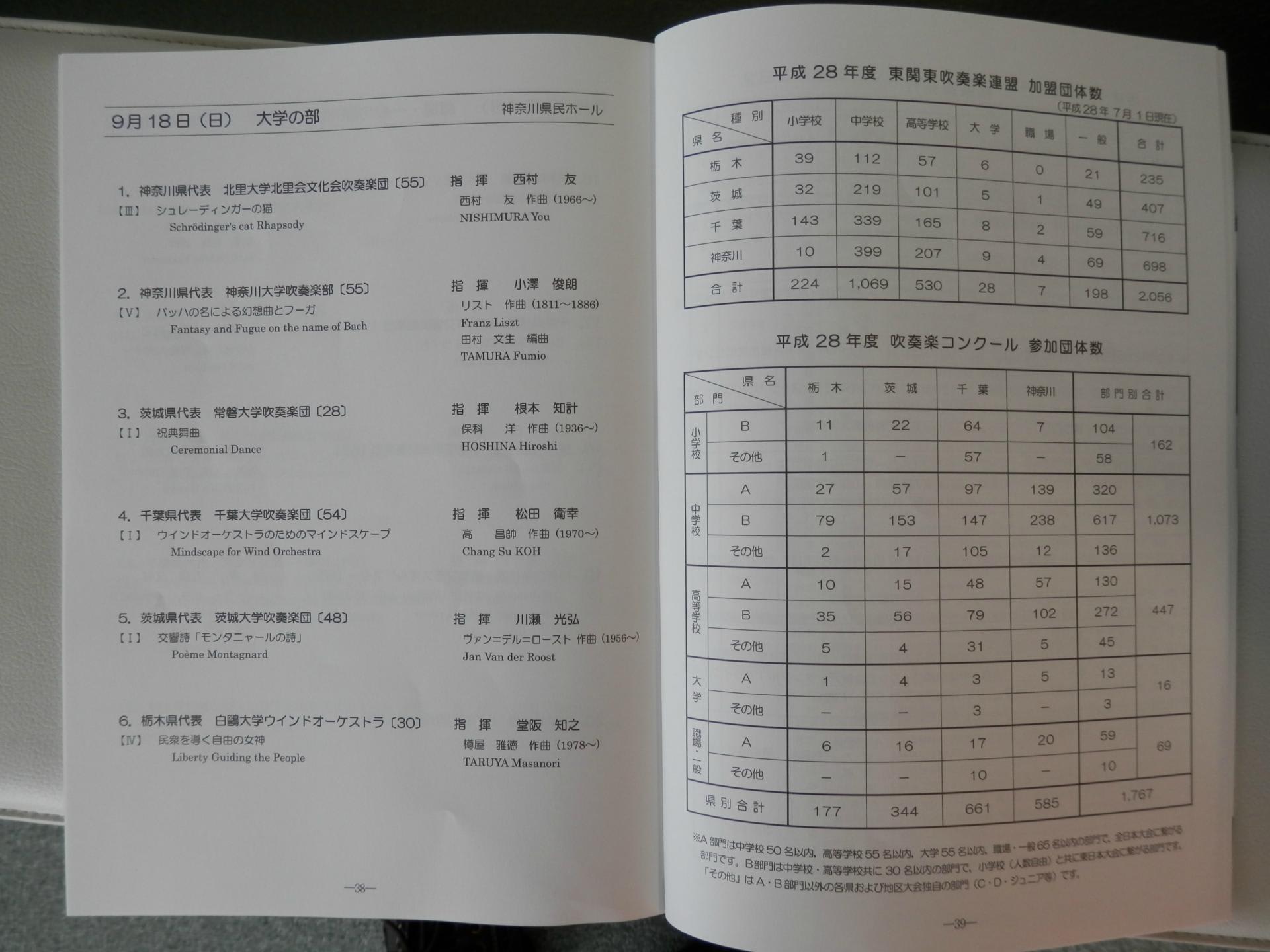
1.神奈川県代表 北里大学北里会文化会吹奏楽団 (指揮)西村 友
[課]Ⅲ[自]シュレーディンガーの猫(西村 友)
課題曲、自由曲とも同じ作曲者と言うことは、多々あることでしょうが、それを作曲者自身が指揮してコンクールに参加しているのは、珍しい。(と言うか、“ほぼ”ないでしょうね。)
その作曲者、西村先生の率いる北里大学の登場です。
課題曲は、もちろん、Ⅲ。
出だし、チョット、不明瞭な入り方をしましたか?
何か会場に広がるサウンドの“拡散”がイマイチかな。
打楽器だけがやたらに目立つような…。
あと、多少、ピッチが気になるパートがありました…。
緊張しているんでしょうか?
全体的にしっくりこなかった…。
県大会の方がパフォーマンス的には上でした…。
自由曲も西村先生の作品です。
何となく不可思議な面白い曲です。
私がもし、演奏者だったら、何らかの形で取り上げて見たくなるような楽曲ですね。
北里大学の演奏も課題曲とは違い、安定してきました。
途中、ホルン等でピッチが気になる場面もありましたが、表現力を感じられる演奏に変わっていきました。
演奏の道筋がみえてきたような…。
とても、良いパフォーマンスでした。
エンジンがかかるのが遅すぎたかな…。
それにしても西村先生の指揮は、“勇ましい”です。
[銀賞]
2.神奈川県代表 神奈川大学吹奏楽部 (指揮)小澤 俊朗
[課]Ⅴ[自]バッハの名による幻想曲とフーガ(リスト/田村 文生 編曲)
正直な話をすると神奈川県大会で聴かせて頂いた時には、ミスをしているわけではないのだけれど、何かしっくりしない演奏の“王者”でした。
だから、東関東で、どのようなパフォーマンスをみせてくれるか、非常に楽しみでした。
そして、この日の神奈川県民ホールで期待に応えた、いや、期待以上の演奏を聴かせてくれたのでした…。
課題曲は、毎年“恒例”のⅤ。
最初のフルート群のソロも観客が自然に受け止められるものでした。
他の団体とは少し違う感じもしました。
曲を通して言えることは、課題曲Ⅴの持つ“泥臭さ”を捨て、“透明感”を追求していたように思えたことです。
ある意味“鋭利”なサウンドです。
自然にスッと耳に、脳に、浸透してくる…。
これも“アリ”なのかなって思った次第。
ひとことで言うならば、“美しい”演奏でした。
自由曲は、今、“大流行”の曲ですね。
正直、自由曲の選択には、もっと冒険をして欲しい気もしますけれど、そんな“浦和のオヤジ”の気持ちを吹っ飛ばす、素晴らしい“時間”が待っていたのです。
寸分の狂いもない完璧なパフォーマンス。
計算しつくされている。
ビックリするくらいです。
だからと言って、“機械的”かと問われれば、“サニアラズ”。
見事な“情緒の世界”が広がっていたのでした…。
「全国金賞」間違いなしかも。
まるで、八代目桂文楽の落語のようでした…。(若い方は知らないですよね…。)
[金賞・代表]
3.茨城県代表 常磐大学吹奏楽団 (指揮)根本 知計
[課]Ⅰ[自]祝典舞曲(保科 洋)
人数が少ないですよね。
プログラムには、28名と書いてあります。
課題曲は“フレキシブル”な対応が出来る課題曲Ⅰ。
「A」の前のアウフタクトから始まる主旋律、良く響いていて心地よい。(特にクラリネット。)
同じく、トリオのメロディも良かったですが、少し元気がありすぎたような。
きれいにメロディを歌おうという意識も大切なのでは?
明るいサウンドは好印象でした。
ところで、打楽器のシンバルのお嬢さん(自由曲では、ティンパニを叩いていた方)は、もしかして、裸足だったのでしょうか?(3階席から見ていたので間違っていたら、ゴメンナサイ…。)
どうでも良いことですけど。
自由曲は保科先生の作品です。
少人数で演奏していることを感じさせない“スケールの大きさ”がありました。
そして、華やかさもありました。
躍動感もありました。
全体的にパンチの効いた演奏でした。
ただ、ゆったりとした部分で、もう少しデリケートな気遣いがあったら、と思いました。
良い演奏でした。
もっと、人数がいたらなぁ…。
[銅賞]
4.千葉県代表 千葉大学吹奏楽団 (指揮)松田 衛幸
[課]Ⅰ[自]ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高 昌帥)
課題曲は前の団体同様、Ⅰです。
サウンドが“シャカシャカ”しています。
わかりにくい表現かも知れませんが、“軽快だ”って事です。
演奏が“はじけて”いますね。
トリオのメロディ、よく歌っています。
細かいミスはあったものの、私は好きでした、この演奏。
最後のトランペットソロのミスは残念。
自由曲に移ります。
最初のマリンバ等、とてもステキでした。
パンチが効いて、勢いがあったので、自然に曲に流れが出来ていた。
だから、観客も舞台上に集中していけます。
反面、スローテンポの部分で雑然とした感じを受けたのも事実。
全体的には私の好みのサウンドで楽しめました。
最後のサックスだかクラリネットだかのリードミスは余計でしたが…。
[銀賞]
5.茨城県代表 茨城大学吹奏楽団 (指揮)川瀬 光弘
[課]Ⅰ[自]交響詩「モンタニャールの詩」(ヴァン=デル=ロースト)
3団体連続、課題曲Ⅰです。
ユーフォニアムが5人もいる!
少し演奏が“カタい”かな。
メロディも伴奏も“カタく”聴こえるような。
しっかりしたアンサンブルだっただけに、その点が惜しかった。
トリオ、トロンボーンの伴奏のロングトーン、ピッチが気になりました。
最後のトランペットソロ、もっと歌い上げれば良かったですね。
自由曲は、「モンタニャール」。
物語性を感じさせる雰囲気が出ていて曲に集中することが出来る演奏でした。
練習したなって思えるパフォーマンスでした。
好感度、“大”です。
ただ、曲の冒頭のウインドマシーン、「キッ、キッ」という機械音がしていたのが耳障りでした。
事前の確認も大事かと思います。
[銀賞]
6.栃木県代表 白鷗大学ウインドオーケストラ (指揮)堂阪 知之
[課]Ⅳ[自]民衆を導く自由の女神(樽屋 雅徳)
ここの団体も人数は少ない。(プログラム記載は“30名”)
課題曲は、「大学の部」で唯一のⅣ。
人数の要素を除いたとしても音が出ていない。
「響いてない」と言っても良いかも知れません。
特に金管楽器は頑張って欲しかった…。
もっと、音を遠くに飛ばす意識を持った方が良いかも。
そうすれば、華やかさも出るし、マーチらしくなると思える演奏でした。
自由曲は、ドラマチックな要素がふんだんにある樽屋作品です。
課題曲同様、“響き”がネックでした。
“激しさ”や“安らかさ”といった相反する表現をするのにもダイナミクス以前に“響き”が重要です。
基礎的なものを大切にしながら、曲を演奏していくのが肝要かと思われます。
[銅賞]

東関東支部(神奈川、千葉、栃木、茨城)の職場一般、大学の26団体、すべて聴き終わりました…。
審査員も疲れたでしょうが、私も疲れました。
でも、楽しかった。
特に職場一般は、“激アツ”の演奏の連続で興奮しました!
これだから、東関東大会はヤメラレナイ!

前も申し上げましたが、「神奈川県民ホール」は、思った以上に響くホールでした。
このホールで聴けて良かったです。
座席数が同等の“我が埼玉”の「大宮ソニックシティ」は、……、神奈川がうらやましいデス…。
来年は茨城での開催のようですが、出来れば、ずっと“ここ”でやってほしいなぁ。
最後に今回の成績のことを記しておきます。(大学は“圧倒的”なので、職場一般のみ)
1位 横浜ブラスオルケスター
2位 光ウィンドオーケストラ
3位 Pastorale Symphonic Band(以上が金賞・東関東支部代表)
3位 相模原市民吹奏楽団(パストラーレと同点、審査員の投票にて代表を逃す)
5位 グラールウインドオーケストラ(3位とわずか“2点”差)
6位 矢板ウインドオーケストラ(以上金賞)
いずれにせよ、平成13年に“土気シビック”と“グラール”が全国へ進んで以来、一度も2年連続、同じメンツで代表として全国大会に進んだことのない東関東支部の職場一般。
来年も熱い戦いが繰り広げられそうです…。

なお、このブログに載せられている文言は、“浦和河童”の個人的感想です。
決して、悪意を持って書かれているものではありません。
ただ、もし、ご不快に思われる方がいらっしゃいましたら、オヤジの戯れ事と思い、ご容赦頂ければ幸いです。















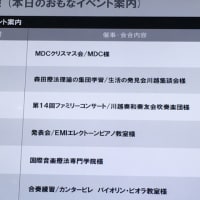
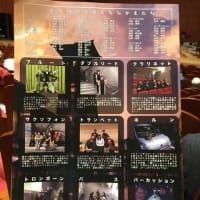
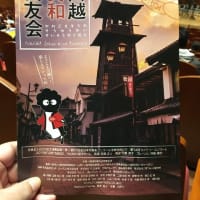


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます