東京メトロ南北線の六本木一丁目駅3番出口を出るとサントリーホールは、もうすぐです。
サントリーホール…。
私にとっては、実に懐かしい響きを持った名の場所です。
どこかのオーケストラ(おもに外国の)のコンサートがあるたびに楽器運びのアルバイトに何度となく通いました。
私の学生時代の話です。
あの頃、南北線は、もちろん、溜池山王駅もありませんでしたので最寄り駅は、東京メトロ(当時は営団地下鉄)千代田線赤坂駅でした。
ですから、私の中ではサントリーホールは、実際は六本木にあるのに赤坂のイメージが強いです。
昔話はこれくらいにして、私は、9月19日(月・祝)、サントリーホールを訪れました。
「全日本吹奏楽コンクール三年連続出場記念演奏会」ということで、東海大学付属第四高等学校と春日部共栄高等学校の合同演奏会が行われたからです。
全国の吹奏楽部員の目標、全日本吹奏楽コンクール(全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催)の全国大会は三年連続出場すると4年目はコンクールに出場できないというルールがあります。
今年は東海大四高も春日部共栄も、これにあたります。
本来であれば、今頃は両校とも地元の支部の代表となって、全国大会に向けての最後の仕上げの時期なのでしょうが、上記の理由でこの演奏会が開催が可能になったのです。

そうこうしているうちにカラヤン広場を抜けてサントリーホールの中に入りました。
20数年ぶりでしょうか?懐かしい!の一言です。(客で入ったのは1回しかありませんけど…)
指定の席につき、プログラムの目を通してみます。
1ページ目に東海大四高の井田重芳先生、春日部共栄の都賀城太郎先生、両顧問が「ご挨拶」文を載せられているのはわかるのですが、何故だかメインで大阪の淀川工科高校の顧問の丸谷明夫先が挨拶文を載せられているのは実に面白かったです。
余談はともかく、プログラムの構成は前半が春日部共栄高校の演奏で15分の休憩をはさんで後半が東海大第四高校の演奏、そして最後に一曲、合同演奏です。
私もワクワクしながら待っていますといよいよ開演です。
まず、最初の曲は「森の贈り物」(酒井 格)。
コンクールでもちょくちょく、取り上げられている曲です。
なんだか最初は緊張感なく曲になだれ込んだ感じがしましたが、時間が経つにつれ表現力が増してきたように思いました。
洗練された大人の演奏です。
2曲目は真島俊夫さんの作曲された「シーガル ~アルトサクソフォンと吹奏楽の為のバラード」でした。
アルトサックスのソロををこなしたのは3年生の部員、笹山しおりさん。
緊張しているのか、しきりにリードを気にされていましたが、深く哀愁のある音色で観客を魅了しました。ブラヴォー!!!
3曲目は「復興」。
私の世代では、神様のような作曲家、保科洋先生がヤマハ吹奏楽団のために作曲されたもだそうです。(そういえば、6月の定期演奏会でも聴かせて頂きました。)
1曲目2曲目は、3年生主体の演奏だったようですが、この曲は1年生,2年生の演奏と聞いて、どうかなと思っていたのですが、ミスはあるものの3年生にも引けを取らない演奏で感銘を受けました。共栄の未来は明るいです。
4曲目は、「祝典序曲“未来への翼”」(福島弘和)です。
この曲は初めて聞く曲ですが、それよりも何よりも演奏が春日部共栄“中学”校の皆さんなのです。
舞台上での都賀先生の説明によると練習日が週3日しかなく、しかも部員は30名しかいない。
それでも、9月17日(本演奏会の2日前)に新潟で行われた西関東大会へ勝ち上がり、中学校Bの部で金賞を受賞されたとのこと。
実際に演奏されているのを聴いてみると、さすがに中学生の未熟さはありますが、明るい音色で、それでいて高校の洗練されたサウンドは受け継いでいるように思いました。
指揮をされた共栄OGで国立音大の現役学生、織戸祥子さんも若者らしく躍動感にあふれ、中学生の皆さんとともに非常に好感が持てました。
ただ、人数が少ないのが残念です。(ホルン2名、チューバ1名、ユーホニューム、オーボエ、バスーン、コントラバスがいなかったように思いました。)
昨年の全国大会高校の部の市立前橋高校のような例(32名で出場)もありますが、いかんせん限界があります。
高校から受け継ぐ素晴らしいサウンドがあるのだから、人数を揃えてAの部に挑戦すれば、きっと強豪校になると思います。
春日部共栄高校単独での最後の曲は、「雷神 ~ソロパーカッションと吹奏楽のための協奏曲」(高 昌帥)。
打楽器奏者 寺山朋子さんを迎えての演奏です。
都賀先生のお話では、今年の春、ニューヨークのカーネギーホールで開催された第5回ニューヨーク国際音楽祭に参加(金賞受賞)した時に演奏し、大絶賛を受けた曲とのことです。
私も6月に大宮ソニックシティホールで聴かせて頂きましたが、(その時も良かったですが、)今回は一段とパワーアップし、完成度が高くなってました。
寺山さんのパーカッションも絶品です。
大絶賛のうちに演奏が終わりました。
その上、作曲者の高 昌帥先生も会場にお見えになっているというサプライズもあり、大拍手の中で前半が終了しました。
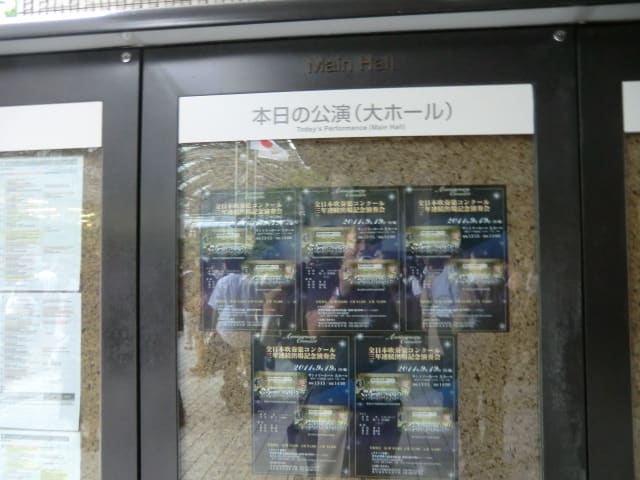
休憩15分。
その間に考えたことは、このホールは良く響くなあということでした。
私はシロウトですのでよくわかりませんが、世界中には様々なホールがあり、それぞれがひとつひとつの個性がある。
その個性を瞬時に見抜き演奏に生かしていくのもプロの技なんだなあと思った次第…。

いよいよ、後半です。
私にとっては初対面?の東海大付属第四高等学校の登場です。
指揮は、これまた吹奏楽界では有名な井田重芳先生。
写真でしか、お会い?したことがないので、動く井田先生を目の当たりにして感激でした。(失礼…)
プログラムを見てみますと春日部共栄に比べてラフな選曲です。
初っ端の曲は「バレエ音楽“白鳥の湖”」(チャイコフスキー/保科 洋 編)。
やはり、緊張するのか何となく曲が始まった感じがしました。
曲が進むにつれ重厚なサウンドが広がり始めましたが、細かいミスも多く何とか乗り切った感がありました。
2曲目は「歌劇“アンドレア・シェニエ”より 亡くなった母を」です。
同校OBであるという読売日本交響楽団の首席トロンボーン奏者 桒田(くわた)晃さんがソロで美しいメロディを奏でました。
私も吹奏楽部員であった太古の昔、トロンボーンを吹いていましたので、食い入るように聴かせて頂きました。
そして、桒田さん奏でるメロディに誘われるようにバンド自体も落ち着きを取り戻し、素晴らしいサウンドに変わっていくのがわかりました。
とても美しいサウンド、音楽でした。
次は「J-POPヒットメドレー」と題して皆さんがご存じの曲を演奏してくれました。
途中で男子学生の奇妙なダンス?があったりで楽しいステージでした。
ただ、一曲目の「笑点」のテーマが流れた瞬間、サントリーホールにはアワネェナアと思った次第。
4曲目は「子猫物語より“守る”」(谷川俊太郎/松下 耕)、合唱曲です。
東海大四高は練習に合唱を取り入れているそうで、そのため披露する事になったようですが、とても透明感のある美しい歌声でした。
私は合唱に関しては、全くの門外漢でしかも、サントリーホールのような素晴らしいホールで聴くのは初めてでした。
合唱もいいもんだなあとつくづく思いました。
東海大四高、最後の曲は、ドヴォルザークの新世界交響曲の有名なメロディをモチーフにした「ゴーイング・ホーム」。
かの岩井直溥先生の曲で前の合唱からの流れもあり、ますます、心洗われるような気になりました。
そして、いよいよ大トリの曲、中村俊哉先生の指揮で「科戸の鵲巣~吹奏楽のための祝典序曲」(中橋愛生)の合同演奏です。
この曲は、2006年、全国大会で高校では初めて春日部共栄高校が演奏し、全国金賞を獲った曲でその後も、いろいろな学校がしばしば演奏している超人気曲です。
とても、いい曲なので期待していました。
最後にふさわしい演奏だったとは思いますが、ただ惜しむらくは、合同演奏ということで演奏人数が増えたせいか輪郭がぼやけた感がありました。
あのようにすごく響くホールではバランスに注意が必要だと感じました。

「科戸の鵲巣」の合同演奏中、クラリネットパートのひとりの女子生徒が涙ぐんでいるのを見ました。
制服から言って、春日部共栄高校の生徒です。
推測するに彼女は、3年生でこのコンサートを以て引退と言う事なのでしょう。
春日部共栄高校は進学校ですので、練習時間も少ないと聞いています。
その中で全国トップクラスのレベルを保つためには、並々ならぬ苦労があったことでしょう。
いろんな事が頭の中を駆け巡り、感涙となったのではと思います。青春ですね。
(一応、お断りしておきますが、あくまでも推測です。違ってたとしたらゴメンナサイ。)
アンコールは両校の先生方が一曲ずつ演奏して下さり、盛況のうちに演奏会は終了しました。
両校とも日頃の練習の成果を発揮し、一生懸命演奏してくれました。
感謝感激であります。
特に東海大学付属第四高等学校の皆さんは、札幌からの遠征で疲れもあるだろうに、良く頑張ってくれました。
本当に御苦労さまと言いたい。

それにしても、全国大会3年連続出場すると4年目は出られないという制度は、如何なものかと思う。
学校は同じでも吹いてる生徒は毎年代わります。
やはり、全国大会のステージに立つというのが吹奏楽部員の共通の夢なのに、それを奪うのはあまりにも残酷です。
より多くの団体に出場の機会を与えたいという意図はわかりますが、どんなに強豪校が目の前に立ち塞がろうが全国大会に出たければ、それを乗り越えればいいだけの話であって、出場を制限するというのはナンセンスだと思います。
また、聴く側にとっても、常連校の春日部共栄や東海大四高(その他の強豪校も)の演奏が聴けないのは残念です。
是非、吹連には、この制度の再考をお願いしたいくらいです。
長くなりましたが、東海大学付属第四高等学校、春日部共栄高等学校が来年も普門館のステージに立ち、金賞を取られる事をお祈り申し上げます。













