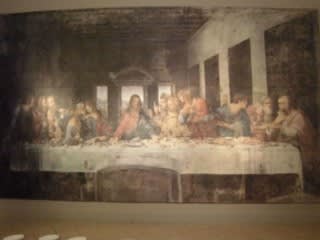徳島市国府町西矢野、阿波史跡公園の中核施設として誕生した「徳島市立考古資料館」。節約の神を自称する私にはかなり嬉しい「入館無料」の施設。

「見て、触れて、体験できる、古代ロマンのあふれる館」 芝生の緑が目に優しい敷地内の街灯は、いかにもそれらしい、古代を髣髴させる銅鐸のデザイン。

古墳とか考古学とか、もの凄~~~~~く興味があるわけではありませんが、だからといって全く興味が無いわけでもない(どっちやねん!)二人。店内の展示物、特に「神獣鏡」の種類に関しては、とても興味深く見学することが出来ました。

「この考古資料館の西に隣接する「気延(きのべ)山」は弥生時代末期から古墳時代の終わりにかけて、有力者の墓が数多く設けられていたと考えられており、気延山古墳群と総称されています。このうち矢野古墳は気延山に築かれた最終末の古墳と考えられています。 埋蔵施設の横穴式石室は、石室の入り口付近が壊されているものの、遺体を安置した玄室は良好な状態で残っており、徳島県内では横穴式石室に入ることができる数少ない古墳です」公式HPより

はるかな昔、権力者の遺体が埋葬された横穴式石室に、何と😲!入って見学することができるのです。 まさに「見て、触れて、体験できる」の言葉に偽りはありません。

どちらかというと人一倍臆病で怖がりの私。墓地に足を踏み入れるのさえ一人では嫌なくせに、何故か古墳とかだと、さして躊躇もせず覗き込んだり出来ます😄 今回は完全に中に入るのですが、石室内は暗いからと懐中電灯まで貸してくださる心配り、とても感激でした。

------------------------00----------------------
徳島市南矢三町にある「国登録有形文化財:高橋家住宅」。徳島藩士であった高橋家が、明治維新の後に現在地に土地と家屋を購入。ここで藍の製造を行ったと伝えられています。寛政11年(1799)建築の主屋は、茅葺の主体部四方に瓦葺の庇を設けた「四方蓋(しほうぶた)造り」。正面右に見える瓦葺の長大な建物は、藍製造に用いられたものだと案内にありました。

また、表門左右に連なる練塀(ねりべい)は、小規模な石を多数積み上げ、上部を漆喰塗りとした特徴ある構法が用いられており、建物同様に文化財の指定を受けています。 個人様のお宅ですので、遠くから写真だけ撮らせて頂きました。

------------------------00----------------------
眉山の麓、徳島市南佐古にも、国登録有形文化財に指定された「佐古の浄水場」と呼ばれる煉瓦造のポンプ場が残されています。

大正15年(1926)に建設されたポンプ場は、イギリス積みの煉瓦壁で四周を囲み、内部は一室で漆喰仕上げとなっています。明治時代の徳島では、赤痢や腸チフスなどの伝染病が毎年発生し、全国平均を上回る死亡者を記録していたといいます。明治42年(1909)、徳島市は、市を近代都市に近づける為の事業として水道敷設の方針を発表。17年の歳月を経て佐古ポンプ場が完成させました。当時の費用で260万円。徳島市の年間予算の3倍の巨費を投じた一大事業でした。

------------------------00----------------------
徳島市八万町、文化の森総合公園にある「徳島県立文書館(もんじょかん)」。昭和5年(1930)竣工の「旧徳島県庁舎」の一部が使用されているそうです。

この公園には沢山の地域猫がおり、ボランティアの方々によって管理されています。人間の勝手で野良になった猫たちを、殺処分ではなく自然に減らしていこうと言う試み。 避妊、去勢を徹底させることで、新たな野良猫の誕生を防ぐと言う市の方針は、猫だい好きの私には涙が出るほど嬉しく、この一事だけで徳島市の大ファンになりました。

------------------------00----------------------
折角徳島まで来たのだから、徳島藩25万石の居城「徳島城」に行かねば!と言っても明治6年に発布された廃城令により、残されたのは三の丸石垣などごく僅か。現在は徳島中央公園として一般開放されており、市民の憩いの場になっています。

【阿波の殿様 蜂須賀さまの 今にのこせし 阿波踊り】 踊らにゃ損々!で有名な阿波踊り「よしこの」の一節が刻まれた碑。

そしてこの方が、その有名な阿波踊りを広めたと言われる『蜂須賀家政公』。

公園内にある「竜王さんのクス」は、城山原生林にある樹齢推定600年の楠でしたが、昭和6年(1934)の室戸台風で倒壊。かつて竜王神社の近くにあったことからこの名称がつけられました。

大正12年(1923)に造られた「8620形式・蒸気機関車」。昭和44年まで県内で活躍していましたが、今はこの公園で静かに余生を楽しんでいます。

雨露がしのげ、真冬の冷たい風も防ぐ機関車の隙間は、地域猫たちの安住のねぐら。人の姿に恐れることも無く、ゆったりと身づくろいをする姿に、地域の方たちの人柄がしのばれ、目頭が熱く🙏。

------------------------00----------------------
どの方向から眺めても眉の姿に見える事からその名がついたという「眉山(びざん)」。徳島市のシンボル的存在で「とくしま88景」にも選定されています。ふらり徳島ラストは、この日の車中泊地にさせて頂いた、眉山からの夜景です。

山頂の無料駐車場と言うことで、車泊は・・と気後れする部分もありましたが、以外にもお仲間さんの車が何台も居て、小心者の私も安心して眠ることが出来ました。 市内の近くでこのような場所を利用できる事に、心から感謝いたします🙏🙏

訪問日:2013年3月16日~17日