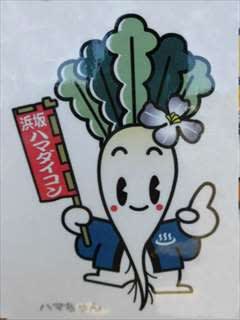相生市(あいおいし)は兵庫県の南西部、西播地域の真ん中に位置する市です。たつの市、赤穂市、上郡町、海を挟んで姫路市に隣接。北部の三濃山、東部の天下台山、西部の宮山等を含め、市の周辺は小高い山に覆われた盆地のようになっており、南はペーロン競漕が行われる相生湾と風光明媚な瀬戸内海に面し、海と山に囲まれた自然豊かなまちです。「市の木:椿」「市の花:コスモス」を制定。

市名は、相生市那波地区にあった大嶋城の城主「海老名氏」が、相模国出自であることから、海=浦名として呼ばれていた「おお」に相模生まれの漢字を宛てたのが「相生」の由来であるという説が有力とされています。
キャッチフレーズは「いのち輝き 絆でつなぐ あいのまち」

明治22年(1889)、町村制の施行により、赤穂郡相生村(おおむら)・那波村・若狭野村・矢野村が発足。
1913年、相生村が町制を施行、赤穂郡相生町となる。
1931年、那波村が町制を施行、赤穂郡那波町となる。
1939年、赤穂郡相生町が那波町を編入。同年4月11日 、 読みを「おお」から「あいおい」に変更。
1942年、赤穂郡相生町が市制を施行、相生市が発足。
1951年、揖保郡揖保川町大字那波野を編入。
1954年、赤穂郡若狭野村・矢野村を編入。現在に至ります。
マンホールには、相生湾特設会場にて毎年実施される相生ペーロン祭の様子と、市の花「コスモス」、市の木「椿」が描かれています。






集落排水マンホール

山陽自動車道:龍野西SA「相生ペーロン祭」

通りすがりに見かけた相生ペーロン祭のモニュメント。

道の駅:あいおい白龍城に展示されていた「ペーロン船」。幅が狭く非常に長いのが特徴で、中国語では龍舟(ドラゴンボート)と呼ばれる事もあるようです。

昭和17年11月12日制定の市章は「カタカナ「アイオイ」の頭文字「ア」の字を相対的に組み合わせたものです。」公式HPより



1992年制定の市旗は「相生市のイニシャル「A」と海のブルーをベースに、船のセイルと波を表現し、未来という大海原へ力強く漕ぎ出していく姿を図案化しています。」公式HPより

西播磨水道企業団を表す「西播水」のロゴと文字が記された消火栓。相生市とたつの市揖保川地域・御津地域で使用されています。

相生市ふるさと応援大使の『ど根性大根 大ちゃん』。2005年8月、相生市那波野の歩道からアスファルトを押しのけて出てきた大根を住民が発見。緑の葉を大きく広げ、行きかう人たちに「アスファルトなんかに負けないぞ!」と元気を与えたとして、全国的に有名になりました。


道の駅:あいおい白龍城には相生湾をバッグに立つ『ど根性大根大ちゃん』の顔出しもあります(*^^*)

撮影日:2008年8月17日&2018年12月14日