
奈良新聞「明風清音」欄に月1~2回程度、寄稿している。昨日(2021.6.17)付で掲載されたのは「半夏生餅、めはりずし」だ。どちらも就職で奈良市に移り住んで以降、初めていただいたものだ。
※トップ写真は「総本家さなぶりや」のさなぶり餅
半夏生餅は、おふさ観音(橿原市小房町)前の「総本家さなぶりや」で見つけた。きな粉や黒蜜がついていたが、何もつけなくても美味しかった。小麦を混ぜた餅なので、独特の食感がある。夏至(今年は6月21日)から数えて11日目が半夏生(はんげしょう)なので、その頃にまた買いに行かなければ。
「めはりずし」はゐざさ寿司(中谷本舗)で「木こり弁当」の名前で店頭販売されていたので、よく買った。子供たちが好きだったので、よく買いに行ったものだ。では、全文を紹介する。
4月15日付の本欄で、鹿谷勲著「茶粥・茶飯・奈良茶碗」(淡交社刊 税込み2420円)を引用し、茶粥のルーツを紹介した。茶粥は弥十郎(または弥二郎)という貧しい男が江戸時代の初め頃、米を食い延ばすために作り始めた。弥十郎の屋敷は現在の奈良市小西さくら通り商店街の西側、石﨑眼科医院のあたりにあったという。
茶粥は柿の葉ずしや三輪そうめんと並ぶ「奈良のうまいもの」であるが、美味しいものなら、まだまだある。今日は県内の伝統的な郷土食として「半夏生(はげっしょう)餅」と「めはりずし」を紹介する。
▼半夏生餅
半夏生(はんげしょう)とは七十二候の一つ(第三十候)で、サトイモ科の半夏(カラスビシャク)が生ずる候という意味だ。夏至から数えて11日目、7月2日頃になる。この日までに田植えを終えないと、秋の収穫が半分になるといわれる。農作業に一段落つけて休みをとり、小麦を混ぜた半夏生餅などを作る。労をねぎらう宴のことを早苗饗(さなぶり)といい、その時に提供される餅なので「さなぶり餅」ともいう。奈良県だけでなく、大阪の河内地方でも作られた。
「前日に洗ってつけておいたもち米と小がらす(唐臼)で精白した小麦を半々に混ぜ、一緒に蒸して搗(つ)く。こね鉢に入れてぬれたふきんで覆っておき、食べたいときにちぎって砂糖を混ぜたきな粉をまぶして食べる。もち米だけのもちよりも歯切れがよく、胃がもたれることがない。日がたってもやわらかい」(「聞き書 奈良の食事」農山漁村文化協会刊)。今、さなぶり餅は「総本家さなぶりや」(橿原市縄手町おふさ観音前)で販売されている。

「十津川うどん古道」のめはりずし
▼めはりずし
「熊野地方を中心に伝わる郷土料理。タカナの漬物の葉の部分で白い飯を包んだ握り飯。名称の由来は、口を大きくあけてかぶりつくと目を見張るような表情になることから、食べると目を見張るほど美味しいことから、といった説がある」(「デジタル大辞泉」)。
地域によっては「薹菜(とうな)ずし」ともいう。
なお「高菜の産地、熊野五郷(いさと=三重県)の庄屋の娘お紺が、大好物の高菜で包んだすしをもって遊女に出たが、後に目をみはるほどの美しい太夫になったため、それを『めはりずし』と呼ぶようになったという一説もある」(「出会い大和の味」奈良新聞社刊)。
奈良県内では、十津川村や上北山村、下北山村などで作られている。以前はゐざさ(中谷本舗・本社は上北山村)の店頭でも「木こり弁当」の名前で販売されていたが、今はなくなった。
私は橿原市の「まほろばキッチン」で見つけた。製造者が「十津川うどん古道」(田原本町味間)となっていたのでお店を訪ねると、あつあつのめはりずし(一個190円)が出てきて、感激したことがある。めはりずしは木こり弁当のネーミングの通り、山に入る男性や、山菜摘みに行く女性が弁当として携行した。
平成25年「和食:日本人の伝統的な食文化」は、ユネスコ無形文化遺産に登録された。そこでは「年中行事との密接な関わり」や「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」が評価された。半夏生餅もめはりずしも、家庭で作る習慣は廃れたが、お店で買って食べることで、伝統的な食文化を継承している。形は変わっても、伝統的な食文化は、末永く引き継いでいきたいものだ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)
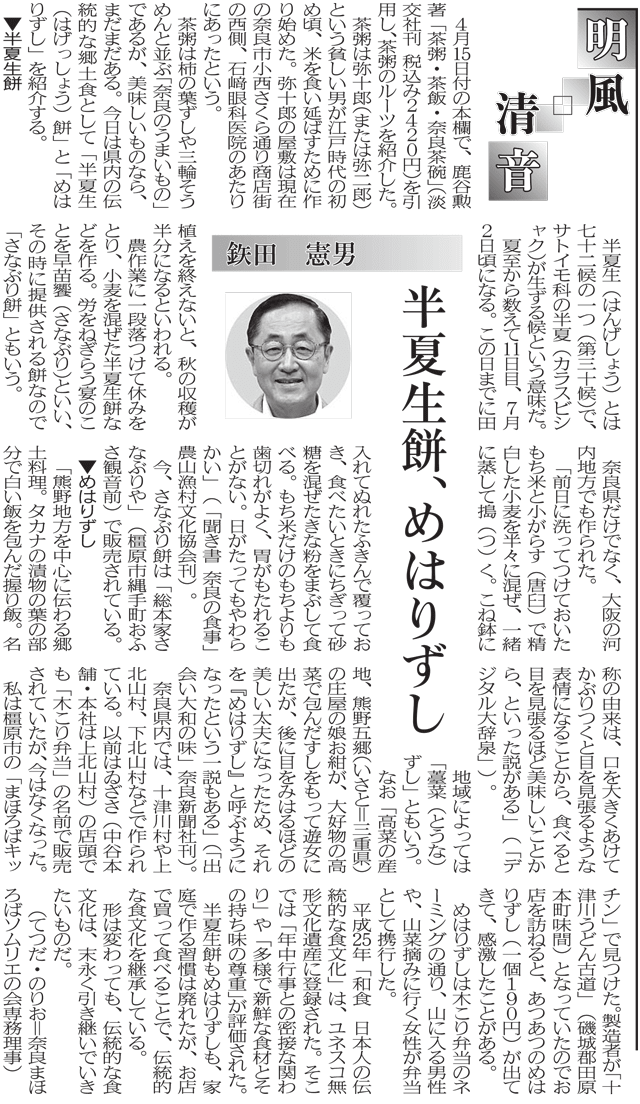
※トップ写真は「総本家さなぶりや」のさなぶり餅
半夏生餅は、おふさ観音(橿原市小房町)前の「総本家さなぶりや」で見つけた。きな粉や黒蜜がついていたが、何もつけなくても美味しかった。小麦を混ぜた餅なので、独特の食感がある。夏至(今年は6月21日)から数えて11日目が半夏生(はんげしょう)なので、その頃にまた買いに行かなければ。
「めはりずし」はゐざさ寿司(中谷本舗)で「木こり弁当」の名前で店頭販売されていたので、よく買った。子供たちが好きだったので、よく買いに行ったものだ。では、全文を紹介する。
4月15日付の本欄で、鹿谷勲著「茶粥・茶飯・奈良茶碗」(淡交社刊 税込み2420円)を引用し、茶粥のルーツを紹介した。茶粥は弥十郎(または弥二郎)という貧しい男が江戸時代の初め頃、米を食い延ばすために作り始めた。弥十郎の屋敷は現在の奈良市小西さくら通り商店街の西側、石﨑眼科医院のあたりにあったという。
茶粥は柿の葉ずしや三輪そうめんと並ぶ「奈良のうまいもの」であるが、美味しいものなら、まだまだある。今日は県内の伝統的な郷土食として「半夏生(はげっしょう)餅」と「めはりずし」を紹介する。
▼半夏生餅
半夏生(はんげしょう)とは七十二候の一つ(第三十候)で、サトイモ科の半夏(カラスビシャク)が生ずる候という意味だ。夏至から数えて11日目、7月2日頃になる。この日までに田植えを終えないと、秋の収穫が半分になるといわれる。農作業に一段落つけて休みをとり、小麦を混ぜた半夏生餅などを作る。労をねぎらう宴のことを早苗饗(さなぶり)といい、その時に提供される餅なので「さなぶり餅」ともいう。奈良県だけでなく、大阪の河内地方でも作られた。
「前日に洗ってつけておいたもち米と小がらす(唐臼)で精白した小麦を半々に混ぜ、一緒に蒸して搗(つ)く。こね鉢に入れてぬれたふきんで覆っておき、食べたいときにちぎって砂糖を混ぜたきな粉をまぶして食べる。もち米だけのもちよりも歯切れがよく、胃がもたれることがない。日がたってもやわらかい」(「聞き書 奈良の食事」農山漁村文化協会刊)。今、さなぶり餅は「総本家さなぶりや」(橿原市縄手町おふさ観音前)で販売されている。

「十津川うどん古道」のめはりずし
▼めはりずし
「熊野地方を中心に伝わる郷土料理。タカナの漬物の葉の部分で白い飯を包んだ握り飯。名称の由来は、口を大きくあけてかぶりつくと目を見張るような表情になることから、食べると目を見張るほど美味しいことから、といった説がある」(「デジタル大辞泉」)。
地域によっては「薹菜(とうな)ずし」ともいう。
なお「高菜の産地、熊野五郷(いさと=三重県)の庄屋の娘お紺が、大好物の高菜で包んだすしをもって遊女に出たが、後に目をみはるほどの美しい太夫になったため、それを『めはりずし』と呼ぶようになったという一説もある」(「出会い大和の味」奈良新聞社刊)。
奈良県内では、十津川村や上北山村、下北山村などで作られている。以前はゐざさ(中谷本舗・本社は上北山村)の店頭でも「木こり弁当」の名前で販売されていたが、今はなくなった。
私は橿原市の「まほろばキッチン」で見つけた。製造者が「十津川うどん古道」(田原本町味間)となっていたのでお店を訪ねると、あつあつのめはりずし(一個190円)が出てきて、感激したことがある。めはりずしは木こり弁当のネーミングの通り、山に入る男性や、山菜摘みに行く女性が弁当として携行した。
平成25年「和食:日本人の伝統的な食文化」は、ユネスコ無形文化遺産に登録された。そこでは「年中行事との密接な関わり」や「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」が評価された。半夏生餅もめはりずしも、家庭で作る習慣は廃れたが、お店で買って食べることで、伝統的な食文化を継承している。形は変わっても、伝統的な食文化は、末永く引き継いでいきたいものだ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)
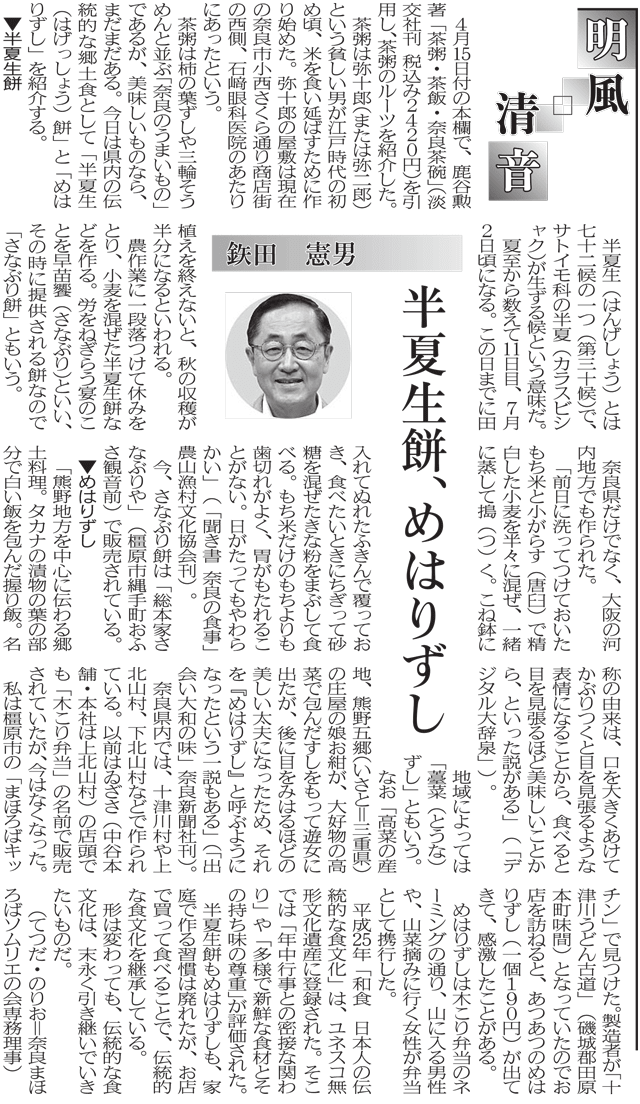




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます