
新刊発売中!!さっそくの重刷決定!ありがとうございます。『とことん解説!タネから始める 無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜』(洋泉社)
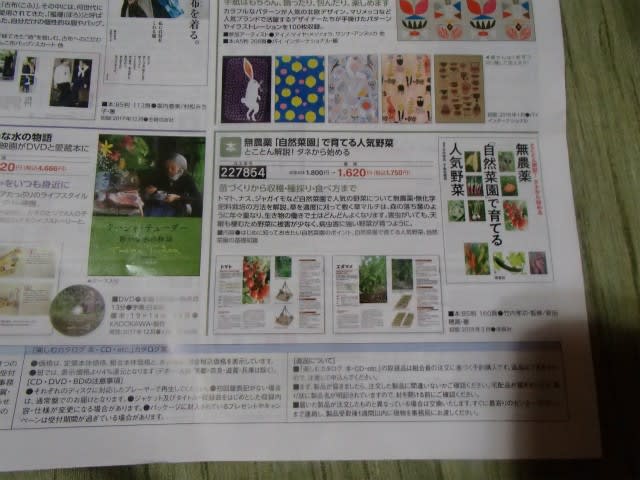
生活クラブの書籍コーナーでも、ご紹介していただきました。
本日、 の予報。
の予報。



昨日は、大岡の小さな田んぼの春起こしを行いました。
稲作には、耕す栽培方法と、不耕起(耕さない栽培方法)がありますが、その田んぼに合わせて、向いている方を選択し、耕すなら徹底的に耕し、中途半端に耕すのはかえって良くないと感じております。
この田んぼは、耕す方法と耕さない方法を両方やってみたところ、耕す方法の方が向いている田んぼだったので、秋起こしに続いて、春起こしを行いました。
田植えまでに、如何に田んぼの稲ワラ(切り株も含む)の分解を進めるかで、コナギなどの田んぼの草の生え方を抑えられるか決まるからです。
田んぼは畑程の水分50~60%がもっとも有機物の分解に適しており、地温が平均10℃以上のときに、微生物の分解も進むため、
適度に乾くまでしっかり待って、よく晴れた昼間に耕すことにしております。
温かい日に耕すと、田んぼの土の中で寝ていた虫やカエルたちが、逃げたり、もう一度土の中にもぐってくれるので、寒い日やしけっている日は避けます。


一昨年新車にした、通常のホンダこまめで田んぼを耕すと、乾いた田んぼの表面しか耕せず、切りワラの分解までは乗用トラクターのように行えないので、
稲刈り脱穀後、一度今回の春起こし同様、土寄せ機のアタッチメントをつけて鋤き耕で行っておき、今回は、米ぬか、クン炭、ゼオライトを補って耕しました。
米ぬかは、ワラの分解を進めてくれる微生物たちのエサであり、クン炭は微生物や根張りを良くしてくれる炭であり、ゼオライトは、ケイ酸を含み、CEC(土の器)を大きくし、稲の茎葉を丈夫にしてくれます。
土寄せ機のアタッチメントの羽を取ったものが最適で、少し面倒でも、1.5往復できるように耕すと、しっかり耕せ、土に空気が入り、凸凹になり表面積が広くなり、ワラの分解を促進してくれます。

この田んぼの水口は低く、水が溜まりやすく、奥は高く水が届きにくいため、箕で、高いところの土を低いところに運び入れ、田んぼ全体が水平になるように調整することが、地味でスがとても大切です。


つつきの棚田で自然菜園スクールで使わせていただいている棚田も同様に、クン炭や米ぬか、ゼオライトなどの量を調整しながら、田植えしやすい深さになるようにしっかり耕しました。
2週間後、水を入れる前に、今度はレーキを搭載し、凸凹の表土を水平になるようにならしながら耕して、5月に入ってしっかり今年のワラの分解がほぼ終わったら、水を入れて、荒代かき、仕上げ代かきで田植えを予定しております。
ただ耕すのではなく、どうしたら、草を抑え、稲が喜び、生き物も保全できるかをよく考え感じながら行います。
天気などに恵まれて、田んぼの土が最大に力を発揮できるように野良仕事を行えて嬉しかったです。
本日開校『無農薬・自然菜園入門講座』4/4(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)、「ジャガイモとネギ」です。

2018年土内容充実で、
城山公民館「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。
毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
この冬の菜園ができない時期にこそ、知っておいてほしい土づくりの基本を行います。
次回から2回にわたって、今度は菜園の環境を調え、病虫害を出にくくし、体力や持久力をつけるトレーニング(菜園プラン)にするのかを行います。
少量多品目を育てることは農家さんでも難しく、家庭菜園ならではの最低限の知識や工夫を学び、病虫害、連作障害が起こりにくく、それでいて野菜を育てれば育てるほど土が良くなっていく菜園プランをご紹介する予定です。
今年度は、いつもの第1水曜日に
長野市城山公民館 18:30~21:25(当日、記録用動画撮影いたしております)
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。
◆次回以降の予定
【テーマ】
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~野菜編~」
4/4(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)、「ジャガイモとネギ」
5/2(水)― 夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、「トマトとキュウリ」
6/6(水)― マメ科で土づくり、「ナスとトウモロコシ」
※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)
お楽しみに~

3/8(木)スタート!! 千曲市戸倉創造館で2018年3~2月に千曲市教室開校します!!
『無農薬無化学肥料でもしっかりやればできる!自給稲作入門講座』
場所:戸倉創造館2階会議室
日時:第2木曜日 18:00~20:45まで(全12回座学のみ)
受講料:1回1,500円、一括申し込み15,000円
対象:米の自給をしたい方。米作りが初めての方大歓迎!
参考テキスト:『自給自足の自然菜園12ヶ月』(宝島社)153~174ページ
●問合せ・申し込み先●
千曲市役所経済部農林課農業振興係服部
電話026-273-1111(内線7244)
Email:nousin@city.chikuma.nagano.jp(件名を「自給稲作入門講座」として送信下さい)


現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。
※最新動画、「畑での野良仕事(実技編)」前編・後編もアップグレードできました。
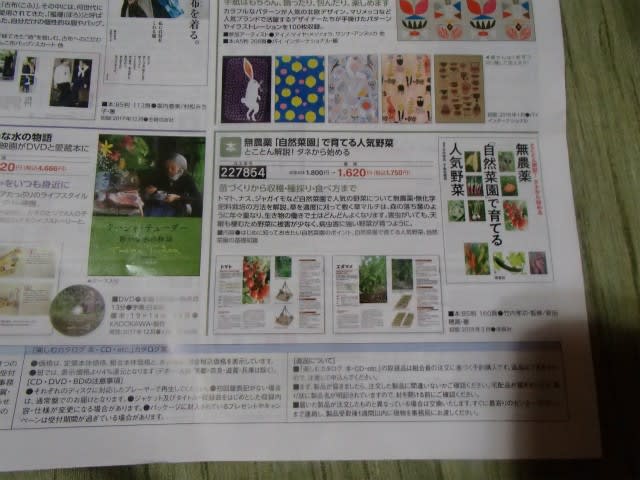
生活クラブの書籍コーナーでも、ご紹介していただきました。
本日、
 の予報。
の予報。


昨日は、大岡の小さな田んぼの春起こしを行いました。
稲作には、耕す栽培方法と、不耕起(耕さない栽培方法)がありますが、その田んぼに合わせて、向いている方を選択し、耕すなら徹底的に耕し、中途半端に耕すのはかえって良くないと感じております。
この田んぼは、耕す方法と耕さない方法を両方やってみたところ、耕す方法の方が向いている田んぼだったので、秋起こしに続いて、春起こしを行いました。
田植えまでに、如何に田んぼの稲ワラ(切り株も含む)の分解を進めるかで、コナギなどの田んぼの草の生え方を抑えられるか決まるからです。
田んぼは畑程の水分50~60%がもっとも有機物の分解に適しており、地温が平均10℃以上のときに、微生物の分解も進むため、
適度に乾くまでしっかり待って、よく晴れた昼間に耕すことにしております。
温かい日に耕すと、田んぼの土の中で寝ていた虫やカエルたちが、逃げたり、もう一度土の中にもぐってくれるので、寒い日やしけっている日は避けます。


一昨年新車にした、通常のホンダこまめで田んぼを耕すと、乾いた田んぼの表面しか耕せず、切りワラの分解までは乗用トラクターのように行えないので、
稲刈り脱穀後、一度今回の春起こし同様、土寄せ機のアタッチメントをつけて鋤き耕で行っておき、今回は、米ぬか、クン炭、ゼオライトを補って耕しました。
米ぬかは、ワラの分解を進めてくれる微生物たちのエサであり、クン炭は微生物や根張りを良くしてくれる炭であり、ゼオライトは、ケイ酸を含み、CEC(土の器)を大きくし、稲の茎葉を丈夫にしてくれます。
土寄せ機のアタッチメントの羽を取ったものが最適で、少し面倒でも、1.5往復できるように耕すと、しっかり耕せ、土に空気が入り、凸凹になり表面積が広くなり、ワラの分解を促進してくれます。

この田んぼの水口は低く、水が溜まりやすく、奥は高く水が届きにくいため、箕で、高いところの土を低いところに運び入れ、田んぼ全体が水平になるように調整することが、地味でスがとても大切です。


つつきの棚田で自然菜園スクールで使わせていただいている棚田も同様に、クン炭や米ぬか、ゼオライトなどの量を調整しながら、田植えしやすい深さになるようにしっかり耕しました。
2週間後、水を入れる前に、今度はレーキを搭載し、凸凹の表土を水平になるようにならしながら耕して、5月に入ってしっかり今年のワラの分解がほぼ終わったら、水を入れて、荒代かき、仕上げ代かきで田植えを予定しております。
ただ耕すのではなく、どうしたら、草を抑え、稲が喜び、生き物も保全できるかをよく考え感じながら行います。
天気などに恵まれて、田んぼの土が最大に力を発揮できるように野良仕事を行えて嬉しかったです。
本日開校『無農薬・自然菜園入門講座』4/4(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)、「ジャガイモとネギ」です。

2018年土内容充実で、
城山公民館「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。
毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
この冬の菜園ができない時期にこそ、知っておいてほしい土づくりの基本を行います。
次回から2回にわたって、今度は菜園の環境を調え、病虫害を出にくくし、体力や持久力をつけるトレーニング(菜園プラン)にするのかを行います。
少量多品目を育てることは農家さんでも難しく、家庭菜園ならではの最低限の知識や工夫を学び、病虫害、連作障害が起こりにくく、それでいて野菜を育てれば育てるほど土が良くなっていく菜園プランをご紹介する予定です。
今年度は、いつもの第1水曜日に
長野市城山公民館 18:30~21:25(当日、記録用動画撮影いたしております)
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。
◆次回以降の予定
【テーマ】
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~野菜編~」
4/4(水)― 春の土づくり(畝立て、クラツキ、緑肥mix)、「ジャガイモとネギ」
5/2(水)― 夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、「トマトとキュウリ」
6/6(水)― マメ科で土づくり、「ナスとトウモロコシ」
※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)
お楽しみに~


3/8(木)スタート!! 千曲市戸倉創造館で2018年3~2月に千曲市教室開校します!!
『無農薬無化学肥料でもしっかりやればできる!自給稲作入門講座』
場所:戸倉創造館2階会議室
日時:第2木曜日 18:00~20:45まで(全12回座学のみ)
受講料:1回1,500円、一括申し込み15,000円
対象:米の自給をしたい方。米作りが初めての方大歓迎!
参考テキスト:『自給自足の自然菜園12ヶ月』(宝島社)153~174ページ
●問合せ・申し込み先●
千曲市役所経済部農林課農業振興係服部
電話026-273-1111(内線7244)
Email:nousin@city.chikuma.nagano.jp(件名を「自給稲作入門講座」として送信下さい)


現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
※有料サイトの都合、登録などの際に一部英語表記になっております。
※最新動画、「畑での野良仕事(実技編)」前編・後編もアップグレードできました。































近所の田んぼの先輩方はそれぞれにこだわりがあり意見がバラバラで…
とても参考になります。
緑肥mix使ってみました。
静電気や風に振り回されたのでちゃんと蒔けたか心配でしたが出てきたので安心しました。
イネ科の子はどれがどの子か全くわかりませんが今後が楽しみです。
ところで小さい種や大きな種、軽い種や重い種が混ざっているのをまるべく上手に蒔けるコツとかありますか?
よく混ぜてから掴むようにしていますが余り気にし過ぎでしょうか…
屋久島(鹿児島)出張のため、ご返信大変遅くなってしまいました。ごめんなさい。
そうでしたか。米ぬかの量と鋤き込む深さなどにもよりますが、水を入れる前までに、ワラと米ぬかが分解がほぼ終わっていることが重要です。
分解が終わっているならば吉(草は抑えられる)。分解が終わっていなければ凶(稲が抑えられ、草が暴れる)ので自然観察して、量とタイミングなどみてください。
私なら、半分はいつも通り、半分は1つだけ違うことを行い、比較試験して稲に意見を聞いてみようと思います。
そうですね。
よく混ぜて播くことも大切ですが、
1)地面近くで播種(風で、比重の違いで飛び方、着地が揃ってしまい混ざらないため)
と、
2)種は必ず、往復して播く。
行きと帰りで、種の量と種類を確認しながら、よく混ざって均一になるように播種する。
のは、緑肥だけでなく、すべて野菜の種まきの基本ですので、今後に活かしてみてください。
スナップエンドウとライ麦を一緒に蒔いた(本を見て)ところその後の誘引が楽でした。
もし叶うなら定番じゃない作物の栽培ポイントも発表してもらいたいです。
これからもご活躍を西方から楽しみにしています。
そうですか。
現在定番でない野菜を「田舎暮らしの本」(宝島社)で毎月健康野菜を健康に育てるをテーマに発表しはじめております。
西にどんどん誘われて、屋久島までいったくらいですので、また機会あれば西方面に伺うことも増えていくかもしれません。その時は楽しみにしていてください。