私は1992年に初めて「北に生きるシカたち」という本を書いた。シカとササのことを軸に、体験を交えながら書いた。この本は河合雅雄先生に望外の評価をいただき、瞬く間に売り切れた。だが、実はこの本は難産だった。どうぶつ社の久木亮一さんは「おもしろくない」と言われた。このときも私は譲歩できないところでは頑として自分を通した。結果としてはそれでよかったと思っている。この本は売り切れてしまったために長い間、手に入らなかったが2014年に丸善から復刻出版された。

その後、7冊の本を書いた。共著を含めれば51冊になる。専門書が多いが、2006年にはもともと書きたいと思っていた若い人向けに岩波ジュニア新書の「野生動物と共存できるか」を出すことができた。この本もよく読まれ、その中の文章は中学生の国語の教科書にも掲載された。子供好きの父が生きていれば喜んでくれたに違いない。

同じ年に「シカの生態誌」を著すことができた。これは今どき珍しい大部な本で、執筆に10年もかかってしまった。私が若い頃から没頭した研究活動と成果を集大成したものになった。

2009年にSpringerから公表された「Sika Deer」はマッカラー先生、梶光一さんと一緒に編集をし、海外に向けてニホンジカの研究成果を紹介するものとなった。初めて欧文書の編集をしたが、充実したものであった。

大学人として最後の年にヤマケイ新書から「唱歌「ふるさと」の生態学」を出すことができた。私は歌が好きで研究室でもよく歌をうたった。「ふるさと」は好きな歌のひとつで、その歌詞を保全生態学の視点で読み解いた。ウサギと茅場の問題は長年取り組んできたシカと植物との関係の延長線上にあったし、魚のこと、水質のこと、林業のこと、社会のことなど、私が研究と並行して関心をもってきたことも総合したものとなった。この本の出版が定年前に間に合ってありがたかった。
つづく

その後、7冊の本を書いた。共著を含めれば51冊になる。専門書が多いが、2006年にはもともと書きたいと思っていた若い人向けに岩波ジュニア新書の「野生動物と共存できるか」を出すことができた。この本もよく読まれ、その中の文章は中学生の国語の教科書にも掲載された。子供好きの父が生きていれば喜んでくれたに違いない。

同じ年に「シカの生態誌」を著すことができた。これは今どき珍しい大部な本で、執筆に10年もかかってしまった。私が若い頃から没頭した研究活動と成果を集大成したものになった。

2009年にSpringerから公表された「Sika Deer」はマッカラー先生、梶光一さんと一緒に編集をし、海外に向けてニホンジカの研究成果を紹介するものとなった。初めて欧文書の編集をしたが、充実したものであった。

大学人として最後の年にヤマケイ新書から「唱歌「ふるさと」の生態学」を出すことができた。私は歌が好きで研究室でもよく歌をうたった。「ふるさと」は好きな歌のひとつで、その歌詞を保全生態学の視点で読み解いた。ウサギと茅場の問題は長年取り組んできたシカと植物との関係の延長線上にあったし、魚のこと、水質のこと、林業のこと、社会のことなど、私が研究と並行して関心をもってきたことも総合したものとなった。この本の出版が定年前に間に合ってありがたかった。
つづく










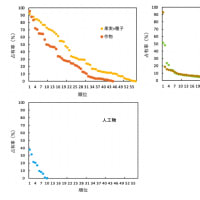
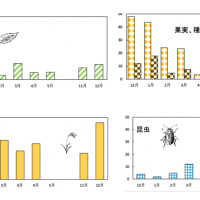








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます