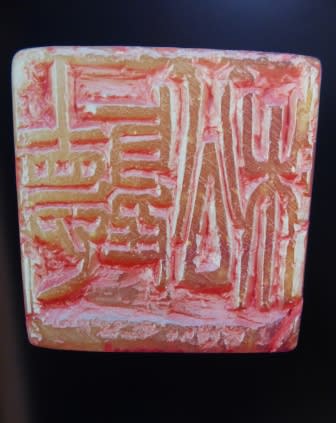10日の土曜日に、お稽古場に行ってまいりました。
大きく生活環境も変化し、4月はお休みしていました。
お伺いしたのは墨華展のみです。
今回は5月の月例競書と大事なお月謝のお納めです。

いつものとおり、朝一番で彩翆さんがお稽古を受けていました。
吉野先生より半切と大きな紙(ニ八)の指導を受けていました。
ご指導内容も奥の深いものです。
墨の重さとか・・・。
*素人的には墨に重さがあるのかな?と思っちゃいます。(笑)


そして、書き順などもです。
同じ字でもいろいろと書き方があるようですね。
ここはこうですよ。と丁寧に説明されていました。
準同人ともなるとこのような指導になるのでしょう。

5月3日(土)朝日新聞の記事です。
これは「ボールペン習字講座」です。
書道とは関係が無いと思いますが、面白い内容でしたのでご紹介いたします。
みなさんはどれに当てはまるのかな?

幅広い年代が「美文字」に関心
女性が75% 女性が25%
関心のあるのは30代・40代60歳代以上となっていました。
彩翆さんが書かれていた大きな紙はなんと言うのですか?
と聞きましたら、二八と言われました。
参考に ↓ に大きさ表を貼っておきます。
|
全紙ぜんし |
2.3×4.5尺 |
70×136.3 |
最も一般的な寸法。全判ぜんばんとも |
|
(全紙の)半切はんせつ |
1.15×4.5尺 |
34.8×136.3 |
(全紙の)幅半分。最も良く使われる |
|
(全紙の)一枚半いちまいはん |
2.3×6.75尺 |
70×204 |
(全紙の)長さ1.5倍 |
|
二×八にはち |
2×8尺 |
60.6×242.4 |
|
|
三×六さぶろく |
3×6尺 |
90.9×181.8 |
|
|
全紙聯落~れんおち |
1.75×4.5尺 |
53×136.3 |
全紙の幅約3/4 |
|
一枚半聯落 |
1.75×6.75尺 |
53×204 |
一枚半の幅約3/4 |
|
八尺聯落 |
1.75×8尺 |
53×242.4 |
二×八の幅約3/4 |
|
半紙はんし |
8寸×1尺1寸 |
24.2×33.3 |
いわゆるお習字用紙 |
|
以下は昨今の展覧会用にスダレが作られた寸法です。 |
|||
|
二×六にろく |
2×6尺 |
60.6×181.8 |
|
|
70×150ななじゅうのひゃくごじゅう |
2.3×4.95尺 |
70×150 |
|
(萬 鶴)