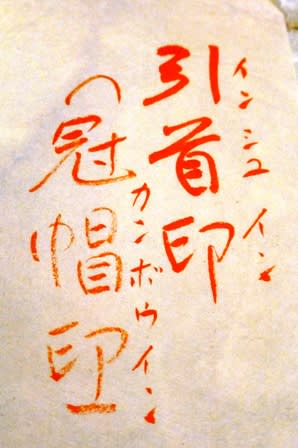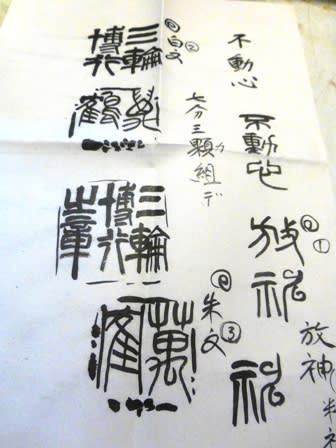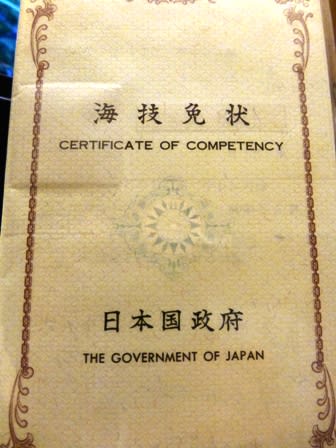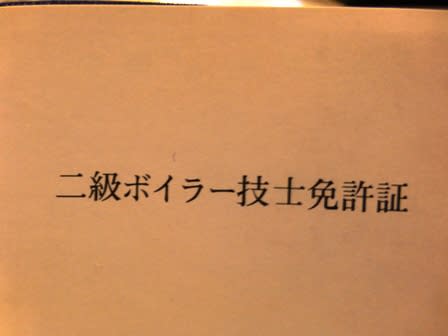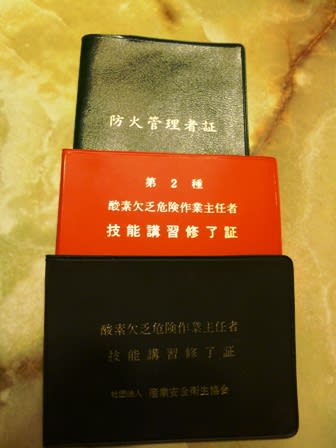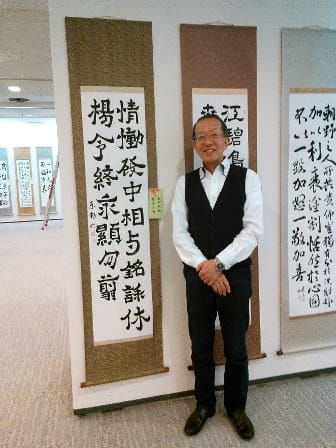私がお稽古場にお伺いするのは土曜日の午前中です。
比較的空いている?(ほぼ順番?)だからです。
とは言っても、月に1回ペースです。
中田仙鶴さんは入門以来欠席したことが無い!と言っておられました。
凄い!の一言です。
さて、今日は硬いタイトルになっちゃいました。
「高 石峯先生の篆刻芸術について」(天)です。

韓国人の篆刻家
若くして比田井天来に、その才能を見出された高石峯。
比田井天来は還暦以後の作には、専ら高石峯の印だけを使用することを言明し、実行した。と残されています。

↑ の写真は天来書院の「知らざれる比田井天来」より引用させていただいております。
お許しを。


吉野大巨先生が秘蔵している、高石峯先生の雅印です。
篆刻に興味を持つ私にいただきました。

そして、一枚のコピーも・・・。
「高 石峯先生の篆刻芸術について」と題し、桑原翆邦先生が書かれているものです。
高石峯先生との初対面は、私の上京の年、昭和7年の秋頃ではなかったかと思う。
天来先生の代々木の書学院の客室で、偶然に同席したのがご縁の始まりだった。
その席で天来先生は石峯先生の印影の中の一つ・・・文末で「人生一楽」だったと思う・・・
を見て感嘆され、それが機縁で先生にその後しばらく、書学院で起臥されることになった。・・・

大巨先生も改めて、印影集をご覧になっています。



そして、秘蔵の雅印をお出しになりました。
石が赤いのは印でいが付いて汚れた訳ではありません。
確かぁ・・・「鳥血石」とか?
お持ちになっているもので一番高価だとか?
これが土曜日午前中のお稽古場です。
篆刻を含めて、全くの初心者ですので無知を失礼いたします。
萬 鶴