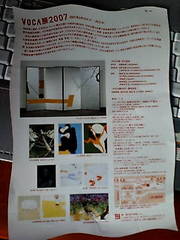♪~ あの日、湯島聖堂の白い石の階段に腰掛けて・・・
さだまさしさんの代表曲の1つに“檸檬(レモン)”という曲があります。
以前ご紹介した“私歌集(アンソロジー)”というアルバムに収められていて、シングルカットされたばかりか、確かドラマの主題歌にもなっていたように思います。
このところ家にいることが少なくギターの弦も緩めっぱなしだったのですが、先ほど久しぶりに調弦してこの記事を書くためにさだまさしさんの曲を何曲か弾き語りしてみました・・・。
あ、ヘタになってる・・・。
まだ落ちるべき底があったのだと、ある意味感動しております。(泣)
もちろん“檸檬”も演ってみましたが・・・う~ん。
ギターを初めて手にしたころ、この曲なんかはキーがEmなのでわりかし早く弾けるようになっちゃったんですね。もちろん右手は全部ストロークだったですが・・・。
他にEmの曲といえば“飛梅”とか“まほろば”、さださん以外なら松山千春さんの“季節の中で”(※カポ1)、アリスの“チャンピオン”(※カポ2)などなど・・・これらの曲がなかったらギター弾くのもメゲて、諦めてたかもしれません。
さて、話を元に戻しましょう。
冒頭の歌詞は“檸檬”の歌いだしです。
まず舞台は湯島聖堂・・・。そして“白い石の階段”にズーム・イン!!
写真は入徳門という一番下の山門から、大成殿の入口に当たる杏壇門に至る階段なのですが・・・
ホントにここかなぁ~?
もしかしたら大成殿の脇の白い石のところじゃないかなぁ~。
でもあれは階段じゃないしなぁ~。
などといろいろ疑惑もありますが、その後の歌詞で“陽だまりのなかへ盗んだ檸檬、細い手でかざす”という件があるので、ここでは脇に木々があり木漏れ日の陽だまりができるという点と、盗んだレモンである以上大成殿の人目に付くところでいちゃいちゃしていることはないだろうという点に着目して、やはりこの階段が舞台であるということにしておきましょう。
いずれにせよ我々は一つの現場を押さえたのです!!
次の現場(私が立ってるところ)は“聖橋”です。御茶ノ水から秋葉原方面を見ています。

“湯島聖堂”と“ニコライ堂”を結ぶ橋だから“聖橋”って言うんですってね。
そして眼下にはアノ“神田川”。ここが神田川であることも知りませんでした・・・。
そういえば“神田川”も典型的なEmキーの曲ですよね。
このころ四畳半フォークなどといわれていましたが、“三畳一間の小さな下宿”に二人で住んでるなんて何てつましいんでしょうか?
これでは一畳半フォークですもんね。
おっと“檸檬”に戻りましょう。この歌の歌詞に、以下のような件があります。
♪~ 喰べかけの檸檬聖橋から放る 快速電車の赤い色がそれとすれ違う・・・
♪~ 喰べかけの夢を聖橋から放る 各駅停車の檸檬色がそれを噛み砕く・・・
聖橋からの景色を見ていたときには、目前の線路を走る電車を歌っていると思っていました。
でも帰ってこの記事を書くに当たり、グーグル・マップで位置関係を確認したところ意外な事実が分かったのです!
この線路は・・・なになに地下鉄(東京メトロ)の丸ノ内線が地上を走る部分だって!?
ということは、快速もくそもない。全て各駅停車じゃないですか!
実は、この写真の右端の先のほうにJR御茶ノ水駅があります。
そして、写真の奥のほうに見えるか見えないかの橋がありますが、これが御茶ノ水駅から秋葉原駅に向かうJRの総武線の各駅停車の路線なのです。
快速電車のJR中央線は神田駅に向かうため、この写真より右側に大きく外れていくことになります。
ところで、現場を踏まえたからこそ理解できたことがあります。
快速電車の場合には、聖橋の今立っているところではなく湯島聖堂側ぎりぎりの地点から御茶ノ水駅方面にレモンを投げたんだなということ。
これなら歌詞のとおりの状況が再現可能です。
いくら距離があっても電車と投げたレモンが重なればいいんですから・・・。
ただし今の快速電車の色は、バーミリオンオレンジ(国鉄朱色1号)です。
当時は赤だったのでしょうか?
まあ、赤っぽいといえばそう言えなくもないので許容範囲ということでよしとすることにしましょう。
しかし問題は各駅停車の方です。
いくらさだまさしさんが野球小僧で、自分の持っている野球チームのピッチャーだったとしても眼下の丸ノ内線に届かせることすら難しいでしょうに、総武線の線路に落として電車に轢かせるというのはムリです!
そして私が見た電車は・・・銀色。
わずかに車体側面のラインがレモン色でした。
まあこれも昔はレモン色だったのかも知れないわけですから、ここはひとつ大人になって不問に伏しましょう!
ただ、放り投げたレモンが川面に落ちて波紋を描いたということを告白しているからには、「川を汚さないように!」とひとこと注意を促しておかなければ!
よいこはゼッタイにまねしちゃダメですよ・・・。
ここも懺悔室で贖罪しながら歌詞を書いたんだろうということで、次に行きましょうか・・・。
信じられないかもしれませんが、今日の本題はここからなのです。(^^)/
さだまさしさんの楽曲はかねてよりその詞の世界が定評あるところでした。
私は逆に彼のメロディーラインに魅せられていたのですが、もちろん歌詞が素晴らしいということについても異論はありません。
この曲をさっき歌ってみて、ハタと気付いたことがあります。
これこそが彼の詩が鮮やかなイメージを構成する大きな要因ではないかと、にわかに睨まずにはおれないような発見でした!
キーワードはズバリ“色”。
この曲の色にまつわる箇所を抜き出してみると・・・
・白い石の階段
・蒼い空
・金糸雀(カナリア)色の風
・快速電車の赤い色
・各駅停車の檸檬色
こうして見るとインクジェット・プリンターのマゼンダ・シアン・イエローがきちんと押えられています。
さらに深読みすると湯島聖堂の敷地自体が常緑樹木に覆われているので、緑も入っているとみるべきかもしれません。これで色の三原色もおさえられたことになります。あくまでも、湯島聖堂のロケーションを知ってる人限定の効果ではありますが・・・。
要するに、さだまさし楽曲の歌詞(少なくとも“檸檬”)は“極彩色”だったということが判明したのです!!
30年近くこの曲と付き合ってきて、これは大きな感動であります!!!
と、書き手ひとりで盛り上がるのはよくない傾向なので、ここでお写真ブレイクをいれましょう。
このあと更に、めくるめくさだまさしさんの色彩ワールドに切り込んでみたいと思います。
《コーヒー・タイム(私の)》
2月25日に代々木公園で見た桜です。河津桜みたいに開花が早いですねぇ~。

♪~ めぐり逢う時は 花びらの中 ほかの誰よりも きれいだったよ
別れ行く時も花びらの中 君は最後までやさしかった・・・
この写真を早く見せたいばっかりにこんなことしたんだろう・・・とお思いのあなた。
正解です!
でも、あながちそればっかりでもないんですよ!! (^^)v
先の歌詞は“つゆのあとさき”というこれまたさだまさしさんの名曲の一節です。
思えばこの曲が私が彼の曲に惹かれた嚆矢となったもの・・・
思い出深い一曲でしてねぇ。
まぁ“檸檬”だとか“つゆのあとさき”さらには“セロ弾きのゴーシュ”なんて曲もあって、2枚(連続)のアルバムの中にこうも著名な文学作品の名前が並んでいたということも、何か自分がアカデミックな文学通になったような気がして、読んでもいないのにエラくなったように錯覚してたのを思い出します。
解説には陶淵明なんてのもあった・・・っていうのは先の記事でもご紹介しましたっけ。
おいおい“檸檬”色の考察記事ではないのかい!?
という声が聞こえてきそうですが、私はあっさり「そうですよ!」と言い張るのです。(^^)/
すなわち、この歌はサビに至り次のように歌われますが・・・
♪~ 梅雨のあとさきのトパーズ色の風は 遠ざかる 君のあとをかけぬける
さて、ここでまたも“トパーズ色”なる新しい色が現われました。
この曲にも仔細に見ると“梅雨のあとさき”は果たして卒業シーズンなんだろうかという疑問もありますが、卒業を期に新しい生活に入った彼女が1カ月余りで疎遠になってとうとう後姿を見せるにいたったと考えられなくもないので、多くは語らないでおきましょう・・・ってしっかり言っちゃってますね。。。(^^)/
ここで似非文学通の私としては、ひとつの有名な詩を思い起こさずにはいられないわけであります。
それは高村光太郎の“智恵子抄”のなかの有名なこの作品です。
「これならエセ文学通じゃなくても知っているぞ」と思ったとしても言わないこと!
そんなにもあなたはレモンを待つてゐた
かなしく白いあかるい死の床で
私の手からとつた一つのレモンを
あなたのきれいな歯ががりりと噛んだ
トパアズいろの香気が立つ
その数滴の天のものなるレモンの汁は
ぱつとあなたの意識を正常にした
( 後 略 )
そう“レモン哀歌”です。 どうです? ちゃんと“レモン”してるでしょ!!
そしてここにも現われる“トパアズいろ”。
さてさて、ここまで現われた色を整理してみたいと思います。
(1)さだまさし
“檸檬”よりかじった檸檬を持つ手の描写 ⇒ 指の隙間から・・・“カナリア色”の風が舞う
(2)高村光太郎
“レモン哀歌”より智恵子が噛んだレモンの描写 ⇒ “トパアズいろ”の香気が立つ
(3)さだまさし
“つゆのあとさき”より ⇒ 梅雨のあとさきの“トパーズ色”の風は・・・
表記の仕方はそろえるとして、論理学的(おおアカデミック!)に展開するとおおよそ次のようになるのではないでしょうか?
前提として(1)および(2)においては、いずれもレモンから発せられる一種の“香気”を色に喩えたものであるということはご了解いただけますよね!
1.言うまでもなく(2)と(3)の“トパーズ色”は同値である。
2.(1)と(2)はレモンの香気を色に喩えたものである。故に(1)(2)も同値である。
3.故に(1)(2)(3)は同値である。
∴ “カナリア色” ≡ “トパーズ色” であることが証明される。
真ん中の“≡”はこの式が恒等式であることを示しています。
論理学的に間違っているところがあったとしても、雰囲気に浸っているだけなので大目に見てもらうとして、カナリア色とトパーズ色は歌詞を交換しても意味は同じということになるのです!!
って、そんなことする人いませんよねぇ・・・。
ここで終わるわけに行かないので、もうひとつややこしい事実を提起すると・・・
総武線の“檸檬色”に喩えられた電車の色を『日本の鉄道ラインカラー一覧』に照らして調べると、何と!!
“カナリアイエロー(国鉄黄色1号)!”というらしい。
ということは、
“カナリア色” ≡ “トパーズ色” = “檸檬色(カナリアイエロー)”
という式も成り立つのではないか!?
ちょっと自信がないので、“檸檬色”は恒等式ではなくイコールにしたものの、実は3本と2本のちがいはよく知らない私・・・。
こうなってしまうと何が何色やら分からないので、トパーズという宝石がどんな色をしているか調べてやれ!!!
というわけで“ウィキペディア”を当ってみました。(“>”以下ウィキペディアより引用)
>トパーズ(topaz)は、水晶より少し硬い珪酸塩鉱物。和名は黄玉(おうぎょく)。
>11月の誕生石。
>フッ素やアルミニウムを含み、様々な色を呈するが、宝石としては淡褐色のものが上質とされる。
なるほど、やはり“黄玉”とか淡褐色とか黄色系なのね・・・。でも・・・
>トパーズの色のあれこれ
>インペリアルトパーズ : シェリーカラー(黄褐色から橙褐色;橙~黄~褐)
>ブルートパーズ : 青、藍 放射線照射されたものが多い
>シャンペントパーズ : 薄茶色 天然ブラウンカラー
>グリーントパーズ : 放射線処理されたものが多い
>ピンクトパーズ : 『OH-タイプ』
>カラーレストパーズ :無色;外見はダイヤモンドに似る
>ミスティックトパーズ : チタニウム照射技術でトリートメント
出てきた色をまとめると・・・無色、淡褐色、淡黄色、黄色、淡青、淡紅、・・・
って、一体何色なのよ!!!!!
んでもって、本日の結論。
“カナリア色” ≡ “トパーズ色” = “檸檬色” ⊂ “玉虫色”
おそまつ!!!!!
《3月18日追記》
本日所用でまた御茶ノ水近辺をほっつき歩いた時にハッシと気づいたことがありますので、ご参考までに追記しておきます。
写真は聖橋より秋葉原方面ではなく、反対側の次ぎの駅“水道橋”方面を見た映像です。

要するに、橋の反対側から電車の車両を見た・・・ということになります。
なんと、眼前に御茶ノ水駅が見えるでは有りませんか!?
記事を書いたときには、秋葉原の方を向いていろいろ考察したのですが、車道を渡った橋の逆側の景色を何も考慮に入れておりませんでした・・・。
迂闊でしたねぇ~。
これなら、さだまさしさんの歌詞どおりのシチュエーションが可能でありますし、歌自体はフィクションであったとしても景色としてはこの方がイメージに相応しいような気がいたします。
快速電車の赤(オレンジだけど・・・)、その向こうに確かに総武線のレモン色(車両側面にレモン色の線が入っています。昔は車両丸ごとレモン色であったようです)の車両が見えます。
そんなことに気づいたもので、この文章を補足させていただきました。記事に記載したことがやはり見当違いのことであったなら申し訳有りませんでした。
取り急ぎ、ご報告だけさせていただきます。