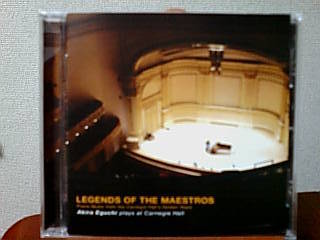★舟歌~フォーレ:ピアノ作品集
(演奏:クン=ウー・パイク)
1.無言歌 作品17の3
2.夜想曲 第1番 作品33の1
3.夜想曲 第3番 作品33の3
4.即興曲 第2番 作品31
5.夜想曲 第6番 作品63
6.舟歌 第1番 作品26
7.夜想曲 第11番 作品104の1
8.夜想曲 第13番 作品119
9.即興曲(8つの小品より)作品84の5
10.無言歌 作品17の1
11.前奏曲 作品103の2
12.前奏曲 作品103の7
13.バラード作品19
(2001年録音)
私は何かあらたまって本などを読んだりすると、すぐその主張するところに影響されることがあります。
もとより、このバックステージで妄言を吐きまくっているのにお付き合いいただいている方には、レコ芸の月評子のセンセイよりもなおディスクの演奏の内外を問わず言いたいことを言っている・・・何がしか当該演奏に影響されたことをホザきまくっているわけですから、そんなことは判っていると仰る向きもありましょう・・・。(^^;)
そんな尻軽な私ではありますが、一方では生まれた時からDNAに刷り込まれていたかのごとく中日ドラゴンズをこよなく愛し、ま、いちおうカミさんにも感謝の念を忘れずこよなく愛してることにしているのと共に、日本・日本語というものにもひとかたならぬ思い入れをもっているつもりの徒でもあります。
「人は言語で思考する」といえば全く当たり前のことなのかもしれませんが、実はこれって大問題なんじゃないでしょうか。
というのは、高島俊男さんという方が著されている「漢字と日本人」という文春新書から出ている本を読んでいろいろ感じるところがありました。
で、あっさり影響されちゃったんですが、ここは音楽関連のスペースといういことをわきまえることにして関連すると思われることだけを述べるにとどめます。
要するに細かいことはおいておいて、『音楽』っていうのもその存在意義においても何かを伝えようという目的を有しているものなんですよね・・・ということを改めて再確認したい、こういうことです。
かの楽聖ベートーヴェン先生も「心より出でて、心に届かんことを」とのたまわっておられるとおりですよね。(^^;)
じゃ、何を心から取り出してみせ、何を先様の心に届けたいのか・・・“音響”をなんていったら、はったおされるでしょうね。。。
それは“何がしかの気分”ではないかと直感的に思うのですが、これって言語、そしてそれを表記する手段である文字に置き換えるというのはとっても至難なことなんじゃないでしょうか?
(かく言う私はこうしてほとんど毎日それらしいことを続けているのではありますが・・・。)
作曲家は表現したい“気分”を惹起させしめうる音の配置やら強度やらを、そのセンスと呼ばれうるであろう自身にすり込まれたいわば“思い込み”との遠近感から巧みに採否を繰り返してひとつの曲をこしらえる・・・という作業をしているのでしょう。
ですから、作曲もひとつの翻訳作業といえると思います。
では、作曲家は常日頃なにで思考しているかというと当然ながらその日常使っている言語であります。
言語の背後には当然にその国の哲学・歴史があり、さらに細かく見ればその人(この場合は作曲家)のそれも概ね被さってくるんでしょう。
では、その音楽を真に理解し楽しむためにはその言語にも通じていなくてはいけないのか?
作曲家理解ということで、その作曲家について深く研究考察し、その作曲家が愛した本や思想などについても想いをいたしたうえで演奏をするとおっしゃるアーティストはいっぱいいますが、作曲家の思想などにもっとも大きな影響を与えているのは実は母国語なのではないでしょうか?
そうであるとすれば、音を楽しむのにもすくなからずその言語に通暁していないとその真意はわからないこともありうるのではないでしょうか?
フォーレは「女性的なところはあるが、少しも女々しくない」という作曲家でサロンなどでは人気者であったらしいのですが、そのことは当時のフランスにおいてどのような意味づけがあったのかももちろんですが、フランスではそれが是とされるお国柄なのか非なのか・・・そしてその理由は何なのかもわたしにはわからない。
実はそんなよく知らない人が作った楽曲を、その曲をよく勉強したであろうけれどその勉強の中身をほとんど知らされていない異国の演奏家がディスクを発表する場合には、例えばこのクン=ウー・パイクという韓国随一の大迫力のヴィルトゥオジティを誇るピアニストが演奏した場合には、それがしなやかで瑞々しくていかに私の心を打ったとしても、フォーレが正しく楽譜に書き落としたその気分を表現しているのであろうか・・・という点において不安になるのです。
リサイタルのプログラミングからこの上なく魅力的な、こんなディスクであればこそなおさらです。
実は母国であるフランスのピアニストによるフォーレ(コラールは聴いたことないんですが)よりも、ずっと自分の心の琴線に触れてくるのですが・・・。
ご存知かどうか判りませんがメラビアンの法則というのがあって、人が何かを話して伝えようとする時に何が影響するのかの研究結果があります。
それによると60%弱は態度・身だしなみ等、35%余が声のトーンなどに影響されるのであり、言葉それ自体は7%の影響に過ぎないといわれているようです。
音楽には言葉は声楽曲など以外はありませんよね。
そうすると先の“気分”を伝える要素って何によるんでしょう?
音楽もそんな伝達手段であるとすれば言葉の代替品という要素もあると思うのですが、これは果たして何語なんでしょう?
人間にある程度普遍的に備わっている共通認識に立脚しているのだとすれば、言語とは切り離して考えるべきなんでしょうかね?
好きな演奏家がいる、好きな作曲家もある・・・その方たちの思考には国籍をこえて私と共通する何かがあるんでしょうか?
ベートーヴェンの運命の第4楽章なんかを聴いて鼓舞されない人種はないんでしょうから、きっとそんな要素も在るにはあるんでしょうね。
確かにいろんな演奏に触れることで私の受け入れうる“気分”の範囲は広がっているのですが・・・それが作曲者のそれと、演奏者のそれとイコールといえるかどうかが心もとない・・・そして必ずしもそれでいいとは思えない。
繰り返しますが、パイクの素晴らしい演奏を聴くにつけ「これが本当のフォーレなのか?」と何度も自問自答してしまいました。(^^;)
本当のフォーレなんて知らないし、フランス人の弾くフォーレが本当なのかもわからないですけどね。
私の好むフォーレの演奏は、実は全然フォーレ的じゃなかったりして・・・。
ん~、なんか意味不明で、中途ハンパな記事になっちゃいましたね。
すんませんこってす・・・。
ところで、高島さんの本にもいろいろ考えされられるところがありました。
自分はこれまで中島敦のような漢文調の文体を非常にカッコよく思うものでしたが、日本語・とくに文字の生い立ちやこれまでの経緯、そして今後日本の文化をおもうとき、つとめてかなをつかうのが望ましいと考えるに至ったからです。
ただでさえダラダラ書くクセがあるので、漢字の熟語を廃してかなを多くすると余計に長くなるからいままでどおりに書いていこうと思っておりますが・・・。(^^;)
(演奏:クン=ウー・パイク)
1.無言歌 作品17の3
2.夜想曲 第1番 作品33の1
3.夜想曲 第3番 作品33の3
4.即興曲 第2番 作品31
5.夜想曲 第6番 作品63
6.舟歌 第1番 作品26
7.夜想曲 第11番 作品104の1
8.夜想曲 第13番 作品119
9.即興曲(8つの小品より)作品84の5
10.無言歌 作品17の1
11.前奏曲 作品103の2
12.前奏曲 作品103の7
13.バラード作品19
(2001年録音)
私は何かあらたまって本などを読んだりすると、すぐその主張するところに影響されることがあります。
もとより、このバックステージで妄言を吐きまくっているのにお付き合いいただいている方には、レコ芸の月評子のセンセイよりもなおディスクの演奏の内外を問わず言いたいことを言っている・・・何がしか当該演奏に影響されたことをホザきまくっているわけですから、そんなことは判っていると仰る向きもありましょう・・・。(^^;)
そんな尻軽な私ではありますが、一方では生まれた時からDNAに刷り込まれていたかのごとく中日ドラゴンズをこよなく愛し、ま、いちおうカミさんにも感謝の念を忘れずこよなく愛してることにしているのと共に、日本・日本語というものにもひとかたならぬ思い入れをもっているつもりの徒でもあります。
「人は言語で思考する」といえば全く当たり前のことなのかもしれませんが、実はこれって大問題なんじゃないでしょうか。
というのは、高島俊男さんという方が著されている「漢字と日本人」という文春新書から出ている本を読んでいろいろ感じるところがありました。
で、あっさり影響されちゃったんですが、ここは音楽関連のスペースといういことをわきまえることにして関連すると思われることだけを述べるにとどめます。
要するに細かいことはおいておいて、『音楽』っていうのもその存在意義においても何かを伝えようという目的を有しているものなんですよね・・・ということを改めて再確認したい、こういうことです。
かの楽聖ベートーヴェン先生も「心より出でて、心に届かんことを」とのたまわっておられるとおりですよね。(^^;)
じゃ、何を心から取り出してみせ、何を先様の心に届けたいのか・・・“音響”をなんていったら、はったおされるでしょうね。。。
それは“何がしかの気分”ではないかと直感的に思うのですが、これって言語、そしてそれを表記する手段である文字に置き換えるというのはとっても至難なことなんじゃないでしょうか?
(かく言う私はこうしてほとんど毎日それらしいことを続けているのではありますが・・・。)
作曲家は表現したい“気分”を惹起させしめうる音の配置やら強度やらを、そのセンスと呼ばれうるであろう自身にすり込まれたいわば“思い込み”との遠近感から巧みに採否を繰り返してひとつの曲をこしらえる・・・という作業をしているのでしょう。
ですから、作曲もひとつの翻訳作業といえると思います。
では、作曲家は常日頃なにで思考しているかというと当然ながらその日常使っている言語であります。
言語の背後には当然にその国の哲学・歴史があり、さらに細かく見ればその人(この場合は作曲家)のそれも概ね被さってくるんでしょう。
では、その音楽を真に理解し楽しむためにはその言語にも通じていなくてはいけないのか?
作曲家理解ということで、その作曲家について深く研究考察し、その作曲家が愛した本や思想などについても想いをいたしたうえで演奏をするとおっしゃるアーティストはいっぱいいますが、作曲家の思想などにもっとも大きな影響を与えているのは実は母国語なのではないでしょうか?
そうであるとすれば、音を楽しむのにもすくなからずその言語に通暁していないとその真意はわからないこともありうるのではないでしょうか?
フォーレは「女性的なところはあるが、少しも女々しくない」という作曲家でサロンなどでは人気者であったらしいのですが、そのことは当時のフランスにおいてどのような意味づけがあったのかももちろんですが、フランスではそれが是とされるお国柄なのか非なのか・・・そしてその理由は何なのかもわたしにはわからない。
実はそんなよく知らない人が作った楽曲を、その曲をよく勉強したであろうけれどその勉強の中身をほとんど知らされていない異国の演奏家がディスクを発表する場合には、例えばこのクン=ウー・パイクという韓国随一の大迫力のヴィルトゥオジティを誇るピアニストが演奏した場合には、それがしなやかで瑞々しくていかに私の心を打ったとしても、フォーレが正しく楽譜に書き落としたその気分を表現しているのであろうか・・・という点において不安になるのです。
リサイタルのプログラミングからこの上なく魅力的な、こんなディスクであればこそなおさらです。
実は母国であるフランスのピアニストによるフォーレ(コラールは聴いたことないんですが)よりも、ずっと自分の心の琴線に触れてくるのですが・・・。
ご存知かどうか判りませんがメラビアンの法則というのがあって、人が何かを話して伝えようとする時に何が影響するのかの研究結果があります。
それによると60%弱は態度・身だしなみ等、35%余が声のトーンなどに影響されるのであり、言葉それ自体は7%の影響に過ぎないといわれているようです。
音楽には言葉は声楽曲など以外はありませんよね。
そうすると先の“気分”を伝える要素って何によるんでしょう?
音楽もそんな伝達手段であるとすれば言葉の代替品という要素もあると思うのですが、これは果たして何語なんでしょう?
人間にある程度普遍的に備わっている共通認識に立脚しているのだとすれば、言語とは切り離して考えるべきなんでしょうかね?
好きな演奏家がいる、好きな作曲家もある・・・その方たちの思考には国籍をこえて私と共通する何かがあるんでしょうか?
ベートーヴェンの運命の第4楽章なんかを聴いて鼓舞されない人種はないんでしょうから、きっとそんな要素も在るにはあるんでしょうね。
確かにいろんな演奏に触れることで私の受け入れうる“気分”の範囲は広がっているのですが・・・それが作曲者のそれと、演奏者のそれとイコールといえるかどうかが心もとない・・・そして必ずしもそれでいいとは思えない。
繰り返しますが、パイクの素晴らしい演奏を聴くにつけ「これが本当のフォーレなのか?」と何度も自問自答してしまいました。(^^;)
本当のフォーレなんて知らないし、フランス人の弾くフォーレが本当なのかもわからないですけどね。
私の好むフォーレの演奏は、実は全然フォーレ的じゃなかったりして・・・。
ん~、なんか意味不明で、中途ハンパな記事になっちゃいましたね。
すんませんこってす・・・。
ところで、高島さんの本にもいろいろ考えされられるところがありました。
自分はこれまで中島敦のような漢文調の文体を非常にカッコよく思うものでしたが、日本語・とくに文字の生い立ちやこれまでの経緯、そして今後日本の文化をおもうとき、つとめてかなをつかうのが望ましいと考えるに至ったからです。
ただでさえダラダラ書くクセがあるので、漢字の熟語を廃してかなを多くすると余計に長くなるからいままでどおりに書いていこうと思っておりますが・・・。(^^;)