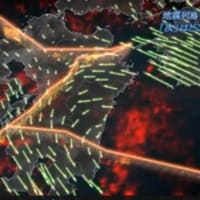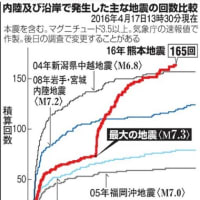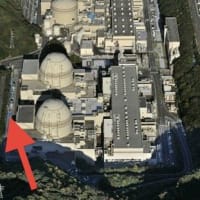人間というのは、つくづく保守的にできているものです。今回の道路財源一般化に関する知事さんたちの反応を見るとそう思います。
生命の本質は現状維持ですから仕方ないといえば仕方ない。急激な環境変化を我々は非常に嫌います。異常事態が生じると、まず身体をぎゅっと縮める。これは防御姿勢です。こうやって、危険を避けようとするのです。
これを心理的な観点から見れば、新しい事態に対してなんでも拒否する姿勢ということです。こうやって、事態に耐えようとするわけです。新しいものに対する拒否感というのは、だいたいこういうものでしょう。
事態が重大なものほどそうなります。たとえば、私の「先見力訓練法」であげた例ですと、黒船来航のときの諸大名の反応ですね。
「こりゃあ、たいへんだ」ということで、まず敵を追い払えという反応が出てくる。攘夷論です。ところが、だんだん時間がたって、緊張に慣れてくると、もう少しよく見てみようじゃないかということになる。その結果、いかに戦争が無謀なことかが理解できてきます。
ということで、数年後に日米修好条約を結ぶときには、ほとんどの藩が「やむなし」ということになった。反対したのは水戸の徳川斉昭とその子供たちだけという状況でした。
もっとも、その後、攘夷を唱える人はさらに増え、長州藩は頑強な攘夷派となりましたが、これも下関砲撃事件(1863-1864)で列強に砲弾をぶち込まれ、ようやく宗旨替えとなりました。薩摩藩も同年薩英戦争で、攘夷の無理を悟りました。
考えてもまとまなことがわからんやつは、最後は頭に大砲をぶち込まれることになります。
知事さんたちの反応もそんな感じです。最初は、予算がたてられないと、大慌てでみな大反対。しかし、日経新聞の今朝の記事によると、日経のアンケートに「全国の知事のうち10人が賛成、または条件付きで容認」と返答したとあります。また、反対は6人で、保留が半数以上だったそうです。
反対の急先鋒だった東国原知事は「方向は間違っていないが、時間をかけて結論を出すべきだ」とずいぶん変わってきています。おそらく、こういうあたりに意見は収斂していくと思いますね。
だいたい、新しいことは、初めは拒否反応を招くものです。しかし、世論の声を聞き、また冷静に事態を眺める時間が与えられれば、次第にまともなところに意見は落ち着きます。しかし、道路族あたりはまだ、頑強に抵抗するでしょう。結局彼らの運命は、長州藩や薩摩藩同様になると推理します。
話を戻しますが、革新を行う人は、最初に拒否反応に会ってもあわてないことで、時間をかけて、相手の緊張がほぐれるのを待つ余裕が必要です。
バーナード・ショーはこの点で、非常に気の利いた言い方をしています。
――すべて偉大なる真理は、最初は冒瀆の言葉として出発する。
ところで、新しい事態に対する反応ですが、外ばかりでなく、身内にも目配りしなければなりません。下手をすると、士気がいっせいに落ちますからね。
それに対する処方箋については、初代南極越冬隊長の西堀栄三郎さんの言葉を思い起こすべきでしょう。私の『暗示型戦略』の一節から引用します。
「西堀隊長は、南極越冬に出かける前、北海道の厳寒の地で隊員たちと暮らし、南極越冬の予行演習をしている。そこでは隊員の訓練はもちろんのこと、犬ぞりの訓練、越冬のための食糧開発、機器の耐寒テストなど、広範囲にわたるテストが行われた」
こうやって、いろいろな問題点をあぶりだしたわけです。西堀さんは、「論理的リスク対策」と呼んでいます。つまり、事前調査の結果をもとに、論理的に考えうるリスクすべてを拾い上げ、それを徹底的につぶしていく対策です。
たとえば、サッカーの国際試合で相手の国で戦うとなれば、そのときの天候やらグランドの芝の状態などを調べるのは、いまでは当たり前でしょう。
それにしても、岡ちゃんはバーレン戦ではドジを踏みました。なにしろ、国際親善試合で一度も試したことのない3バックシステムを、本試合でいきなり採用してしまったんですからねえ。
それまで、選手はオシム流のTバック、じゃなかった4バックシステムでやってきましたからね。選手は混乱するに決まっていますよ。私も混乱していますね。
岡田さんのやりようは、私のようなマネジメントを見る者からすれば、狂気の沙汰です。監督の資質を正直疑ってしまいます。
それと、気になるのは、この人は3バックが根っから好きなようなんですが、これをやっていたら、いつまでたっても世界標準にはなれないという話を聞いたことがあります。そのあたり、どうなんでしょうか。案外監督交代が早いかもしれませんよ。
ようやく「新製品の芽を育てる」の話にたどりつきました。フー~。私の話はほんとにいつも回しゲリですねえ。仕方ない。なにしろ伝動戦略の著者なもんで。
伝動戦略というのは、「回し蹴り」のようなものですからね。突然、後頭部に相手の足が飛んでくるような戦略なんですよ。よかったら、私の本をお読みください。この本をアマゾンに頼むと3週間も待たされるようで、まったくどうかしている。仕事が甘いぞ、アマゾンさん。アマゾンじゃなくて、大甘損だ。
なんだっけ、すぐ本題を忘れてしまう。そうそう、論理的リスク削減策でした。とにかく、テスト、テストです。模擬試験ですね。全部を一時に模擬試験しなくてもいいのです。部分的にテストするだけでも価値がある。
だから、試験のときに試験会場に下見に行くのも意味ある行為です。一度行けば、ずいぶん落ち着きますからね。それに電車の乗り換えで迷うこともなくなるし。
新しいサービスを行うときは、テストを繰り返すことで、できるだけ未知の要因を少なくすることが大事です。ですから、まったく新規分野に参入するなどは、かなり危険な行為です。
私は経営コンサルティングをやっていて、あるとき老人福祉分野の調査をするようになったのですが、これもまったくの未知分野というわけではありませんでした。コンサルティングの分析手法は、福祉の調査でも使えるからです。
それにしても、ずいぶんメンタリティーが違うものだと思いましたよ。民間企業や民間人とつきあうのは気楽でいいです。
中央の役人というのは、へんな臭みがある。見下したようなところが。区役所や都庁のお役人さんもそれぞれ独特の雰囲気があります。それで、あまり私は続きませんでしたが、いろんな人間がいるものだと思いました。もっとも、民間企業のなかにもへんな人は多いですがね。
生命の本質は現状維持ですから仕方ないといえば仕方ない。急激な環境変化を我々は非常に嫌います。異常事態が生じると、まず身体をぎゅっと縮める。これは防御姿勢です。こうやって、危険を避けようとするのです。
これを心理的な観点から見れば、新しい事態に対してなんでも拒否する姿勢ということです。こうやって、事態に耐えようとするわけです。新しいものに対する拒否感というのは、だいたいこういうものでしょう。
事態が重大なものほどそうなります。たとえば、私の「先見力訓練法」であげた例ですと、黒船来航のときの諸大名の反応ですね。
「こりゃあ、たいへんだ」ということで、まず敵を追い払えという反応が出てくる。攘夷論です。ところが、だんだん時間がたって、緊張に慣れてくると、もう少しよく見てみようじゃないかということになる。その結果、いかに戦争が無謀なことかが理解できてきます。
ということで、数年後に日米修好条約を結ぶときには、ほとんどの藩が「やむなし」ということになった。反対したのは水戸の徳川斉昭とその子供たちだけという状況でした。
もっとも、その後、攘夷を唱える人はさらに増え、長州藩は頑強な攘夷派となりましたが、これも下関砲撃事件(1863-1864)で列強に砲弾をぶち込まれ、ようやく宗旨替えとなりました。薩摩藩も同年薩英戦争で、攘夷の無理を悟りました。
考えてもまとまなことがわからんやつは、最後は頭に大砲をぶち込まれることになります。
知事さんたちの反応もそんな感じです。最初は、予算がたてられないと、大慌てでみな大反対。しかし、日経新聞の今朝の記事によると、日経のアンケートに「全国の知事のうち10人が賛成、または条件付きで容認」と返答したとあります。また、反対は6人で、保留が半数以上だったそうです。
反対の急先鋒だった東国原知事は「方向は間違っていないが、時間をかけて結論を出すべきだ」とずいぶん変わってきています。おそらく、こういうあたりに意見は収斂していくと思いますね。
だいたい、新しいことは、初めは拒否反応を招くものです。しかし、世論の声を聞き、また冷静に事態を眺める時間が与えられれば、次第にまともなところに意見は落ち着きます。しかし、道路族あたりはまだ、頑強に抵抗するでしょう。結局彼らの運命は、長州藩や薩摩藩同様になると推理します。
話を戻しますが、革新を行う人は、最初に拒否反応に会ってもあわてないことで、時間をかけて、相手の緊張がほぐれるのを待つ余裕が必要です。
バーナード・ショーはこの点で、非常に気の利いた言い方をしています。
――すべて偉大なる真理は、最初は冒瀆の言葉として出発する。
ところで、新しい事態に対する反応ですが、外ばかりでなく、身内にも目配りしなければなりません。下手をすると、士気がいっせいに落ちますからね。
それに対する処方箋については、初代南極越冬隊長の西堀栄三郎さんの言葉を思い起こすべきでしょう。私の『暗示型戦略』の一節から引用します。
「西堀隊長は、南極越冬に出かける前、北海道の厳寒の地で隊員たちと暮らし、南極越冬の予行演習をしている。そこでは隊員の訓練はもちろんのこと、犬ぞりの訓練、越冬のための食糧開発、機器の耐寒テストなど、広範囲にわたるテストが行われた」
こうやって、いろいろな問題点をあぶりだしたわけです。西堀さんは、「論理的リスク対策」と呼んでいます。つまり、事前調査の結果をもとに、論理的に考えうるリスクすべてを拾い上げ、それを徹底的につぶしていく対策です。
たとえば、サッカーの国際試合で相手の国で戦うとなれば、そのときの天候やらグランドの芝の状態などを調べるのは、いまでは当たり前でしょう。
それにしても、岡ちゃんはバーレン戦ではドジを踏みました。なにしろ、国際親善試合で一度も試したことのない3バックシステムを、本試合でいきなり採用してしまったんですからねえ。
それまで、選手はオシム流のTバック、じゃなかった4バックシステムでやってきましたからね。選手は混乱するに決まっていますよ。私も混乱していますね。
岡田さんのやりようは、私のようなマネジメントを見る者からすれば、狂気の沙汰です。監督の資質を正直疑ってしまいます。
それと、気になるのは、この人は3バックが根っから好きなようなんですが、これをやっていたら、いつまでたっても世界標準にはなれないという話を聞いたことがあります。そのあたり、どうなんでしょうか。案外監督交代が早いかもしれませんよ。
ようやく「新製品の芽を育てる」の話にたどりつきました。フー~。私の話はほんとにいつも回しゲリですねえ。仕方ない。なにしろ伝動戦略の著者なもんで。
伝動戦略というのは、「回し蹴り」のようなものですからね。突然、後頭部に相手の足が飛んでくるような戦略なんですよ。よかったら、私の本をお読みください。この本をアマゾンに頼むと3週間も待たされるようで、まったくどうかしている。仕事が甘いぞ、アマゾンさん。アマゾンじゃなくて、大甘損だ。
なんだっけ、すぐ本題を忘れてしまう。そうそう、論理的リスク削減策でした。とにかく、テスト、テストです。模擬試験ですね。全部を一時に模擬試験しなくてもいいのです。部分的にテストするだけでも価値がある。
だから、試験のときに試験会場に下見に行くのも意味ある行為です。一度行けば、ずいぶん落ち着きますからね。それに電車の乗り換えで迷うこともなくなるし。
新しいサービスを行うときは、テストを繰り返すことで、できるだけ未知の要因を少なくすることが大事です。ですから、まったく新規分野に参入するなどは、かなり危険な行為です。
私は経営コンサルティングをやっていて、あるとき老人福祉分野の調査をするようになったのですが、これもまったくの未知分野というわけではありませんでした。コンサルティングの分析手法は、福祉の調査でも使えるからです。
それにしても、ずいぶんメンタリティーが違うものだと思いましたよ。民間企業や民間人とつきあうのは気楽でいいです。
中央の役人というのは、へんな臭みがある。見下したようなところが。区役所や都庁のお役人さんもそれぞれ独特の雰囲気があります。それで、あまり私は続きませんでしたが、いろんな人間がいるものだと思いました。もっとも、民間企業のなかにもへんな人は多いですがね。