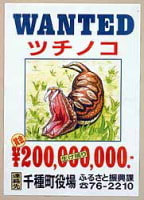●「金魚すくい」で使用される金魚
1 小赤(7~22円) 一般的な金魚。小さめのワキン。もっとも小さく軽いが動きは速い。
2 黒出目金(15~30円) 出目金(デメキン)
3 姉金(25~35円) 大きな小赤。
4 大物(250~500円) 目玉となる派手で高価な金魚。数は多くない。
・ペット用等の金魚の市場で選別の際に撥ねられた、商品価値の低い個体を使うビジネスとして金魚すくいが営まれていることが多い。
・カッコ内の価格は業者での夏季のもの。金魚は時価で売られるのが一般的で、流通の少ない春にはこの約1.5倍に上がる。
・これらは金魚すくい業界での呼称で、正式な品種とは異なっている。
●ポイ
・柄の付いたプラスチック等の輪に紙の膜が貼られたものが主流。店によっては最中(もなか)に針金を指したものを使う場合もあるが近年は少ない。
・金魚すくいに必須の道具。水に浸すとあっという間にもろくなる。
・ポイは紙の厚さによって4号~8号と種類がある。号数が大きくなるほど紙が薄くなる。
・店によっては、2種類の厚さのポイを使用している。
なぜか?それは、あまりすくえそうにない、子供や女性に対しては厚い紙。いっぱいすくいそうな男性客に対しては薄い紙という使い分けをしているから。
・簡単に見分ける方法
金魚すくい屋さんの裏手にまわり、ポイの箱を探すこと。
ポイの箱があればラッキー♪
箱にポイの厚さ(号数)が書いてある。
※号数‥とりあえず5号が厚くて、7号が薄いと覚えておこう。
・分かり難いがポイには表裏があり、枠の縁に紙が乗っている面が表、乗っていない面が裏で、金魚すくいには表面が適している。
●金魚すくい
・背が低く面積の広い水槽に入れられた金魚をすくう遊び。
・縁日の代表的な屋台の1つ。
・金魚の養殖が盛んな奈良県大和郡山市では、観光事業として1995年から毎年8月に「全国金魚すくい選手権大会」が開かれている。
●「全国金魚すくい選手権大会」奈良県大和郡山市
・8月第3日曜日は「金魚すくいの日」に開催
・第12回大会 平成18年8月20日開催
出場選手数: 小中学生の部411名 一般の部641名
最高匹数者 49匹 鈴木さん 小中学生の部
・第11回大会 平成17年8月21日開催
出場選手数:小中学生の部405名 一般の部631名
最高匹数者 35匹 大久保さん 一般の部
・第10回大会 平成16年8月22日開催
出場選手数:小中学生の部407名 一般の部632名
最高匹数者 61匹 上村さん 準決勝で記録
<ルール> 一部
◎競技はすべて3分間に1人1枚のポイ(すくい網)で何匹すくえるかを競います。
◎競技は片手(利き腕)だけで行って下さい。
ボールは水に浮かせた状態にし、遠くに流された場合は、ポイを持っている手で自分の方に引き寄せて下さい。
◎ポイは柄の部分を持って下さい。円の部分を持つのは反則です。
◎3分以内であっても、金魚がすくえない状態までポイが破れた場合は、審判員から競技終了の判定があります。その後、金魚がすくえないポイの枠で金魚を引っかけてすくおうとするのは動物愛護の精神に反しますので、失格になります。
※団体戦は、必ず3人一組で申し込んでください。
<金魚すくい認定大会>
4月22日(日) 静岡下田大会 あずさ山の家
5月3日(木) 九州大会 長洲大会(熊本県) 金魚と鯉の郷広場
5月3日(木) 東灘大会(兵庫県) サンシャインワーフ神戸2階
5月5日(土) 大阪空港大会 大阪国際空港
7月16日(祝) 福山大会(広島県) 福山ロッツ地下1階
7月21日(土) 防府大会(山口県) 羽嶋松翠園
7月22日(日) 柏原大会(大阪府) オガタ通り商店街中央
7月29日(日) 川西大会(兵庫県) アステ川西TEMPO175
8月4日(土) たつの大会(兵庫県) 揖保川河川敷千鳥ヶ浜
グラウンド内
8月5日(日) 鈴鹿大会(三重県) 弁天山公園
8月5日(日) 東住吉大会(大阪府) 東住吉区民ホール
●金魚すくい~ネットゲーム
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kingyo/game/index.htm
●金魚すくいの極意
・水面近くでじっとしている金魚は狙い目である。
・また尾からすくうと破れるため、頭からすくうのがよい。
・ポイを水に漬けるときはいっきに全面をつける。
・金魚を追いかけない。
・紙に水圧がかからないように斜めに入れる。
・金魚すくいには、数匹のかなり大きめの金魚や小さめのコイなどが入っている‥これらは目玉商品‥通称「紙破り」
決してこいつらを狙ってはいけない!
参考にしたHP
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kingyo/index.htm
http://portal.nifty.com/special04/09/05/
http://www1.kcn.ne.jp/~puni/skill/index.html
ウィキペディア(Wikipedia)
1 小赤(7~22円) 一般的な金魚。小さめのワキン。もっとも小さく軽いが動きは速い。
2 黒出目金(15~30円) 出目金(デメキン)
3 姉金(25~35円) 大きな小赤。
4 大物(250~500円) 目玉となる派手で高価な金魚。数は多くない。
・ペット用等の金魚の市場で選別の際に撥ねられた、商品価値の低い個体を使うビジネスとして金魚すくいが営まれていることが多い。
・カッコ内の価格は業者での夏季のもの。金魚は時価で売られるのが一般的で、流通の少ない春にはこの約1.5倍に上がる。
・これらは金魚すくい業界での呼称で、正式な品種とは異なっている。
●ポイ
・柄の付いたプラスチック等の輪に紙の膜が貼られたものが主流。店によっては最中(もなか)に針金を指したものを使う場合もあるが近年は少ない。
・金魚すくいに必須の道具。水に浸すとあっという間にもろくなる。
・ポイは紙の厚さによって4号~8号と種類がある。号数が大きくなるほど紙が薄くなる。
・店によっては、2種類の厚さのポイを使用している。
なぜか?それは、あまりすくえそうにない、子供や女性に対しては厚い紙。いっぱいすくいそうな男性客に対しては薄い紙という使い分けをしているから。
・簡単に見分ける方法
金魚すくい屋さんの裏手にまわり、ポイの箱を探すこと。
ポイの箱があればラッキー♪
箱にポイの厚さ(号数)が書いてある。
※号数‥とりあえず5号が厚くて、7号が薄いと覚えておこう。
・分かり難いがポイには表裏があり、枠の縁に紙が乗っている面が表、乗っていない面が裏で、金魚すくいには表面が適している。
●金魚すくい
・背が低く面積の広い水槽に入れられた金魚をすくう遊び。
・縁日の代表的な屋台の1つ。
・金魚の養殖が盛んな奈良県大和郡山市では、観光事業として1995年から毎年8月に「全国金魚すくい選手権大会」が開かれている。
●「全国金魚すくい選手権大会」奈良県大和郡山市
・8月第3日曜日は「金魚すくいの日」に開催
・第12回大会 平成18年8月20日開催
出場選手数: 小中学生の部411名 一般の部641名
最高匹数者 49匹 鈴木さん 小中学生の部
・第11回大会 平成17年8月21日開催
出場選手数:小中学生の部405名 一般の部631名
最高匹数者 35匹 大久保さん 一般の部
・第10回大会 平成16年8月22日開催
出場選手数:小中学生の部407名 一般の部632名
最高匹数者 61匹 上村さん 準決勝で記録
<ルール> 一部
◎競技はすべて3分間に1人1枚のポイ(すくい網)で何匹すくえるかを競います。
◎競技は片手(利き腕)だけで行って下さい。
ボールは水に浮かせた状態にし、遠くに流された場合は、ポイを持っている手で自分の方に引き寄せて下さい。
◎ポイは柄の部分を持って下さい。円の部分を持つのは反則です。
◎3分以内であっても、金魚がすくえない状態までポイが破れた場合は、審判員から競技終了の判定があります。その後、金魚がすくえないポイの枠で金魚を引っかけてすくおうとするのは動物愛護の精神に反しますので、失格になります。
※団体戦は、必ず3人一組で申し込んでください。
<金魚すくい認定大会>
4月22日(日) 静岡下田大会 あずさ山の家
5月3日(木) 九州大会 長洲大会(熊本県) 金魚と鯉の郷広場
5月3日(木) 東灘大会(兵庫県) サンシャインワーフ神戸2階
5月5日(土) 大阪空港大会 大阪国際空港
7月16日(祝) 福山大会(広島県) 福山ロッツ地下1階
7月21日(土) 防府大会(山口県) 羽嶋松翠園
7月22日(日) 柏原大会(大阪府) オガタ通り商店街中央
7月29日(日) 川西大会(兵庫県) アステ川西TEMPO175
8月4日(土) たつの大会(兵庫県) 揖保川河川敷千鳥ヶ浜
グラウンド内
8月5日(日) 鈴鹿大会(三重県) 弁天山公園
8月5日(日) 東住吉大会(大阪府) 東住吉区民ホール
●金魚すくい~ネットゲーム
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kingyo/game/index.htm
●金魚すくいの極意
・水面近くでじっとしている金魚は狙い目である。
・また尾からすくうと破れるため、頭からすくうのがよい。
・ポイを水に漬けるときはいっきに全面をつける。
・金魚を追いかけない。
・紙に水圧がかからないように斜めに入れる。
・金魚すくいには、数匹のかなり大きめの金魚や小さめのコイなどが入っている‥これらは目玉商品‥通称「紙破り」
決してこいつらを狙ってはいけない!
参考にしたHP
http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/kingyo/index.htm
http://portal.nifty.com/special04/09/05/
http://www1.kcn.ne.jp/~puni/skill/index.html
ウィキペディア(Wikipedia)