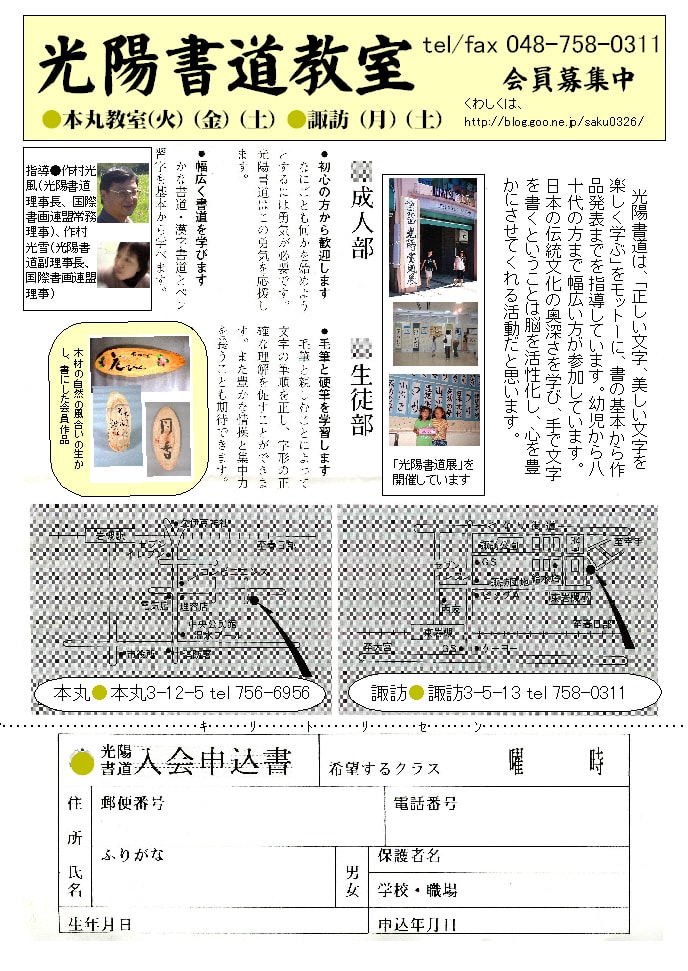第33回 光陽書道展は
さいたま市 氷川の杜(もり)文化会館展示室で、
6/17-18の両日開催することが決まりました。
氷川神社の参道に位置し、静かな大人の雰囲気の展示会場です。
大宮での開催は、10数年ぶり?

氷川の杜文化館
-----------------------------------------------------------------
◇施設概要
氷川の杜文化館は、氷川参道沿いの緑豊かな場所に立地する伝統文化の拠点施設です。能楽、狂言、日本舞踊、三曲などの本格的な練習の場として、また、茶道や華道などの活動の場としてご利用されています。
◇アクセス
JR : 大宮駅東口下車徒歩15分
◇所在地
住 所 … 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1
電話番号 … 048-648-1177
FAX 番号 … 048-648-1311
さいたま市 氷川の杜(もり)文化会館展示室で、
6/17-18の両日開催することが決まりました。
氷川神社の参道に位置し、静かな大人の雰囲気の展示会場です。
大宮での開催は、10数年ぶり?

氷川の杜文化館
-----------------------------------------------------------------
◇施設概要
氷川の杜文化館は、氷川参道沿いの緑豊かな場所に立地する伝統文化の拠点施設です。能楽、狂言、日本舞踊、三曲などの本格的な練習の場として、また、茶道や華道などの活動の場としてご利用されています。
◇アクセス
JR : 大宮駅東口下車徒歩15分
◇所在地
住 所 … 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1
電話番号 … 048-648-1177
FAX 番号 … 048-648-1311
観音経の最古の記録、木簡が出土 奈良・石神遺跡
2006年 3月 9日 (木) 20:55
奈良県明日香村の石神(いしがみ)遺跡(飛鳥時代)で、観世音(かんぜおん)経(観音経)について国内最古の記録となる木簡が見つかった。奈良文化財研究所が9日、発表した。679年に写経を届けたことを依頼主へ報告する内容で、「686年に天武天皇の病気平癒のため観音経が読まれた」という日本書紀の記述を7年さかのぼる。当時、現世利益を求める観音信仰が広く浸透していたことを裏付ける資料となりそうだ。
同遺跡は、天武天皇の母である斉明天皇の迎賓館などがあったとされ、木簡は溝跡から出土した。縦18.6センチ、幅2.3センチ、厚さ4ミリで、表に「己卯(きぼう)年八月十七日白奉経」、裏に「観世音経十巻記白也」と丁寧に墨書されていた。「679年8月17日、観世音経10巻を書写したことを報告いたします」などと読めるといい、写経を届ける際に添えたものらしい。
また、別の溝跡から「間人内」と墨書された土器の破片(7世紀後半)も見つかった。前の文字が欠けて解釈は不明だが、天武天皇の姉で、孝徳天皇の后(きさき)になった間人皇女(はしひとのひめみこ)に関係するものという見方もある。
同村の飛鳥池遺跡(飛鳥時代)で「観世音経巻」と書かれた木簡の出土例があるが、時期は特定できていない。日本書紀は、天武天皇が亡くなる2カ月前の686年7月、観音経を大官大寺(だいかんだいじ)で読経させ、8月には観音像100体を宮中に据えて観音経を読ませたと記している。
現地説明会は11日午後1時半から。近鉄橿原神宮前駅の東約2キロ。
◇
〈キーワード・観音経〉 法華経の第25章が独立したもので、観音菩薩(ぼさつ)の名を唱えればあらゆる苦難から救われると説く。飛鳥時代に伝来し、現世利益を求めて観音信仰が急速に広まったといわれる。平安以降は西国三十三カ所などの巡礼も盛んになった。仏像では、奈良県斑鳩町の法隆寺にある651年の銘の観音菩薩像が国内最古とされている。
2006年 3月 9日 (木) 20:55
奈良県明日香村の石神(いしがみ)遺跡(飛鳥時代)で、観世音(かんぜおん)経(観音経)について国内最古の記録となる木簡が見つかった。奈良文化財研究所が9日、発表した。679年に写経を届けたことを依頼主へ報告する内容で、「686年に天武天皇の病気平癒のため観音経が読まれた」という日本書紀の記述を7年さかのぼる。当時、現世利益を求める観音信仰が広く浸透していたことを裏付ける資料となりそうだ。
同遺跡は、天武天皇の母である斉明天皇の迎賓館などがあったとされ、木簡は溝跡から出土した。縦18.6センチ、幅2.3センチ、厚さ4ミリで、表に「己卯(きぼう)年八月十七日白奉経」、裏に「観世音経十巻記白也」と丁寧に墨書されていた。「679年8月17日、観世音経10巻を書写したことを報告いたします」などと読めるといい、写経を届ける際に添えたものらしい。
また、別の溝跡から「間人内」と墨書された土器の破片(7世紀後半)も見つかった。前の文字が欠けて解釈は不明だが、天武天皇の姉で、孝徳天皇の后(きさき)になった間人皇女(はしひとのひめみこ)に関係するものという見方もある。
同村の飛鳥池遺跡(飛鳥時代)で「観世音経巻」と書かれた木簡の出土例があるが、時期は特定できていない。日本書紀は、天武天皇が亡くなる2カ月前の686年7月、観音経を大官大寺(だいかんだいじ)で読経させ、8月には観音像100体を宮中に据えて観音経を読ませたと記している。
現地説明会は11日午後1時半から。近鉄橿原神宮前駅の東約2キロ。
◇
〈キーワード・観音経〉 法華経の第25章が独立したもので、観音菩薩(ぼさつ)の名を唱えればあらゆる苦難から救われると説く。飛鳥時代に伝来し、現世利益を求めて観音信仰が急速に広まったといわれる。平安以降は西国三十三カ所などの巡礼も盛んになった。仏像では、奈良県斑鳩町の法隆寺にある651年の銘の観音菩薩像が国内最古とされている。