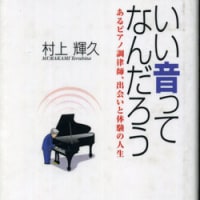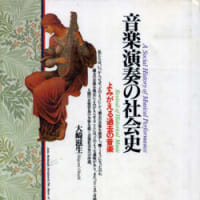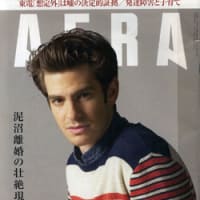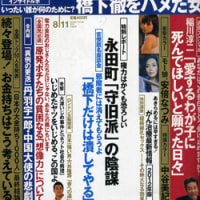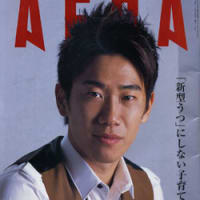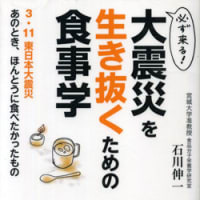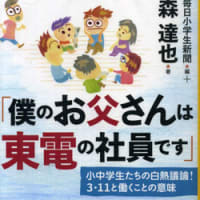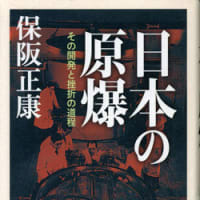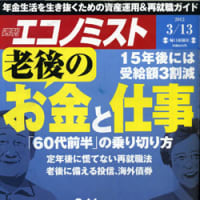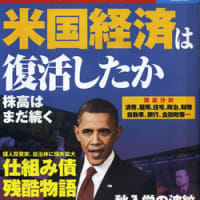『日本の原点シリーズ 木の文化2 檜』
大澤一登・編/新建新聞社出版部2003年
写真が豊富にあります。
--ヒノキも美しいものですね。

日本の文化を支えてきたとボクは思う……。下「」引用。
「ヒノキは昔から日本の木の文化を支え、その形成に大いに貢献してきた。「日本書記」の中に、「スギとクスノキは船に、ヒノキは宮殿に、マキ(槇)は棺にせよ」とあるのは、よく知られている。日本書紀に記されているということは数千年も前、相当古い時代からヒノキが宮殿建築用として使われて、最適最高の材であることが証明されていたことになる。」
どうして、「ひのき」という名がついたか? 下「」引用。
「「ひのき」という和名は「火の木」の意味で、古代にこの木を使って火をおこしたことによるとされている。「ヒ」には「良い」という意味があるため、ヒの木と呼ばれたという説もある。」
「日本の木の王様 木曽檜」下「」引用。
「長野県上松町にある赤沢自然休養林(通称「赤沢美林」)は、木曽林業を代表する古い歴史を持つとともに、森林浴の地としても知られている。-略-」
大正5年、上松駅→赤沢にむかう小川森林鉄道が開設。
現在、かつての小川線の一部を観光用に復活。
裏木曽(神宮備林 350年前の天然更新)
--世界遺産に値するこの森林。
世界に誇る法隆寺の五重の塔……。下「」引用。
「法隆寺の昭和の大修理したときに、取り替えた材は35%だけで、残りの65%は千三百年前そのままの木を使っていると聞いています。もし、法隆寺がケヤキやマツを使ってあったら、だいたい六百年くらいしかもたないでしょう。スギで千年から八百年くらい。ヒノキだから千三百年以上も塔を支えているんだと思いますね。」
かしこまった舞台……。下「」引用。
「スギは少し暖かいが、ヒノキは冷たい。スギが作業場など冷えては困るところに使われたのに対して、ヒノキはピリッと身を引き締めるようなかしこまったところに使われてきた。「ヒノキ舞台」という言葉もあるのも納得できよう。」
遺跡から……。下「」引用。
「遺跡から出土する木材の樹種を全国的に調べてみると、ヒノキの木材はスギの丸木舟が出土したことで知られる福井県三方郡三方町の鳥浜貝塚遺跡が最も古いようである。ここでは縄文時代の草創期から前期にかけて地層から出土した自然木(昔の人々が利用した痕跡のない木材)約32000点のうち20点がヒノキであった。-略-この遺跡から人々がさまざまに良した木材も出土している。最も古いものは約1万年前の杭でわずか2点であるが、約6千年前の縄文時代前期になるとたくさんの杭、板材、そして図に示したスプーン状の木器、また彫刻のある細長い板などがあり、生活に密着したヒノキ材の利用を既に見てとれる。」
校舎「贄川(にえかわ)小学校【長野県・贄川村】
「まちづくりの核として日本一の総檜づくり校舎の保存 旧甲良東小学校【滋賀県・甲良町】」
「中国南部トン族の集落に見る木の文化ルーツ」
「へぎ目の美しさを生かす」木曽福島 曲物師・村地忠太郎
「国産ヒノキにもあった! ヒノキチオール」
 もくじ
もくじ


大澤一登・編/新建新聞社出版部2003年
写真が豊富にあります。
--ヒノキも美しいものですね。

日本の文化を支えてきたとボクは思う……。下「」引用。
「ヒノキは昔から日本の木の文化を支え、その形成に大いに貢献してきた。「日本書記」の中に、「スギとクスノキは船に、ヒノキは宮殿に、マキ(槇)は棺にせよ」とあるのは、よく知られている。日本書紀に記されているということは数千年も前、相当古い時代からヒノキが宮殿建築用として使われて、最適最高の材であることが証明されていたことになる。」
どうして、「ひのき」という名がついたか? 下「」引用。
「「ひのき」という和名は「火の木」の意味で、古代にこの木を使って火をおこしたことによるとされている。「ヒ」には「良い」という意味があるため、ヒの木と呼ばれたという説もある。」
「日本の木の王様 木曽檜」下「」引用。
「長野県上松町にある赤沢自然休養林(通称「赤沢美林」)は、木曽林業を代表する古い歴史を持つとともに、森林浴の地としても知られている。-略-」
大正5年、上松駅→赤沢にむかう小川森林鉄道が開設。
現在、かつての小川線の一部を観光用に復活。
裏木曽(神宮備林 350年前の天然更新)
--世界遺産に値するこの森林。
世界に誇る法隆寺の五重の塔……。下「」引用。
「法隆寺の昭和の大修理したときに、取り替えた材は35%だけで、残りの65%は千三百年前そのままの木を使っていると聞いています。もし、法隆寺がケヤキやマツを使ってあったら、だいたい六百年くらいしかもたないでしょう。スギで千年から八百年くらい。ヒノキだから千三百年以上も塔を支えているんだと思いますね。」
かしこまった舞台……。下「」引用。
「スギは少し暖かいが、ヒノキは冷たい。スギが作業場など冷えては困るところに使われたのに対して、ヒノキはピリッと身を引き締めるようなかしこまったところに使われてきた。「ヒノキ舞台」という言葉もあるのも納得できよう。」
遺跡から……。下「」引用。
「遺跡から出土する木材の樹種を全国的に調べてみると、ヒノキの木材はスギの丸木舟が出土したことで知られる福井県三方郡三方町の鳥浜貝塚遺跡が最も古いようである。ここでは縄文時代の草創期から前期にかけて地層から出土した自然木(昔の人々が利用した痕跡のない木材)約32000点のうち20点がヒノキであった。-略-この遺跡から人々がさまざまに良した木材も出土している。最も古いものは約1万年前の杭でわずか2点であるが、約6千年前の縄文時代前期になるとたくさんの杭、板材、そして図に示したスプーン状の木器、また彫刻のある細長い板などがあり、生活に密着したヒノキ材の利用を既に見てとれる。」
校舎「贄川(にえかわ)小学校【長野県・贄川村】
「まちづくりの核として日本一の総檜づくり校舎の保存 旧甲良東小学校【滋賀県・甲良町】」
「中国南部トン族の集落に見る木の文化ルーツ」
「へぎ目の美しさを生かす」木曽福島 曲物師・村地忠太郎
「国産ヒノキにもあった! ヒノキチオール」
 もくじ
もくじ