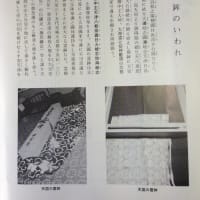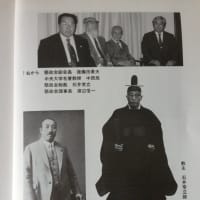・第五識 (眼識・耳識・鼻識・舌識・身識 =五感のこと)
・第六識 (意識)
・第七識 (末那識 まなしき)
・第八識 (阿頼耶識 あらやしき)
◎末那識を説く理由
我執の意識として殊更に末那識の如きものを説くのは、仏教という立場に立つからである。
一般的な立場からいえば、第六意識までで心理学的には説明がつくし、もし記憶の相続という問題の解決には六識では十分に説明がつかないなら、せいぜいその根本的なものとして根本識を考えれば説明はつく。さらに今日のように潜在意識というような考え方でもよいであろう。
ところが、仏教は人間界の苦悩を自我を執じ、他を差別する分別にあるとみる。自他の区別があることが苦の原因ではない。自他の区別に執着して、区別されたものを差別視するところに苦の原因があるというべきである。
無常であること自体は世間の実相である。したがって、世の中の無常であることが苦の原因であるといってみたところで、それを苦にしなければ別にどうでもない。一切は無常であって別に問題はない。ただ人間は常に変化してゆく存在に対して、なんらかの固定観念をつくりあげ、その固定観念にとらわれるから無常を苦にせざるを得ないのである。
金持ちだ貧乏だといっても、金そのものが悪いのでもなんでもない。貧乏が苦しいというのは、その金にとらわれるからである。金持ちが貧乏したとき、もと貧乏であったこと、本来無一物であることが十分に了解されていれば、たいして貧乏は苦にならないはずである。しかし、失ったものに対して、それを所有していた時の執着でとらまえるから、貧乏が苦しいのである。
苦こそは人間のとらわれから起こるというのが仏教の立場である。
無我である現実の中で、自らに実我のとらわれをもつから、そこに孤独の苦が起こるのであり、本来無我と了達するならば、そこには苦悩はなく、すべてが自由自在である筈である。
しかし、人間は自らを実我と考えなければ――たとえ、とらわれであるとしっていても――生きてゆけない。人間存在そのものは苦であると説かれるのは、このためである。仏教は、このような我執を退治して、真実の自由を生きることを目標とするのである。したがって、仏教にとって、なぜ、このような我執があるのか。また、我執はどのような構造の中にあるのかを明らかにすることは大切な問題である。
いま、この我執の構造を明らかにして、末那識が説かれ、我執は、意識が根本識たる阿頼耶識によって、しかも、この阿頼耶識の見分を実我であると誤認するところから起こるといい、その誤りを犯すものが末那識であると説明する。このように末那識は阿頼耶識に依止し、しかも阿頼耶識の見分を所縁とするものであるから、その働きは非常に微細である。
阿頼耶識は法界共通の意識・記憶とでも言えばいいと思う。 この阿頼耶識の元品の無明と言うたった一つの迷いと言うか動揺から法界の一切の存在が始まっている。 そしてその迷いが煩悩(業)を生み、その煩悩が体となって我々のように個我が出来る。 阿頼耶識全体からみれば海全体に対する水滴のような物である。 そして個々の末那識は阿頼耶識を常に観ているが、阿頼耶識内の自分の境界の「部分」の煩悩を「恒久的に存在する自分の正体=霊魂」だと誤解する。 これが自我のメカニズムである。
そして末那識(七識)以下に意識(六識)、前五識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識)がある。
ちなみに阿頼耶識(八識)は表裏一体で煩悩で汚染されている側(=染分・元品の無明)と無垢で清浄な側があり、清浄な側(=浄分・元品の法性)は阿摩羅識(九識)ともいう。
又、末那識は二乗界、阿頼耶識は菩薩界とされている。 大乗仏教以外の宗教で説く、瞑想による覚りというのは普通この末那識レベルの事である。 これを指して大乗仏教では二乗界は成仏できないという。 まだ無我のレベルではないからである。 阿頼耶識レベルになると法界の一切衆生全てで共有なので小乗(二乗)の行ではなく菩薩行が必要だと言うわけである。
阿頼耶識の無数の煩悩が消えると元品の無明と言う一番最初の迷いだけが残る。 少しだけ全宇宙のプラス・マイナスのエネルギーが相殺して0になるがどうしても余韻だけが揺らぎとして残りその揺らぎから宇宙の素が出来たと言うビッグバン理論の一種に似ている。 阿頼耶識の無明と言う小さな動揺から万物が始まったのである。