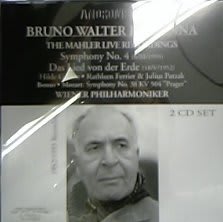○ホーレンシュタイン指揮ボーンマス交響楽団(BBC)1969/1/10・CD
ガシガシと音は強いが遅めインテンポでフォルムの崩れないやり方は最初は抵抗あるだろう。だが内声部までぎっちり整えられた音響の迫力、またテンポ以外で魅せる細かなアーティキュレーション付け、デュナーミク変化にホーレンシュタインの本質が既に顔を出している。ブルックナー的な捉え方をしているなあと提示部繰り返しを聴きながら思うのだが、コーダの盛り上がりはそうとうなもの。続いてスケルツォでは切っ先鋭い発音が絶妙なリズム表現を産み出し出色である。アンダンテ楽章も意外にロマンティック。しかしやっぱりこの演奏は長大な4楽章に尽きる。独特の設計を施された英雄譚はこれはこれで成立している。ホーレンシュタインの表現も幅が出てきて、法悦的なテンポの緩徐部などそれまでのこの指揮者の表現からは逸脱している。威厳ある演奏ぶりはオケがやや残念な部分もあるものの十分堪能できます。モノラルなのが残念。
ガシガシと音は強いが遅めインテンポでフォルムの崩れないやり方は最初は抵抗あるだろう。だが内声部までぎっちり整えられた音響の迫力、またテンポ以外で魅せる細かなアーティキュレーション付け、デュナーミク変化にホーレンシュタインの本質が既に顔を出している。ブルックナー的な捉え方をしているなあと提示部繰り返しを聴きながら思うのだが、コーダの盛り上がりはそうとうなもの。続いてスケルツォでは切っ先鋭い発音が絶妙なリズム表現を産み出し出色である。アンダンテ楽章も意外にロマンティック。しかしやっぱりこの演奏は長大な4楽章に尽きる。独特の設計を施された英雄譚はこれはこれで成立している。ホーレンシュタインの表現も幅が出てきて、法悦的なテンポの緩徐部などそれまでのこの指揮者の表現からは逸脱している。威厳ある演奏ぶりはオケがやや残念な部分もあるものの十分堪能できます。モノラルなのが残念。