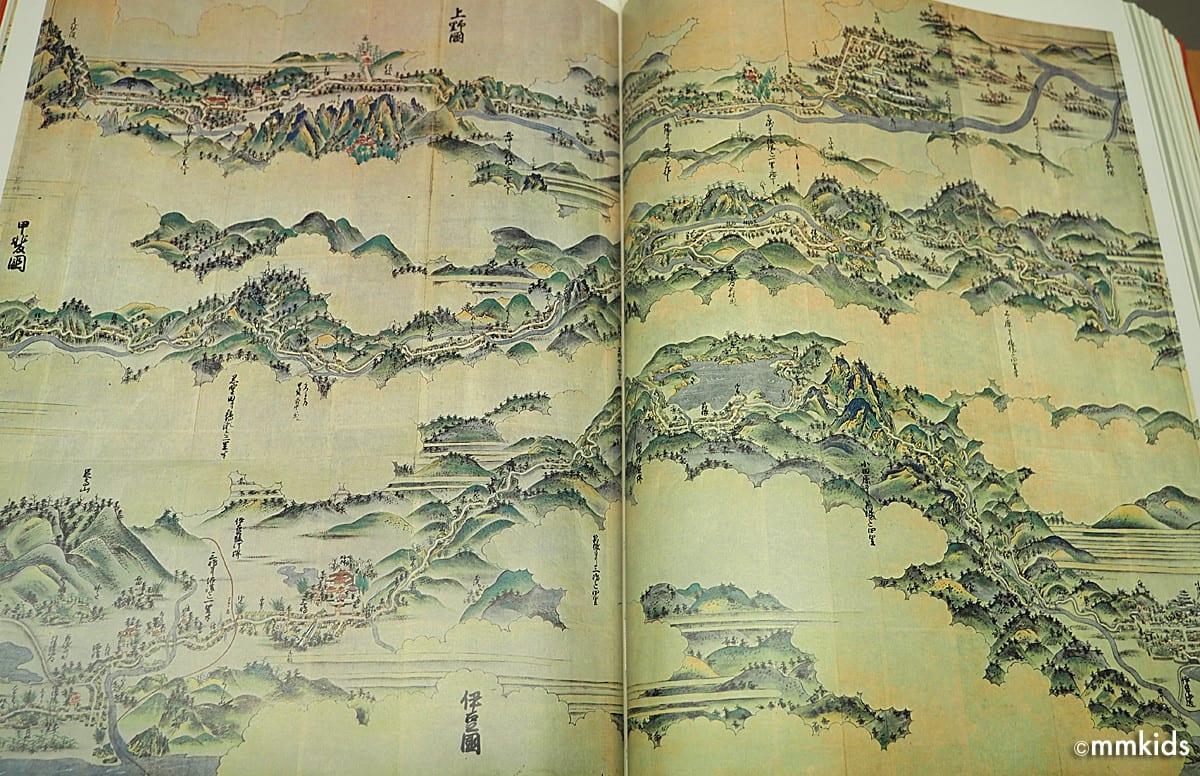来月、松代夢空間主催の「妻女山 紅葉と歴史のハイキング」が行われます。そのガイドをするのでコースのチェックと所要時間をつかむために天城山(てしろやま)へ登りました。

陣場平から登って天城山登山道との分岐手前から松代方面。里山はまだまだ緑色です。右奥の高い山々は、焼額山とか岩菅山などの奥志賀高原方面です。奥志賀から秋山郷へ抜ける405号沿いは紅葉の見頃でしょう。
●錦秋の奥志賀から秋山郷で紅葉に酔い滝三昧、そして蕎麦三昧の始まり(妻女山里山通信):かなりの秘境なので気軽には行けませんが、心に沁みる素晴らしい紅葉が見られます。

登山道は帰路に下りてきます。まず林道を芝山方面へ歩きます。かなりの草薮ですが、歩くのに問題はありません。

樹間から見える篠ノ井方面。手前の尾根は、斎場山から土口将軍塚へ続く長尾根です。

帰化植物のマルバフジバカマ。吸蜜していたアサギマダラは、南へ飛び去りました。

林道を完全に塞ぐクヌギの倒木。今回はこれの除去のために来ました。

15分ほどかけて倒木を処理。なんとか人が安全に通れるようになりました。

天城山と芝山のあいだにある鞍部。直登します。かなりの急斜面ですが、落ち葉が深いので登りにくくはありません。尾根に登ると登山道に出ます。

南面に色づいているのは欅(ケヤキ)。この先の芝山の岩稜地帯を越えていくと、雨宮方面へ下れます。

天城山方面へ。左を直登すると、5分ぐらいで天城山山頂です。坂山古墳があります。ハイキング当日はここを登りますが、今回は久しぶりに右の倉科将軍塚古墳方面への道をたどりました。

ところが倒木が何本も。これは下を巻きました。赤松の倒木で登山道が崩れて無いところもありました。

この倒木は下をくぐり抜けました。この登山道は使えません。危険です。

倉科尾根へ。ジコボウ(ハナイグチ)がたくさん出ていました。もう充分に採ったのでいらないのですが、きのこ屋の性で、キノコがあるとつい採ってしまいます。小さなものと虫が入っていないものだけを採りました。

フウセンタケの仲間だと思うのですが。マンジュウガサ?毒キノコではなさそうです。同定できていません。

二本松峠(坂山峠)から鞍骨山(鞍骨城跡)方面。右が倉科方面で倉科坂となっていますが、間違っています。倉科方面が清野坂、清野方面が倉科坂なのです。清野側の妻女山から象山へ行く林道が「林道倉科坂線」と国土地理院の地図にもある様に。清野側が倉科坂なのです。清野の人が山を超えて倉科へ行ったから清野側が倉科坂なのです。これを設置したのは倉科の方たちでしょう。完全に間違っています。これを作った倉科のMさんは知っていて以前入れ替えられたことを怒っていました。

これも昔、Mさんが作った標識なんですが腐ってしまいました。防腐剤を塗布しておかないと持ちません。それと石油溶剤を使った塗料は熊に壊されるので使ってはいけません。

クリタケを発見。6株ぐらい採れました。

赤松の間から松代方面の眺め。

陣場平へ。今年は三回も草刈りをしたので清々しています。バイモの球根をたくさん移植したので、来年4月が楽しみです。

その陣場平にシロシメジがたくさんありました。別名をヌノビキ(布引)といい、白い布を敷いた様に生えるのですが、妻女山山系では幻のキノコです。こんなに大量に群生しているのは初めて見ました。

遅い昼は、堂平大塚古墳のあるログハウスを借りて。ここも案内します。左側の紅葉は、まだ全く紅葉していません。ハイキングの時は色づいているといいのですが。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

陣場平から登って天城山登山道との分岐手前から松代方面。里山はまだまだ緑色です。右奥の高い山々は、焼額山とか岩菅山などの奥志賀高原方面です。奥志賀から秋山郷へ抜ける405号沿いは紅葉の見頃でしょう。
●錦秋の奥志賀から秋山郷で紅葉に酔い滝三昧、そして蕎麦三昧の始まり(妻女山里山通信):かなりの秘境なので気軽には行けませんが、心に沁みる素晴らしい紅葉が見られます。

登山道は帰路に下りてきます。まず林道を芝山方面へ歩きます。かなりの草薮ですが、歩くのに問題はありません。

樹間から見える篠ノ井方面。手前の尾根は、斎場山から土口将軍塚へ続く長尾根です。

帰化植物のマルバフジバカマ。吸蜜していたアサギマダラは、南へ飛び去りました。

林道を完全に塞ぐクヌギの倒木。今回はこれの除去のために来ました。

15分ほどかけて倒木を処理。なんとか人が安全に通れるようになりました。

天城山と芝山のあいだにある鞍部。直登します。かなりの急斜面ですが、落ち葉が深いので登りにくくはありません。尾根に登ると登山道に出ます。

南面に色づいているのは欅(ケヤキ)。この先の芝山の岩稜地帯を越えていくと、雨宮方面へ下れます。

天城山方面へ。左を直登すると、5分ぐらいで天城山山頂です。坂山古墳があります。ハイキング当日はここを登りますが、今回は久しぶりに右の倉科将軍塚古墳方面への道をたどりました。

ところが倒木が何本も。これは下を巻きました。赤松の倒木で登山道が崩れて無いところもありました。

この倒木は下をくぐり抜けました。この登山道は使えません。危険です。

倉科尾根へ。ジコボウ(ハナイグチ)がたくさん出ていました。もう充分に採ったのでいらないのですが、きのこ屋の性で、キノコがあるとつい採ってしまいます。小さなものと虫が入っていないものだけを採りました。

フウセンタケの仲間だと思うのですが。マンジュウガサ?毒キノコではなさそうです。同定できていません。

二本松峠(坂山峠)から鞍骨山(鞍骨城跡)方面。右が倉科方面で倉科坂となっていますが、間違っています。倉科方面が清野坂、清野方面が倉科坂なのです。清野側の妻女山から象山へ行く林道が「林道倉科坂線」と国土地理院の地図にもある様に。清野側が倉科坂なのです。清野の人が山を超えて倉科へ行ったから清野側が倉科坂なのです。これを設置したのは倉科の方たちでしょう。完全に間違っています。これを作った倉科のMさんは知っていて以前入れ替えられたことを怒っていました。

これも昔、Mさんが作った標識なんですが腐ってしまいました。防腐剤を塗布しておかないと持ちません。それと石油溶剤を使った塗料は熊に壊されるので使ってはいけません。

クリタケを発見。6株ぐらい採れました。

赤松の間から松代方面の眺め。

陣場平へ。今年は三回も草刈りをしたので清々しています。バイモの球根をたくさん移植したので、来年4月が楽しみです。

その陣場平にシロシメジがたくさんありました。別名をヌノビキ(布引)といい、白い布を敷いた様に生えるのですが、妻女山山系では幻のキノコです。こんなに大量に群生しているのは初めて見ました。

遅い昼は、堂平大塚古墳のあるログハウスを借りて。ここも案内します。左側の紅葉は、まだ全く紅葉していません。ハイキングの時は色づいているといいのですが。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。