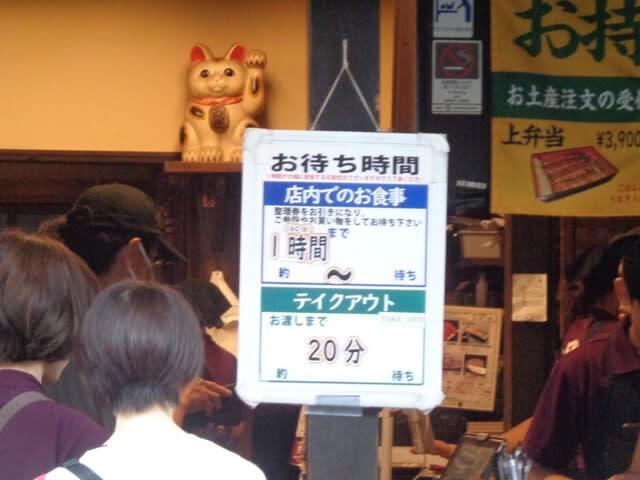虎ノ門近辺巡り、
3か所目は愛宕神社(あたごじんじゃ)です。

それにしても、この防水桶の標識は何とかならないものか。

愛宕神社は、標高25.7メートルの愛宕山の山頂にあります。

愛宕山は、23区内で一番高い山。
それより高い新宿区の箱根山(44.6メートル)は人工の山ですので、
自然の地形としては一番高い山ということになります。
江戸時代には、見晴らしの名所として、見物客で賑わいました。
今は高層ビルが林立して見えませんが、
当時は、山頂から東京湾や房総半島までを
見渡すことができたと言われています。
幕末に、
勝海舟と西郷隆盛が
愛宕山で会談し、
二人が江戸の街を見下ろして、
「戦火で消失させてしまうのは忍びない」と、
江戸城無血開城につなげたという逸話があります。
なお、愛宕山という地名は全国各地にあります。
ちなみに、落語の「愛宕山」の舞台は、京都。

入り口にある大鳥居。

愛宕神社に登る石段は二つあり、
こちらは男坂86段。

こちらは傾斜がゆるやかな、女坂108段。

他に、車で行くことができる道と
エレベーターもあります。
こんな注意書きも。

男坂は神社創建時の姿が保たれ、
上り始めたら休むことが許されません。
約40度もの急勾配には、
踊り場がないため、
途中で足を止めて見上げると
上体を大きくそらす体勢になって、
転げ落ちそうな感覚に襲われるのです。

別名、「出世の石段」と呼ばれるのは、
次のような故事によります。

1634年2月25日(寛永11年1月28日)、
徳川幕府3代将軍家光が
増上寺への参拝の帰路に、
愛宕山から梅の香りがするのに気づきました。
(山上に梅が咲いているのを見て、という説もある。)
「誰か馬で石段を上り、梅を取ってくる者はいないか」
と命じたところ、
並みいる家来たちが尻込みする中、
四国丸亀藩士、曲垣(まがき)平九郎が
愛馬とともに階段を上り、
梅を取って再び階段を下り、
梅を献上して、
馬術の名人として全国にその名を轟かせた、
という講談譚。

この故事にちなみ、
この階段を「出世の石段」と呼んで、
急な石段を登ると出世するという言い伝えがあり、
多くのビジネスマンが
この石段を登って神社にお参りに見えています。

しかし、実際の石段を見て、
ここを馬の蹄で登るのは至難のわざ、
後世の作り話だろうと思いましたが、
調べると、明治から昭和にかけて
3度の成功例があるといいます。
1例目は仙台藩で馬術指南役を務め、
廃藩後曲馬師をしていた石川清馬(せいま)。
師の四戸三平が挑み、果たせなかった
出世の石段登頂を1882年(明治15年)に成功させ、
これにより石川家は徳川慶喜より葵の紋の使用を許されました。
2例目は参謀本部馬丁の岩木利夫。
1925年(大正14年)11月8日、
愛馬平形の引退記念として挑戦し、
観衆が見守る中成功させました。
この模様は山頂の東京放送局によって中継され、
(日本初の生中継とされる)
昭和天皇の耳にも入り、
平形は陸軍騎兵学校の将校用乗馬として
使われ続けることとなりました。
この時、上りは1分ほどで駆け上がりましたが、
下りは45分を要したといいます。
上りより下りの方が恐怖感は大きいと思われますので、
馬が何度も立ち止まったのではないでしょうか。
3例目は馬術のスタントマン、渡辺隆馬。
1982年(昭和57年)、
日本テレビの特別番組「史実に挑戦」において、
安全網や命綱、保護帽などの安全策を施した上で
32秒で登頂しました。
という成功例は伝わっているものの、
失敗例はそれより多いはず。
どんな悲惨な結果になったのでしょうか。
長い石段を上がると、
一の鳥居が迎えます。

境内には都会とは思えぬほど多くの木々が茂り、
四季折々の花々が咲き乱れます。

山の証しである三角点があります。
丹塗りの門「神門」。

江戸幕府ゆかりの印として、
葵の御紋が飾られています。
社殿。

主祭神「火産霊命(ほむすびのみこと)」を祀ります。
火産霊命は別名「火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)」と言い、
「伊邪那美命(いざなみのみこと)」から最後に産まれた炎の神。
しかし炎の神ゆえに、
伊邪那美命に大やけどを負わせ、
これが原因で伊邪那美命は亡くなってしまいました。
怒った夫の「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)」は、
自らの手で火産霊神の首を切り落とします。
しかしその血や体からは、
岩石の神、火の神、雷神、雨の神、水の神、
多くの山々の神々などが生まれました。
ご神徳は、鍛冶・土器・消防・防災などですが、
火はすべてを浄化して帳消しにすることから、
「祓いの神」としても信仰されています。

御社殿の中に入れる人は特別な人たちだけです。
奥には「本殿」がありますが、ふだん開かれることはありません。
手水舎

ここで手を口とを清めます。
手は行為の象徴。人のふるまいを清めます。
口はことばの象徴。人のことばを清めます。
招き石

この石を撫でると福が身に付くといわれており、
たくさんの人に撫でられたせいか、ツルツルになっています。
これは、山の印、三角点。

将軍梅。

曲垣平九郎が手折った梅といわれています。
池には、鯉たちが泳いでいます。

3つの末社。

左から太郎坊社、

福寿稲荷社、

大黒天社。

その他、境内にはいろいろなものがあります。




ところで、山と丘の違いですが、
国土地理院では,山の定義はしていません。
しかし、辞典等によりますと、
「山というのは、周りに比べて地面が盛り上がって高くなっているところ」
と言われています。(笑)
それでは丘と同じで、
山と丘の区別は明確ではありません。
国際連合環境計画においては、
高度が少なくとも2500メートル以上あるところ、
イギリスでは標高600メートル以上の高地などと決められています。
ブリタニカ百科事典では、
相対的に2,000 フィート(610メートル)の高さを持つものを山としています。
UIAA(国際的な山岳とクライミングの団体)の定める山の定義では、
標高が700メートル以上あり、
山頂に向かって急峻な傾斜を持つ陸地とされ、
標高が700メートル未満でも、
山脈の一部として形成されている場合、山に分類されます。
比較的日本の基準は甘く、
山と呼んでも、そうでないものが沢山あます。
日本で最も低い山は
大阪にある天保山(4.53メートル)でしたが、

今は仙台の日和山(3メートル)です。

日和山は元は標高が6メートルありましたが、
東日本大震災で削られて3メートルになったことで、
天保山より低くなってしまいました。
ただ、日和山も天保山も自然の山ではなく筑山(人工の山)ですので、
自然の山で1番低いのは徳島の弁天山(6.1メートル)です。

日和山に1位を譲った大阪の天保山ですが、
「三角点のある日本一低い山」としてなら、
日本一を維持しています。
三角点は正確な位置を求める測量をおこなうために、
国土地理院が作った位置の基準となる点のことで、
仙台の日和山には三角点がありません。
このため「正確な位置を測量している」山としては、
天保山が1番低いというわけです。
東京23区には標高50メートル以下の「山」が沢山あります。
青山、代官山、権現山
城南五山(島津山、池田山、御殿山、八ツ山、花房山)
千石山、飛鳥山などですが、
上野恩賜公園も「上野の山」と呼ばれています。
ただし、国土地理院の地形図に記載されている山は愛宕山だけ。
国土地理院の2万5千分の1地形図に
山の名前が記載されていることが、
一般的に山であるかどうかの識別に使われています。
このため、正式に
愛宕山が東京23区で最も高くて、
その上、最も低い山ということになります。