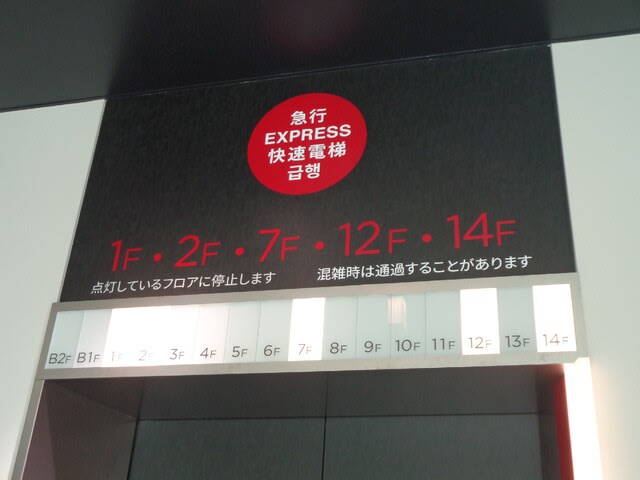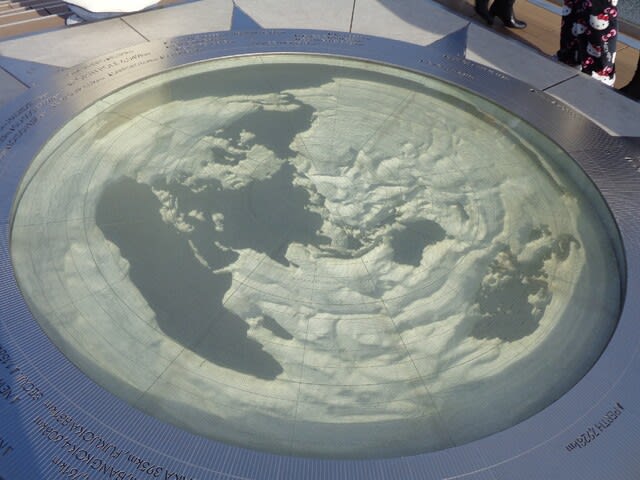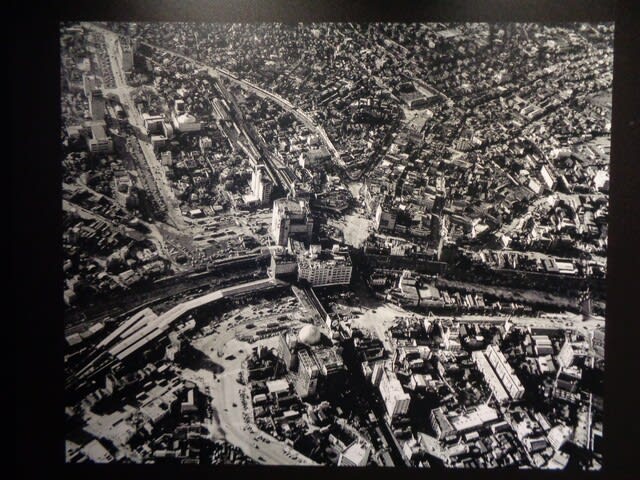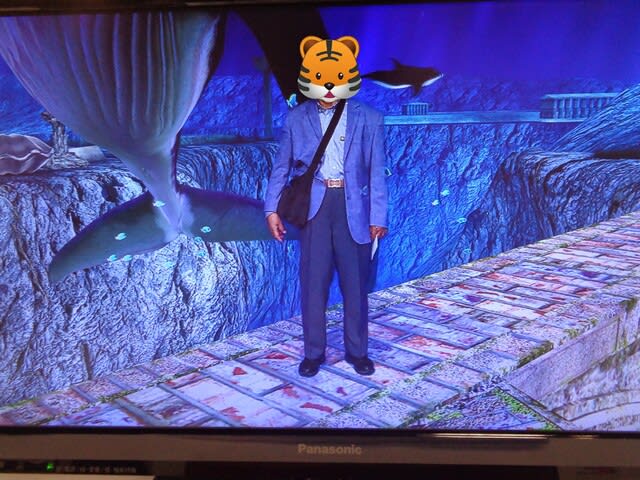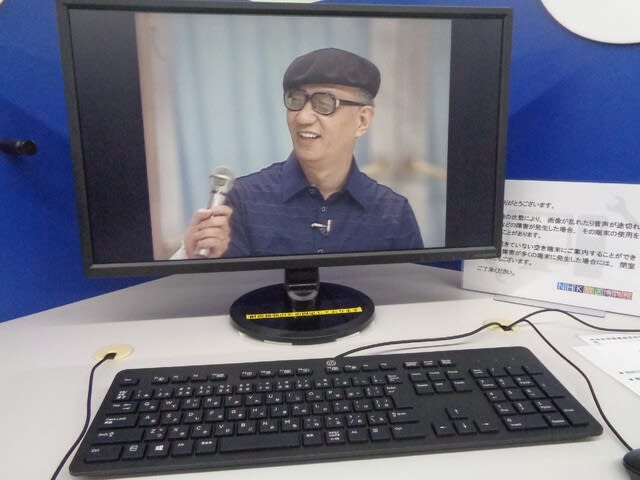つい先日、ここ↓へ。

というのは、「名所めぐり」をしていて、
ふと気づいた。
お寺の頂点・浅草寺も、
神社の頂点・明治神宮も、
何度も行っているのに、ちゃんと見ていない。
毎年正月2日には訪れるなど、
浅草寺には、十回を下らないほど行っていますが、
いつも雷門から入って仲見世を通り、
宝蔵門をくぐり、本堂を見て、
西に向かい、はなやしき方面から六区に抜ける、
というのが定番コース。
境内内にある様々なお堂は何があるかも知らない。
それでは申し訳ないので、
改めて、細部を見てみようと思った次第。
↓のマップにあるように、

境内は広く、沢山の見どころがあります。
改めて浅草寺を紹介すると、
都内最古の寺で、
正式には金龍山浅草寺(きんりゅうざん せんそうじ)と号します。
聖観世音菩薩を本尊とすることから、
浅草観音とも言われます。
元は天台宗に属していましたが、
昭和25年(1950)に独立して
聖観音宗の本山となりました。
「浅草寺縁起」等の伝承によると、
浅草寺の創建の由来は以下の通り。
飛鳥時代の推古天皇36年(628) 、
宮戸川(現・隅田川)で漁をしていた
檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟の網に
一つの仏像がかかる。

これが浅草寺本尊の聖観音(しょうかんのん)像。

この像を拝した兄弟の主人・土師中知(はじのなかとも)は出家し、
自宅を寺に改めて供養。
これが浅草寺の始まり。
その後大化元年(645年)、
勝海という僧が寺を整備し
観音の夢告により本尊を秘仏と定めた。
観音像は高さ1寸8分(約5.5cm)の金色の像と伝わるが、
公開されることのない秘仏のためその実体は明らかでない。
一説に、本尊の聖観音像は、
飯能市岩淵にある成木川沿いにある岩井堂に安置されていた観音像が
大水で流されたものとする伝承がある。
浅草寺創建より100年程前、
岩井堂観音に安置されていた観音像が
大雨によって堂ごと成木川に流され、
行方不明になったという。
成木川は入間川、荒川を経て隅田川に流れており、
下流にて尊像発見の報を聞いた郷の人々が
返還を求めたが叶わなかったという。
天慶5年(642) 、
安房守平公雅が武蔵守に任ぜられた際に
七堂伽藍を整備し、
雷門、仁王門(現・宝蔵門)などはこの時の創建といわれる。
それでは、浅草のシンボル・雷門から入りましょう。

表参道入口の門。
切妻造の八脚門で
向かって右の間に風神像、
左の間に雷神像を安置することから
正式には「風雷神門」というが
「雷門」の通称で通っている。

その創建年代は詳らかではないが、
平公雅が天慶5年(642) に堂塔伽藍を一新した際、
総門を駒形に建立したと伝わる。
慶応元年(1865)に焼失後は
仮設の門が時折建てられていたが、
昭和35年(1960)に、常設の門が鉄筋コンクリート造で再建された。
実業家・松下幸之助が浅草観音に祈願して病気平癒した報恩のために
寄進したもの。
門内には松下電器産業(現パナソニック)寄贈の大提灯がある。
大提灯には表面に「雷門」、

裏手に「風雷神門」と書かれている。

宝蔵門にかかる大提灯とともに、
三社祭の時(神輿通過のため)と
台風接近など自然災害に備える必要がある場合には
提灯が畳まれる。
仲見世通り

雷門から宝蔵門に至る長さ約250mの表参道の両側には
土産物、菓子などを売る商店が立ち並んでいる。
商店は東側に54店、西側に35店を数える。
日本で最も古い商店街のひとつ。
寺院建築風の外観を持つ店舗は、
関東大震災による被災後、
大正14年(1925)に
鉄筋コンクリート造で再建されたもの。
私が行った日、インバウンドの人々が一杯で、
さながら外国のよう。
やはり東京観光の目玉として、
日本情緒が味わえる場所として人気があるようだ。
貸衣装の着物姿の外国人の姿も多い。
宝蔵門

入母屋造の二重門。
江戸時代には一年に数度二階部分に昇ることが可能であった。
昭和20年(1945)、仁王門は東京大空襲により
観音堂・五重塔・経蔵などとともに焼失。
現在の門は昭和39年(1964)に再建された
鉄筋コンクリート造で、
実業家・大谷米太郎(ホテルニューオータニ創業者)夫妻
の寄進によって建てられたもの。
門の左右に金剛力士(仁王)像を安置することから
かつては「仁王門」と呼ばれていたが、
昭和の再建後は宝蔵門と称している。
その名の通り、
門の上層は文化財「元版一切経」の収蔵庫となっている。

門の背面左右には、
魔除けの意味をもつ巨大なわらじが吊り下げられている。
これは、金剛力士像のうち、向かって右の像の作者・村岡久作が
山形県村山市出身である縁から、
同市の奉賛会により製作奉納されているもので、
わら2500kgを使用している。
わらじは10年おきに新品が奉納されている。

宝蔵門には「小舟町」と書かれた大提灯が架かっている。
1659年に日本橋小舟町の信徒から寄進されたのが最初で、
日本橋小舟町奉賛会によって奉納が続けられており
ほぼ10年ごとに新調されている。
お水舎

煙を浴びると、健康になるという。

本堂

本尊の聖観音像を安置するため観音堂とも呼ばれる。
旧堂は慶安2年(1649)の再建で
近世の大型寺院本堂の代表作として国宝に指定されていたが、
昭和20年(1945)の東京大空襲で焼失した。
現在の堂は昭和33年(1958)に再建されたもので
鉄筋コンクリート造。(木製じゃないんだ!)

本堂へ上がる階段の上部にせり出した向拝には、
直径4.5mの大提灯が掛かる。

堂内は内陣(ないじん)と外陣(げじん)に分けられており、

外陣に入ると、正面上に雄渾な筆致で
「施無畏(せむい)」と書かれた扁額が掛かっている。

靴を脱いで畳敷の内陣に上がると、
その中央にはご本尊を奉安する御宮殿(ごくうでん)があり、
その内部にお厨子が安置されている。


御宮殿は堂内のお堂というべきで、最も神聖な空間を結界している。
東側。

西側から。


本堂の東側に、いろいろなものがあります。
平和地蔵尊

二尊仏

露座であることから、「濡れ仏」の名で知られ、
向かって右が観音菩薩、左が勢至菩薩像。
台座を含めた高さは約4.5m。
久米平内堂

ここに祀られる久米平内(くめのへいない)は、
講談等に登場する人物で、
剣の道に優れ、多くの人の命を奪ったので
(首切り役人だったともいう)、
その罪滅ぼしのために、
自らの像を仁王門の近くに埋めて多くの人に踏みつけさせたという。
「踏みつけ」が「文付け」(恋文)に通じることから、
縁結びの神とみなされるに至った。
弁天山

弁財天を祀る弁天堂が建つことから弁天山と呼ばれる。
石段上に朱塗りの弁天堂、
その右手に鐘楼が建つ。
 この鐘楼に架かる梵鐘は
この鐘楼に架かる梵鐘は
江戸時代の人々に時を知らせた「時の鐘」の一つ。
戦時中、多くの寺の鐘が供出を余儀なくされた中で、
弁天山の「時の鐘」は特に由緒がある鐘ということで残された。
現在も毎朝6時に役僧によって撞かれており、
大晦日には新年を告げる「除夜の鐘」が鳴らされる。
弁天堂への石段の左側には芭蕉の
「観音の甍(いらか)見やりつ花の雲」の句碑がある。

旧五重塔跡

現在、五重塔は境内の西側に建立されているが、
かつてはその反対側に位置していた。
五重塔が元の三重塔の跡伝承地付近に場所を移して、
再建される前に五重塔があった跡地。
戦災公孫樹

樹齢八百余年ともいわれ、
源頼朝公(1147~99)が浅草寺参拝の折、
挿した箸から発芽したと伝えられる。
東京大空襲をくぐり抜けた神木として、
今も多くの人々に慕われている。
二天門

本堂の東側に東向きに建つ、切妻造の八脚門。
元和4年(1618)の建築で、
第二次世界大戦にも焼け残った貴重な建造物。
浅草寺境内にあった東照宮(徳川家康を祀る神社)への門として
建てられたもの。
(東照宮は寛永19年(1642)に焼失後、再建されていない)。
現在、門の左右に安置する二天(持国天、増長天)は
上野の寛永寺墓地にある厳有院(徳川家綱)霊廟から移されたもの。
門に向かって右が持国天、左が増長天。

二天門は境内に残る江戸時代初期の古建築として貴重であり、
国の重要文化財に指定されている。
平成22年(2010)に改修を終え、創建当初の鮮やかな姿によみがえった。
二天門から入った景色。

着物の親子三代。

浅草神社

本堂の東側にある。
拝殿、幣殿、本殿は重要文化財。

浅草寺の創建に関わった3人を
祭神として祀る神社。
明治の神仏分離以降は浅草寺とは別法人になっている。
「こちら葛飾区亀有公園前派出所」記念碑

浅草神社鳥居脇にある。
平成17年(2005年)に
秋本治の漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の
単行本の発行部数が1億3千万部を突破したことを記念するため建立された。
同作品の主人公である「両さん」こと警察官両津勘吉は
浅草育ちという設定になっており、
両津の少年時代のエピソードを題材にした「浅草物語」の巻に
浅草神社が登場した縁により建立されたもの。
今日は、ここまで。
次回は本堂の西方面の数々を。