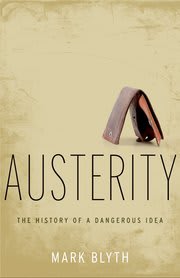最近読んだ論文に引用されていて気になったので、Alasdair Roberts, The Logic of Discipline: Global Capitalism and the Architecture of Government (Oxford University Press, 2010)を読んでみました。

ちなみに、著者は「Suffolk University Law School」の教授とのことで、勝手に親近感が湧いていたのですが、ここでいうSuffolkはイギリスの州の一つ(素晴らしい教会がたくさんあります!)ではなくて、アメリカのBoston市がある群の名前のようです。
イギリスとアメリカで同じ地名があることはすごくよくあるので注意しないといけません。(せめてNewをつけるとかして違う地名にしてくれればよかったのに。)
さて、本書は1978~1980年以降の時代を「the era of liberalization」(自由化の時代)と呼び、この時代に共通する諸改革の精神を「the logic of discipline」(規律の論理(?))と名付け、それが様々な政策にどのように表れていたのか、そしてその妥当性が否定されていった(著者はそう主張します――p.14)プロセスを論じていきます。
ちなみに、なぜ1978年~1980年かというと、この時期に中国で改革・開放政策が始まったこと、サッチャー政権とレーガン政権の成立及び彼らの下で市場化政策が行われたことが理由として挙げられています。
著者によれば、logic of disciplineは以下の2つの要素から成り立っています(pp.4-6)。
(1)民主的プロセスを通した統治への深い懐疑
(2)それを是正するために、政治家と選挙民の行動を制約して、間違った決定を下せないようにする。その手段として、法律や条約、契約が頻繁に用いられる。
(1)の民主主義への懐疑の原因として、経済学における公共選択理論(政治家は自分の利益を最大化するように行動する)の発展だけでなく、Huntington, Crozier and Watanuki (1975)が提起した「overload thesis」(人々の政治参加が進み、人々は政治に多くの事を要求するようになったが、その要求は政府の応答能力を凌駕してしまった)も挙げられています(pp.9-10)。
ここまではよくある話なのですが、僕が特に勉強になったのは、(2)の手法をnaive institutionalism(ナイーブな制度主義)と呼んで批判するところ。
著者によればナイーブな制度主義の特徴は、ある国の制度を別の国に導入することで所期の目的を達成できると考えているところにあります(pp.15-17)。
Douglass NorthやPaul PiersonやPeter Hallなどの「新制度論者」は制度の重要性を主張して学界に大きな影響を与えたけど、彼らは制度として公式な(formal)ものだけでなく、文化や習慣などの非公式な(informal)ものも含めた。
formalな制度は簡単に変えやすいけれど、informalな制度はなかなかすぐには変わらない。
新制度論者が指摘していたこの点は、しかしナイーブな制度論者によって忘却されます。
そもそも制度のナイーブな見方は、第二次世界大戦後すぐの政治学者によって否定されていたものだったそうです。
しかし、制度改革をしたい人たちは時間や資源に制約を抱えているためにinformalな制度のことまで考えていられないことや、改革の成果を測定するためにはformalな制度の変化を見るのが分かりやすいから、彼らはformalな制度の変更ばかりを目指すようになってしまった。
でも、たとえば、法文上で素晴らしいことを意図していたとしても、それを適用する段階で政治、行政、社会経済の様々な主体の地からによってその意図は容易に歪められてしまう(1970年代のGreat Societyがあまり大きな変化を起こせなかった理由を著者はこの点に帰しています)。
著者はある論者の次の言葉を引用しています。
「政策の企画と適用は複雑で、多面的で、断片化されていて、予測のつかないプロセスだ」(p.17)。
「ナイーブ」とされた側からは、「文化とか習慣とかがなかなか変えられないからこそ、変えられる制度を改革することでよりよい社会にしようとしているんだ!」と反論されるような気がしますが、この指摘はとても重要なんじゃないかなと思いました。
本書でケーススタディの対象になっているのは、中央銀行の独立性付与(2章)、財務当局の権力増大/財政ルール(3章)、主に途上国における徴税当局の権限増大(4章)、海港や空港の管理運営の民営化(5章)、海外投資の規制緩和(6章)、インフラ整備の契約手法(PFIとか)(7章)。
僕の興味は2章&3章でしたが、多岐にわたる主題が簡単にまとまっていて、世界で起こっていることを概観できた気になりました。
ただ、著者が本書で示そうとした、「logic of disciplineの妥当性が否定されつつある」ことについては、あまり成功していないんじゃないかと思ってしまう。
世界金融危機によってこの精神の説得力は弱まった、と著者は繰り返し語っているけど、現実には世界の各国の政策はそんなに変化していない(ちょっと前に取り上げたGrant and Wilson (2012)とか、もっと露骨にはPhilip Mirowski (2013) Never Let a Serious Crisis go to Wasteとか。外在的な批判でしかないけど)。
Colin Hayが言うように、我々はalternativeを保持していないのであり、説得的なalternativeなしではそれまでのアイディアは、いかにそれが「失敗」だったと言われようと廃棄されない(Hay (2011) "Pathology Without Crisis?", Government and Opposition 46(1), pp.1-31; Blyth (2002))。
でも、それは、本書を2008年~2009年にかけて書いた(Acknowledgementsより)著者に言うのはちょっとズルいかもしれない。
(投稿者:Ren)

ちなみに、著者は「Suffolk University Law School」の教授とのことで、勝手に親近感が湧いていたのですが、ここでいうSuffolkはイギリスの州の一つ(素晴らしい教会がたくさんあります!)ではなくて、アメリカのBoston市がある群の名前のようです。
イギリスとアメリカで同じ地名があることはすごくよくあるので注意しないといけません。(せめてNewをつけるとかして違う地名にしてくれればよかったのに。)
さて、本書は1978~1980年以降の時代を「the era of liberalization」(自由化の時代)と呼び、この時代に共通する諸改革の精神を「the logic of discipline」(規律の論理(?))と名付け、それが様々な政策にどのように表れていたのか、そしてその妥当性が否定されていった(著者はそう主張します――p.14)プロセスを論じていきます。
ちなみに、なぜ1978年~1980年かというと、この時期に中国で改革・開放政策が始まったこと、サッチャー政権とレーガン政権の成立及び彼らの下で市場化政策が行われたことが理由として挙げられています。
著者によれば、logic of disciplineは以下の2つの要素から成り立っています(pp.4-6)。
(1)民主的プロセスを通した統治への深い懐疑
(2)それを是正するために、政治家と選挙民の行動を制約して、間違った決定を下せないようにする。その手段として、法律や条約、契約が頻繁に用いられる。
(1)の民主主義への懐疑の原因として、経済学における公共選択理論(政治家は自分の利益を最大化するように行動する)の発展だけでなく、Huntington, Crozier and Watanuki (1975)が提起した「overload thesis」(人々の政治参加が進み、人々は政治に多くの事を要求するようになったが、その要求は政府の応答能力を凌駕してしまった)も挙げられています(pp.9-10)。
ここまではよくある話なのですが、僕が特に勉強になったのは、(2)の手法をnaive institutionalism(ナイーブな制度主義)と呼んで批判するところ。
著者によればナイーブな制度主義の特徴は、ある国の制度を別の国に導入することで所期の目的を達成できると考えているところにあります(pp.15-17)。
Douglass NorthやPaul PiersonやPeter Hallなどの「新制度論者」は制度の重要性を主張して学界に大きな影響を与えたけど、彼らは制度として公式な(formal)ものだけでなく、文化や習慣などの非公式な(informal)ものも含めた。
formalな制度は簡単に変えやすいけれど、informalな制度はなかなかすぐには変わらない。
新制度論者が指摘していたこの点は、しかしナイーブな制度論者によって忘却されます。
そもそも制度のナイーブな見方は、第二次世界大戦後すぐの政治学者によって否定されていたものだったそうです。
しかし、制度改革をしたい人たちは時間や資源に制約を抱えているためにinformalな制度のことまで考えていられないことや、改革の成果を測定するためにはformalな制度の変化を見るのが分かりやすいから、彼らはformalな制度の変更ばかりを目指すようになってしまった。
でも、たとえば、法文上で素晴らしいことを意図していたとしても、それを適用する段階で政治、行政、社会経済の様々な主体の地からによってその意図は容易に歪められてしまう(1970年代のGreat Societyがあまり大きな変化を起こせなかった理由を著者はこの点に帰しています)。
著者はある論者の次の言葉を引用しています。
「政策の企画と適用は複雑で、多面的で、断片化されていて、予測のつかないプロセスだ」(p.17)。
「ナイーブ」とされた側からは、「文化とか習慣とかがなかなか変えられないからこそ、変えられる制度を改革することでよりよい社会にしようとしているんだ!」と反論されるような気がしますが、この指摘はとても重要なんじゃないかなと思いました。
本書でケーススタディの対象になっているのは、中央銀行の独立性付与(2章)、財務当局の権力増大/財政ルール(3章)、主に途上国における徴税当局の権限増大(4章)、海港や空港の管理運営の民営化(5章)、海外投資の規制緩和(6章)、インフラ整備の契約手法(PFIとか)(7章)。
僕の興味は2章&3章でしたが、多岐にわたる主題が簡単にまとまっていて、世界で起こっていることを概観できた気になりました。
ただ、著者が本書で示そうとした、「logic of disciplineの妥当性が否定されつつある」ことについては、あまり成功していないんじゃないかと思ってしまう。
世界金融危機によってこの精神の説得力は弱まった、と著者は繰り返し語っているけど、現実には世界の各国の政策はそんなに変化していない(ちょっと前に取り上げたGrant and Wilson (2012)とか、もっと露骨にはPhilip Mirowski (2013) Never Let a Serious Crisis go to Wasteとか。外在的な批判でしかないけど)。
Colin Hayが言うように、我々はalternativeを保持していないのであり、説得的なalternativeなしではそれまでのアイディアは、いかにそれが「失敗」だったと言われようと廃棄されない(Hay (2011) "Pathology Without Crisis?", Government and Opposition 46(1), pp.1-31; Blyth (2002))。
でも、それは、本書を2008年~2009年にかけて書いた(Acknowledgementsより)著者に言うのはちょっとズルいかもしれない。
(投稿者:Ren)