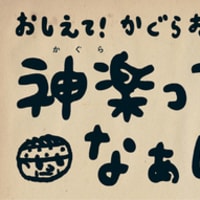「空想の森美術館コレクション」と銘打った企画が掲載された古裂会カタログオークション第57号・特集Ⅲ(2010年10月発行)の表紙と巻頭には、「山本勘助所用の兜」が掲載されている。じつは私は、この兜と一瞬の間だが、すれ違っている。そのことを記す前に山本勘助とこの兜に関する解説を同書から引用(『』内筆者要約)しよう。

『写真は山本勘介所用の兜として1960年に開催された「謙信と信玄展」に出展されたものだが、以後、半世紀にわたって所在が不明であった。
山本勘助(生誕不詳~永禄四・1561)は武田信玄(大栄元・1521~天正元・1573)に仕えた軍師。信玄に勘助ありと評価されるが、歴史的には実在そのものが疑われていた。が、近年に実在を決定する文書が発見され、疑問は霧消した。
勘助が武田信玄に仕えるまでの経歴には諸説が知られる。勘助の活躍を如実にする「甲陽軍艦」によれば、天文十二年(1543)に出仕したとされ、信玄に多くの策を献じて名軍師と称えられた。永禄四年(1561)の第四次川中島合戦において落命と記される。
兜は、鮑の形に打ち出した片貝二枚を中心の鎬筋でつなぎあわせ、二枚貝のごとく左右対称に形を整えている。正面の左右に、梵字の種子二つを金象嵌し、後正面の左右には大きな猪目を飛雲とともに銀象嵌する。眉庇にも雲中に双龍を銀象嵌するほか、鎬筋にも銀象嵌の飛雲を施している。(中略)
正面左右の梵字については、右を釈迦・法華経・准胝観音のバク、左を大黒天・孔雀明王・摩利支天のマの種子と判断される。井上靖著「風林火山」によれば、勘助は摩利支天信仰
を、生涯にわたって護持したという。(中略)
鮑は石決明と呼ばれ、眼病の治療に使われ、目のくもりをはらう貝と信じられた。古くから朝廷に献じられ、伊勢神宮の神饌にも熨斗に加工して供されるなど特別な扱いが知られる。疱瘡病よけに鮑の殻を家の門に掛けたほか、美濃では妊婦が鮑を食べると目の良い子が生まれると信じられた。
山本勘助は「色が黒く、片眼で跛だった。片目は疱瘡で失った」と「風林火山」は記す。映画などで、勘助が着ける眼帯が鮑の貝殻であることも偶然の符帳とはいえない。』
*
武田信玄の戦法は、「孫子の兵法」に重きを置いたものであると考えられ、それを献策したのが山本勘助であっただろう。
天文十年、信州・諏訪を制した武田信玄は、続いて、佐久に侵入、ほぼ佐久の全域を制した後、最後の砦である志賀城攻めにかかった。志賀勢は頑強に抵抗したが、武田軍は、その周辺の戦で討ち取った大将格14人(あるいは15人ともいわれる)、雑兵3000人の首を志賀城の周囲にずらりと並べた。これにより、志賀勢の士気は一気に衰え、ついに城は陥落した。資料的には、この戦に勘助の姿が見当たらないというが、戦法を進言し、それを行なったのが信玄軍であったのだろう。軍師が、常に戦の最前線にいるとはかぎらない。この戦では、勘助は後方にいて戦の経緯を観察しているか、あるいは次の攻略地に向かい、工作を行なっているなどの行動をとっていたのであろう。
敵方の首を城の周囲に置いて戦意を喪失させるという戦法は、「孫子の兵法」によると思われる。古代中国で完成された「孫子の兵法」は日本にも渡来し、中世から戦国時代の戦争では盛んに応用された。古代中国における戦争では、討ち取った敵将の首を竿、矛、槍などに取り付けて進軍するという戦法が用いられたらしい。「孫子の兵法」とは古代中国(春秋~戦国時代)の人「孫武(そんぶ)」とその子孫「孫臏(そんぴん)」によって完成されたとされる。孫武は古代の戦跡や戦記・伝承などを調査し、記録した。その詳細なデータをもとに孫臏が軍学としての「孫子の兵法」を完成させたとみられている。
古代中国(商時代頃。約3000年前)には、すでに戦闘で得た異民族の首を持ち帰り、都邑の門などに懸けておくと呪力を発揮し、邪悪な力を退けるという考え方が確立していた。古代文字の「方」や「邦」は、「国」を表すが、「方」とは横木に屍体を懸けたもので国の境を意味する。人の首を逆さに吊るした「県」も同様の発想であり、方も県も「ここからはわが国である、外敵は入るな」という警告であるという。
このような事例を引いたのは、南九州には「群行する仮面」と呼ばれる仮面群があり、いずれも、仮面が矛に取り付けられ、祭礼行列を先導する事例が多くみられるからである。あるいは、群行することそのものが、「王の御幸」と位置づけられているものもある。古代中国から伝わった「首」を「仮面」が代替し、呪力を持って地霊・悪霊を払うという儀礼が、南九州の祭りに残存しているのではないか、と私は考え続けているのである。これらの祭礼に登場する南九州の「王面」「火の王・水の王」などは、現存する民俗仮面のなかで最も古い部類のものが多数みられる。
*
山本勘助の兜と仮面祭祀発生の源流部とを位置づけて考えてしまった。今はまだ、学問的な考察とはいえないが、いつか、どこかでこの推理を定説として証明してくれるような資料に出会うような気がしてならない。
さて、この勘助所用の兜と「すれ違った」のは、あるコレクターのもとであった。訪ねたときは地元のオークション出品のための準備が進められているところだったが、私は、従前、武具甲冑の類は無縁のものと決めているので、資料の写真だけを撮らせていただき、実物を見ることもせずにコレクター宅を辞した。このようなすれ違いのエピソードは、釣りにおける「逃した魚は大きい」に類似し、さほど珍しいものではない。
珍重すべきは、その後の経緯である。
この二ヶ月ほど後、古裂会の森川氏がお見えになった。そのとき、諸々の話の接ぎ穂に、
「ところで、先日、山本勘助所用の兜が出ましたよ。ただし、それは出品されたオークションで落札されて、今はまた行方知れずとなっていますが・・・」
というようなことを私が述べると、森川氏は、あっと、と飛び上がるような所作をして、
「それです!私は、その勘助の兜を追いかけて、今、こうしてここ九州にいるのです」
と仰ったのである。
この瞬間、私と古裂会・森川氏の距離感が一気に縮まった。その後、森川氏の追跡は成功し、勘助の兜と「空想の森美術館コレクション」が同一のカタログに掲載されるという重複もみせた。これもまた思いがけない交錯であった。
(文字の起源と仮面祭祀については「白川静著作集」宮城谷昌光「太公望」を参照)
*
このカタログオークションでは、もうひとつ、衝撃の出会いがある。それは次回。





![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/35/8c/9dce2c42453d0e3d2de364e09f67c529.jpg)


![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)
![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)
![変異するとき/予告・武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:15>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2a/07/efa184aee8271918ffcc80f4ee249500.jpg)
![紅蓮の炎に映し出されるものは/田口雅己「八百屋お七」[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:14>]アートスペース繭コレクションから④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4e/19/7e04bc2df5ec82a537852c6b8ca6c477.jpg)