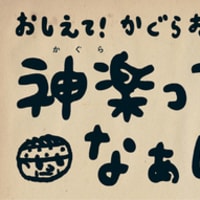本日OPEN!!*今日は作家・武石さんが会場にお出でになります。
開催中の「空想の森アートコレクティブ展」に【武石憲太郎展】が加わりました。現代の芸術表現活動は、日常生活全般の中にあり、変化と進化を繰り返しながら展開してゆくものと把握し、その経緯を楽しみ、鑑賞する機会としましょう。

空想の森アートコレクティブ[武石憲太郎展202]]
【由布院空想の森美術館】2025年4月25日~6月20日
大分県由布市院町川北平原1358
電話 0977-85-7542
開館日 金曜・土曜・日曜 *ご予約いただけば開館可能です。
入館料 大人500円 中学生以下無料
☆ホームページkuusounomori2018.wixsite.com/mysite 由布院空想の森美術館←検索
【小鹿田焼ミュージアム 渓聲館】2025年7月1日~8月31日
大分県日田市源栄町4830-3
(火)(木)定休。祝祭日は営業。
小鹿田の窯元集落に近い小鹿田焼古陶展示室、ショップ、カフェスペース。
☆インスタグラム https://www.instagram.com/ontapottery_museum/
【友愛の森ギャラリー響界】2025年6月25日~8月20日
宮崎県西都市穂北5248
電話 090-5319-4167(高見)
不定休。古い教会を改装した無人のギヤラリーです。ご自由に入りご覧ください。今季より「祈りの丘空想ギャラリー」→「友愛の森空想ギャラリー」→「友愛の森ギャラリー響界」へと改名しました。運営は従前どおり。
☆森の空想ブログ https://blog.goo.ne.jp/kuusounomori

[魂の刻印]
二十数年ぶりに会った武石憲太郎さんは、どこの老人か、と見紛うほどに痩せ、憔悴していた。そのわけを訊くと、半年ほど前に、自作が20点以上、紛失したのだという。現時点でその詳細を語るわけにはいかないが、画家が魂をこめて描いた作品の行方がわからなくなるということはこんなにもつらいことなのか、と思わずにはいられない変貌ぶりであった。そのことと、今回の企画展とは直接の関係はない。個展の約束はその前からできていたものだ。それでも、この企画展を契機として、情報を集積し、実態を確認する作業を続け、無事に作者の元へ作品が戻る機会となればありがたい。作者と、展示空間と、鑑賞者、蒐集家などの心理の奥にある美しい衝動が芸術の核であると信じていたいのである。

[変異するとき]
武石憲太郎氏は、初期の由布院空想の森美術館(1986-2001)によく通ってきてくれて、個展を開催してもらったり、ともに各地へ出かけたりした。そんなある一夜、「お面を描かせてください」とリクエストしてきたので、どうぞ自由に美術館空間を使って下さいと言い残し、自分の部屋で描きかけの原稿を仕上げ、深夜の美術館にもどってみると、「うむ、うーん」と獣のうなるような声が聞こえた。憲太郎さんが、展示された100点あまりの九州の民俗仮面たちと対話しながら絵を描いているのであった。またある時、由布院の隣町の湯平温泉で開催された「由布院と山頭火展」で一緒に仕事をし、温泉街を巡って絵を描いた。旅の俳人・種田山頭火は放浪の途次、この温泉町に立ち寄り、木賃宿の娘さんのやさしさにふれて「しぐるるや人の情けに涙ぐむ」という秀句を残したのである。それにちなむ企画の間じゅう、武石憲太郎は放浪の画人となり、ひたすら絵を描いた。そんなふうに、場や空間に同化し、その空気を瞬時に捉えて画面に定着させるのが武石さんであった。通い続けた海辺の町では、漁師さんと間違えられることもあったらしい。画面には潮風の匂いが漂っている。

[無名ということ]
久しぶりに武石憲太郎氏のアトリエを訪ねた後、少し調べてみた。第一期の由布院空想の森美術館(1986-2001)を閉館して以来、24年の年月が経過しており、その間、彼とは一度も会っていないのだ。風の便りでは、地元でこつこつと描いている、ちかごろ小さな個展を開いたらしい、いや、野に籠り百姓をしている、酒の飲みすぎで体調を崩しているのではないか、などという情報がとぎれとぎれに届いていたのだが、どれも正確ではないようだ。要するに、武石憲太郎は無名の地方画家なのだ。構わぬ。無名であろうがなかろうが、武石さんの絵はいいのだ。どこか心の奥に響いてくる、たとえば1970年代のフォークソングのような親しみと哀愁があるのだ。「無名」を「無明」と呼び変えてもいい。「無」の中に灯る微かな「明」のようなものといおうか。それを彼の周りの人々は察知し、こよなく愛し、認知しているということが大事なのだ。アトリエには旧作と近作とが並び、どれもが70年代の作品と変わらぬ味わいがあった。黒々とした夜の風景の中に、キャンバスを抱えて歩く青年の姿や、老境に入り、さらに風狂の度を加えた彼の姿が刻印されているように思えるのだ。ほんものの芸術家がここにいる、という実感もまた、ずしりと重い手ごたえのあるものであった。