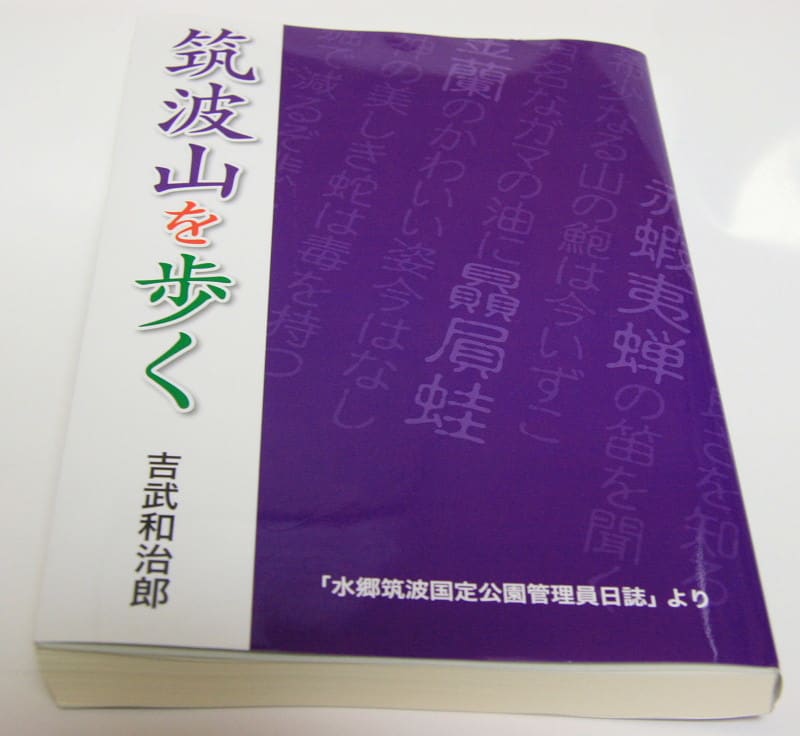東富士五湖有料道路を山中湖ICでおりて、湖岸の729号線を走ります。
日の出前の薄暗い道路で、不慣れな道です。
目指すはパノラマ台なのですが、確実な場所が判らなかったので、とりあえず平野の交差点まで
カーナビに案内させました。
パノラマ台は、730号線で三国峠に行く途中に有るらしい事は、調べて判っていたので
平野で左折するのです。が、それでとんでもないヘマをやらかしました。
平野は、変速の4差路なのです。
平野で左折したまでは良かったのですが、なんか感じが変です。
そのうち「道志みち」の案内が、ガーン!?
やっちまったぜ! 一つ手前を左折してしまったのです。
あわててUターンして平野へ、もちろん連続して左折の道が有る交差点です。
左に曲がってすぐに又 左です。まるでUターンなみの曲がりできついこと。(泣)
右前方に光りが当たり始めた雄大な富士山が見えます。
早くパノラマ台を見つけなければ、チャンスを逃してしまう。
きついカーブの曲がり角に、左にトイレの有る駐車スペースが有りました。
2台ほど車が駐まっています。
とりあえずそこに車を駐めて、富士山の写真を撮る事にしました。

そこへもう一人の男性がやってきて「ここはパノラマ台ですか?」と聞いてきた。
「イヤー私も初めてなので、良くわからないのですが」と答えると「実は三国峠まで行って見たが
それらしい駐車場が無かったので、戻ってきたのです。」という。
「それじゃここがパノラマ台じゃないでしょうか。パノラマ台にはトイレが有ると聞いてますから。」
そんな話をしているところに、中年のご夫婦がやってきた。
挨拶をして「ここはパノラマ台でしょうか?」と尋ねると「そうですよ。」という。
どちらからと聞くと「ここ山中湖に住んでいるのです。ここからも見えますよ。」という。
「あなたはどちらから?」と聞くので、車のナンバーを指さして「ここからです。」と答えると
「ああ茨城からですか、どのくらいかかりました。」「2時間半かかりましたよ」
そんな話をしていると、先ほどの男性が戻ってきて「私は群馬から来た」という。
名前も知らない人達が、こんな風に話せるのも、旅の楽しみでもあり、情報源でも有る
三人でしばらく富士山談義をして楽しんだ。
ここがパノラマ台と判れば、後はここから「鉄砲木ノ頭(てっぽうぎのあたま)」を目指して登るだけである。
登山靴に履き替え、ザックに持ち物を詰めていると、奥に止まっていた車から年配の男性か降りてきた。
話を聞くと、昨日は杓子山に登って富士山の写真を撮っていたという。
なんでも富士山の廻りの山を、泊まり込みで撮り歩いているという猛者である。
その前は谷川岳に登っていたというから凄い。
「早く山に登って、良い写真を撮ってください。」という励ましを貰って、私の登山が始まった。
登山道はトイレの左脇から、カヤトの原の踏み跡をたどって登っていく。
来るとき富士五湖有料道路に、-7度の表示が有った寒さである。
何よりも手の指がかじかんで、薄い革手袋では役に立たないが、厚い革手袋ではシャッターが押せない。
踏み跡は凍り付き、霜が降りたように一面に白くなっていた。
踏み跡は何本も有り、古い物は雨で流されて深い溝になっている。
どれが正規のルートなのか判らないので、滑らないような踏み跡を登る。

振り返ると、抜けるような青空に富士山が聳えている。
幾度となく立ち止まり、富士山を撮った。

カヤの原に光りも当たり始め、金色に輝きだした。
ひんぱんに「ドドーン」という腹に響く音がする。
何だろうと思ったら「自衛隊の砲撃の音」だと後で知った。
「バッバッバッ」と連続するのは、さしずめ「機関銃」なのだろうか。
平和な富士山と砲撃の音、何とも不釣り合いな取り合わせではないか。
この辺の人は、毎日あれを聞いてどう思っているのかな。

山頂直前の凍った坂道

やがて「山中諏訪神社奥宮」と書かれた立派な祠の建つ山頂に着いた。
一帯は地面がむき出しの原で、凍り付いたガチガチの黒い土である。

その廻りはカヤトの原が続いている。
奥の三角点には「明神山」と書かれた標柱が有る。標高1291メートルである。
三国峠とパノラマ台に向かう方向表示版は有るが、高指山や切通峠に向かう表示がない。

ザックに三脚をくくりつけた年配の男性が来ていた。
三国峠から登って来たらしい。

これは自分の陰も写った失敗作だが、富士山の右側に南アルプスの山々が写っているので
載せて見ました。

カヤを前景に入れて、カヤトの山らしい雰囲気をだして。

200ミリの望遠で見ると、右の狭い斜面にジグザグの登山道も見て取れる。
あんな狭い所を登っているんだナー。
ここから北の高指山に向かうルートは、東海自然歩道の一部を兼ねている道で
神奈川と山梨の県境の尾根道が続く。

山頂から左の尾根に高指山(たかざすやま)に続く道がある。だがその案内板は無い。
山頂は神奈川県側の展望が無い、林が視界を遮っている。
山梨県側は、カヤトの原で抜群の展望である。
パノラマ台の緯度と経度をカーナビのGPS情報から得たものを掲載します。
N 35°24′34″
E 138°54′45″
ハンディGPSの登山口の緯度・経度は
N 35°24′45.51″
E 138°54′34.52″
駐車した場所より、奥で計っているので、秒数は違うが
あるいはハンディGPSの精度の方が高いかも知れない。
その三に続く。