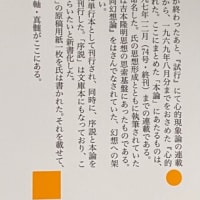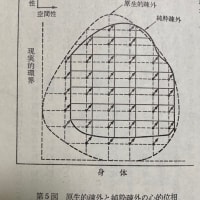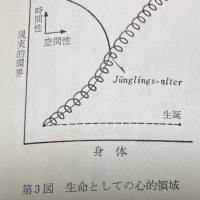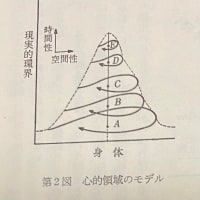言の葉113 〈信〉の構造 吉本隆明•全仏教論集成1944.5〜1983.9
③ 歎異抄に就いて
亡き吉本邦芳君に捧ぐ
投稿者 古賀克之助(吉本さん同様、当方も信の外にいるものです。)

〈信〉の構造 吉本隆明•全仏教論集成
1944.5〜1983.9 昭和五十八年十二月15日第一刷発行 著者吉本隆明 発行所 株式会社 春秋社
2 歎異抄に就いて
亡き吉本邦芳君に捧ぐ より抜粋

——むさぼりて厭かぬ渠ゆゑ
いざここに一基をなさん
正しく愛しき ひとゆえに
いざ さらに一を加へん
(宮沢賢治「詩の塔」より)
僕は親鸞の詩人的資質が仏教の倫理体系に遭遇した場面を想像してみる。殊に無量寿経や阿弥陀経の途轍もない観念論や観無量寿経の心理学に面した折の、彼の困惑を想像することは意義あることだ。道元等同時代の宗教家がすべて仏教体系の内部に帰したとき親鸞独りがこの体系を突き崩し、引退かざるを得なかった理由がはっきりするだらうから。「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり(歎異抄十九)」それほど、彼の資質と三部経とは異質のものだ。
僕は且つてルッターの「ハイデルベルヒの論争」を読んで、諸家が仏教に於ける親鸞の位置を、キリスト教に於けるルッターに比較する理由を合点したが、資質は更に親鸞の方が悲し気である。
親鸞の文章にある唯信や浄土の理念は、僕を困らせはしないが、あの流れる非調の韻律は僕の胸を外れてはゆかぬ。僕は初めに所謂浄土三部経といはれる大経、阿弥陀経、観経には資質的には反撥しながら、理念的には惹かれた親鸞を空想したまでである。いや、これでは言葉が悪いかも知れぬ。資質的に反撥したからこそ理念的に惹かれていったと云へるはずだ。何故なら、彼こそこの様な逆説心理を思想の骨格として歩んだ唯一の宗教家だったから。
親鸞の思想系列は成立過程としての「三願転入」の釈義が諸家により行はれているが(例へば三木清の遺構「親鸞」についてみられたし)僕は余り信じない。僕には彼が体系など企んだとは思はれぬのだ。「誠に知んぬ悲しき哉愚禿鸞愛欲の広海に沈没し、名利の大山に迷惑して、定聚の数に入ることを喜ばず。真証の証に近づくことをたのしまず。恥ずべし、傷むべし(教行信証)
この様な感懐を各所に浮かべてゐる文章が、何故に体系の書でなくてならぬのか、僕は同意しない。
教=無量寿経、行=第十七願、信=第十八願、証=第十一願、真仏土=第十ニ願及び第十三願
この様な対比など愚かなことだ。
けれどこゝに確かな事実がある。それは彼に三度の思想的転期があったといふ事だ。その時期に就いては諸家の一致した通説を僕も疑わない。今日残されてゐる親鸞の行伝(例へば「本願寺聖人親鸞伝絵」についてみられたし)には幾多の虚構と誇張が混ざってゐるが「然るに今特に方便の真門を出でて選択の願海に転入せり」と第三願への転入を告げた親鸞自身の真実だけは信じよう。
彼は夢想家であり、時には感傷家でさへあったが、恒に現実の悲しみが誇大に写ってならなかった彼の網膜に僕は何等不潔なものを見出すことが出来ぬ。当時の仏教家が理性と感性との統一を武器として、人間存在の深義を尋ねはじめた時、人間の生死と歴史的現実の信義を徹底的に凝視し、そこに人間存在の危機を刻み出したのも彼のその網膜に外ならなかった。「正像の二時はおはりにき如来の遺弟悲泣せよ」(正像末和讃)瞋りであったか、祈りであったか。
僕たちは歎異抄を第三願の骨髄に見る。「万行諸善の仮門」を出て「善本徳本の真門に廻入し」更に「選択の願海」に転入したいと云ふ彼の言葉を疑わないが、悲しいかな僕は信仰を持たぬ。僕はこゝに唯一の悲しみを提げた人間がゐたと云ふ真証さへあれば、又遠く旅立つに事欠かないやうだ。
歎異抄十九章のうち前十章が親鸞の語録の祖述であることは周知だ。僕はこの十章に何等曖昧な言葉も偽念も見出すことが出来ぬ。被害妄想と思はれる徹底的な自己謙譲と、空前の自念放棄のなかにいさゝかの偽りをも感ずることが出来ぬ。確かにひめられてゐるやうだが、稀有の苦悩と忍耐とが。否これは僕の思ひ過ごしであらうかそんな筈がない。僕は天性などと云ふものを信じてゐないのだから。すべて現在あるところは、自らの意思と宿命とで得たものだ。親鸞の絶対他力の地も自ら得たもので、流れて到った自然の地ではあるまい。それが自然に見えれば見ゆるほど——。
「世々生々に無量無辺の諸仏菩薩の利益によりて、よろづの善を修行せしかども、自力にて生死を出でずありし故に(御消息集)」流転の段階と宿命とを遠き劫初に視る親鸞の眼は如何にも悲し気であるが、歎異抄全篇を貫く、これが光であるやうだ。彼はすべての善は不要であると説く、それは念仏にまさる善はないからだ。すべての悪は畏ろしくない。人間のやる悪などたかが知れてゐるのだ。と——。
法文等に疑質があれば南都北領のゆかしき学生に問ひたまへ、親鸞は念仏しか知らぬのだ。「いづれの行もおよび難き身なれば、とても地獄は一定のすみかぞかし(歎異抄ニ)」
女々しい自嘲も陶酔も感ぜられぬ。慈円の如き仏教を以って教養体系の一つと考えた知識人が、法然親鸞の出現を目して「誠にも仏法の滅相うたがひなし」と罵ったのも故なきことではない。親鸞の膨大な夢想と苦悩とを凡庸な知識人が呑み得た筈がない。さあれ苦しき事を人は好まない。何故に親鸞だけが、それを耐えたのであらうか。僕は言わぬ、言ってはならぬのだ。「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや。しかるを世の人、つねにいはく悪人なほ往生す、いかにいはんや善人をや、この条一旦そのいはれあるににたれども、本願他力の意趣にそむけり(歎異抄三)」僕はこの言葉の親鸞的真実を彼の宗教々義から演繹しやうとは思はぬ、唯常人の称へる善悪が微塵のやうに吹き飛ばされ、改変されるのを見る。それは壮観であるのか、いや悲しみ極まる筈だ。何故なら親鸞の壮絶な人生的苦悩を、僕は言葉の裏に見ないわけにはゆかぬからだ。
ゆづりわたすいや女事
みのかはりをとらせて、せうあみだ仏のめしつかう女なり。しかるをせうあみだ仏、ひむがしの女房にゆづりわたすものなり、さまたげをなすべき人なし、ゆめゆめわづらいあるべからず、のちのちのために、ゆづりふみをたてまつるなり、あなかしこあなかしこ
これは親鸞が吾が子のみうりのために書いた証文だ。僕たちがこゝに彼の悪機を見ようが善機を見ようが自由である。僕は大感傷を却けてこの身売証文を読むのだが、彼の悲しみには到達しないやうだ。何故であらうか、僕は秘す。けれど親鸞はひそかにもらした、その機微をその真実を「善人なほもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」と——。
弥陀のはからひに徹するほど彼はますます孤独でなくてはならなかった。それは彼に生涯伴った絶対矛盾であった。彼は肉親を突き放つ、自らをめぐる特殊性から逃れんがために。
彼の外には唯普遍的な世界があり、そのなかに彼は孤立する点だ。世界は唯無心に彼を載せている——彼がもとめてゐたところではあるまいか。即ち絶対他力本願の生まれるために、それが必要な土壌であった。彼は「総じてもて存知せざるなり」「面々の御はからひなり」と云ふような、つき放った借辞法を多く用ひてゐる。これは重要だ。それらは各々彼の思想の中核に衝き当たって反射した言葉だから。「親鸞は弟子一人ももたずさうらふ(歎異抄六)」
ともあれ歎異抄で親鸞といふ一個の人間に衝き当たるために、僕たちは弥陀とか、往生とか念仏とか云ふ一見重要に思はれる概念を捨てていかねばならぬ。
教行信証をはじめ、彼の主著は大体仏典の要門を集成したものだが、その折々にもらす彼の感懐だけが、高い格調を以って鳴りはじめるのは何故だらうか、どうして彼は仏教者でなくてはならなかったのか、「念仏は行者のため非行非善なり、わがはからひにて行ずるにあらざれば非行と云ふ。わがはからひにてつくるにもあらざれば非善といふ、ひとへに他力にして自力をはなれたるゆへに行者のためには非行非善なりと云々(歎異抄八)」そうだらうか、僕は疑う。人々は確に誤ってゐる、心に則って思想が生まれるので、思想に則って心が歩むのではあるまい。
されば彼の主著中の感懐は仏教のために鳴らず、むしろ人間性の機微のために鳴ってゐると思ふのは僕の僻眼か。
「たまたま行信を得ば、遠く宿縁をよろこべ。若し又、このたび疑網に覆蔽せられなば、かへりてまたを曠劫を逕歴せん(教行序)」行路が難いときたまたま仏法が彼を捉えた。僕が尊重するのはそれだ。
僕は且つて往生要集を読み源信の正気を疑った事がある。あの陰惨な地獄の絵巻を捻出した歴代の仏家のレアリズムも不快だが、僕はそれを集成して、勧善の手段としてゐるような源信の心理が憤ろしかった。誰のために僕は憤ったのかいまは忘れた。僕たちは親鸞が源信を祖として学び、法然の衣鉢を継いだのを知っているが、この三代目は決して亜流ではない。彼は人間心理に通暁したが、決して人をおびやかさなかった。彼に於て初めて往生は高らかな再生の謳歌であったようだ。人間は未だ生死の現実を超えはしないが、彼は思想を以って否実力を以ってこれを超えた恐らく最初の人であった。
念仏まうしさふらへども、踊躍歓喜のこゝろおろそかにさぶらふこと、またいそぎ浄土へまいりたきこゝろのさふらはぬは、いかにとさふらふべきことにてさふらふらんと、まうしいれてさぶらひしかば、親鸞もこの不審ありつるに、唯信坊同じこゝろにてありけり、よくよく案じみれば、天におどり、地にをどるほどに、よろこぶべきことをよろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもひたまふべきなり、よろこぶべきこゝろを、をさへてよろこばせざるは煩悩の所為なり(中略)久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土はこひしからずさふらふことまことによくよく煩悩の興盛にさふらふにこそ、なごりをしくおもへども、娑婆の縁つきて、ちからなくしてをはるときに、かの土へはまひるべきなり(歎異抄九)
歎異抄の中核だが、恐らくこの十数行の中に親鸞の最も重要な思想が秘められてゐる。畏るべき逆説のなかをかれは驕らず静かに歩んでゐるやうだ。僕たちは彼の相に不安な片鱗さへも認めぬ。だか思へばこれは空前の思想である。死とは彼にとって生であったのか、死であったのか。愚かな反問をしてはいけない。僕たちが身を以って生死を解決する日は「娑婆の縁」つきた日だ。その日は遅くも早くもやって来ない。何と当たり前の事を彼は言ってゐるのか。併も彼の外に誰もこの当然の事実を改めて確かめる者はゐなかった。
さあれ僕は来世などを信ずる気にはならぬ。併し生きることが死よりも遥かに辛く悲しいことを少しも疑はない。僕たちの感官は「所労」のために痛まず、むしろ精神のために痛むからだ。煩悩がない奴は人間ではないと親鸞は僕達に繰返してやまぬ。いやむしろ煩悩のない奴は人間の資格がないと、僕たちにはそのやうに聞えてくる。人間がなくて浄土など要るか、それが彼が抱いた最も確かな思想だ。
僕はこゝで一応親鸞の思想と訣別せねばならぬ。この章以後は率直に親鸞の響だけが伝はらぬからだ。歎異抄の著者は、専ら親鸞教義の鮮明化と異解の論破に忙しいようだ。これ以降提出されてゐる疑質は末梢で、最早僕を動かしはしない。
たとひ諸門こぞりて念仏は、かひなき人のためなり、その宗あさしいやしといふも、さらにあらそはずして、われらが如く、下根の凡夫、一文不通のものと信ずればたすかるよし、うけたまはりて信じさふらへ(中略)たとひ自余の教法すぐれたりとも、みづからがためには、器量及ばざればつとめがたし云々
僕らはこの言葉の中から唯亜流の弁解をきくだけだ。決して僻眼ではない。親鸞は仮門を出て真門に入った。難を捨てゝ易に就いたのではない。併るに最早こゝには親鸞の逆説も、あの空前の思想も感じられないではないか。何故であるのか、亜流はつねに形骸を守るに忙しいからだ。
親鸞は早くから人間の無意識の構造に眼を注いだやうだ。後人の附会として一笑するわけにはゆかぬ。彼の無意識の構造への味到は恐らく「弥陀のはからひ」と彼が云ふ所と関聯してゐる、間違ひないところだ。人間の善悪の観念の無意識域への拡張は、明らかに彼の思想の一つの骨格をなしてゐた。「善悪のふたつ総じてもて存知せざるなり(歎異抄十九)
何も何くはぬ顔をしたかったわけではない。唯それを挙げつらはぬだけだ。例へば愚禿抄の中から二隻四重の体系を引出すことは容易である。併し今となってそれが親鸞と出遇ふ道であらうか、僕はむしろ愚禿抄の中の「愚禿が心は、うちは愚にして外は賢なり」を見出して其の重たい自嘲に一念を費やすことを好むのだ。
彼は弘長二年十一月二十八日天寿を全くして死んだ。
(以下略)