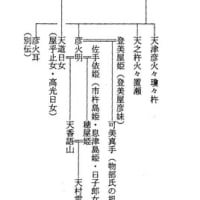私が字母歌の暗号解読を思い立ったきっかけは、村上通典氏の『「いろは歌」の暗
号』と出会ったことによる。この本は1994年1月に㈱文芸春秋から出版され、著者
は今治明徳高校の数学の先生であったが、古代史の暗号解読に専念するため退職さ
れたという。数学的思考が随所に見られるため、数学音痴の私には理解不能の箇所
も多少あったが、なにより素晴らしいのは暗号解読のための基本的なルールに気づ
かれた事である。
これまでの字母歌の暗号説は「いろは歌」の七段書きした沓の部分の<咎なくて死
す>論に終始していたが、村上氏は「いろは」「たゐに」「あめつち」にもこの分
かち書きをためされたのである。その結果
「いろは」の五段書きの中に「やまのうえおくら」の名を拾ってみると絵文字
「上」の形に「山のうえおくら」の名が隠されていることを発見した。下図参照。
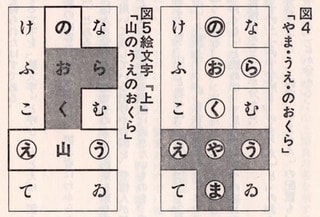
同様に「あめつち」でも試されておられ、五段書きの中から「やまのうへおくら」
を拾うと、やはり絵文字「山」の形の一部分となっており、これも仕組まれた暗号
としている。下図参照。
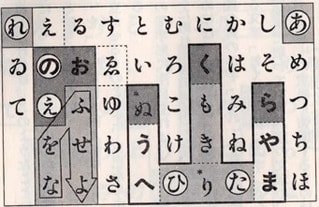
一方、「たゐに」の六段書きをした沓の部分を、右から読むと「なぞあくうらえ
ぬ」つまり「謎明く裏得ぬ」という暗号文になる事を発見した。下図参照。
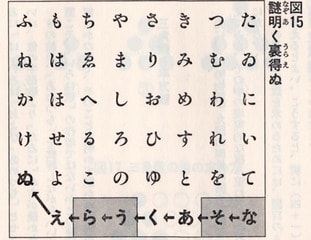
また、四段に分かち書きすると、六行目から九行目にかけて「やまのうへおくら」
の名が規則性を持って配列されていることも指摘している。下図参照。
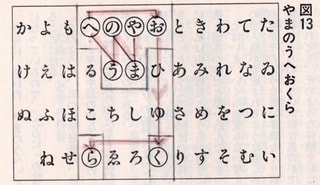
私はこれらの村上氏の指摘した配列がすべて「山上憶良」の名前を示している事に
衝撃をうけた。なぜなら1996年3月から当時所属していた短歌誌『炸』に「古代よ
りの暗号」という題で、山上憶良の「秋の七草」が日本のルーツを秘めた暗号歌と
する仮説の連載を始めたばかりだった。この村上氏の発見に勇気づけられ、約10年
かけて、50回の連載をし、2007年に一冊の本にまとめることが出来たのだった。
村上氏の『「いろは歌」の暗号』には関連の諸説が掲載されているが割愛して、
暗号「山上憶良」を発見した「いろは」「たゐに」「あめつち」の分かち書きの
表を土台にしてさらに考察推理したいと思います。
号』と出会ったことによる。この本は1994年1月に㈱文芸春秋から出版され、著者
は今治明徳高校の数学の先生であったが、古代史の暗号解読に専念するため退職さ
れたという。数学的思考が随所に見られるため、数学音痴の私には理解不能の箇所
も多少あったが、なにより素晴らしいのは暗号解読のための基本的なルールに気づ
かれた事である。
これまでの字母歌の暗号説は「いろは歌」の七段書きした沓の部分の<咎なくて死
す>論に終始していたが、村上氏は「いろは」「たゐに」「あめつち」にもこの分
かち書きをためされたのである。その結果
「いろは」の五段書きの中に「やまのうえおくら」の名を拾ってみると絵文字
「上」の形に「山のうえおくら」の名が隠されていることを発見した。下図参照。
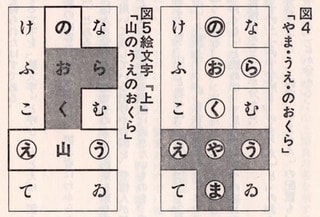
同様に「あめつち」でも試されておられ、五段書きの中から「やまのうへおくら」
を拾うと、やはり絵文字「山」の形の一部分となっており、これも仕組まれた暗号
としている。下図参照。
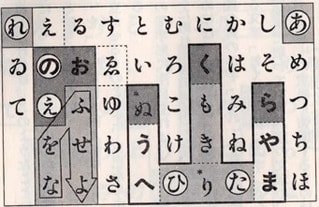
一方、「たゐに」の六段書きをした沓の部分を、右から読むと「なぞあくうらえ
ぬ」つまり「謎明く裏得ぬ」という暗号文になる事を発見した。下図参照。
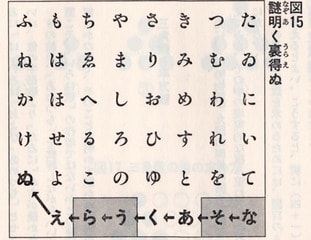
また、四段に分かち書きすると、六行目から九行目にかけて「やまのうへおくら」
の名が規則性を持って配列されていることも指摘している。下図参照。
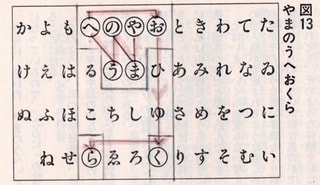
私はこれらの村上氏の指摘した配列がすべて「山上憶良」の名前を示している事に
衝撃をうけた。なぜなら1996年3月から当時所属していた短歌誌『炸』に「古代よ
りの暗号」という題で、山上憶良の「秋の七草」が日本のルーツを秘めた暗号歌と
する仮説の連載を始めたばかりだった。この村上氏の発見に勇気づけられ、約10年
かけて、50回の連載をし、2007年に一冊の本にまとめることが出来たのだった。
村上氏の『「いろは歌」の暗号』には関連の諸説が掲載されているが割愛して、
暗号「山上憶良」を発見した「いろは」「たゐに」「あめつち」の分かち書きの
表を土台にしてさらに考察推理したいと思います。