暗号<秋の七草>の区分からいえば国神系=出雲系=葛城系で天皇の位についた弘計
(顕宗天皇)億計(仁賢天皇)の二王子を守ったのは叔母である忍海飯豊青尊が丹波
との絆があったためと思われ、それは尊称の<忍海>や<青>に込められていました。
しかし彼女の尊称の中で最も知られている飯豊(いひどよ)とは何でしょうか?
イヒドヨ(以比止与・伊比止与)とは鳥の名でフクロウのことです。
日本書紀では皇極3年3月条に休留(イヒドヨ)が豊浦大臣(蘇我蝦夷)の大津の
宅(いへ)の倉に子産(う)めり(瑞祥のひとつとして)
天武10年8月条に伊勢国が白茅鴟(白フクロウ)を貢れり(貢物)
の記事がありますが、古くは木菟(つく・ミミズク)とも言い、仁徳天皇元年条に興味
深い誕生説話があります。
父である応神天皇が大臣(武内宿禰)に語るには、仁徳天皇が生まれる日、産殿に木
菟が飛び込んで来た「是、何の瑞ぞ」と問うと、大臣は「吉祥なり。また昨日私の妻
が出産にあたり、鷦鷯(さざき・みそさざい)が産屋に飛び込んできました。」と申
しあげました。天皇は我が子と大臣の子が同日に生まれた事を瑞祥と考え「是天の表
(しるし)なり、お互いに鳥の名を換え子に名づけて、後の世の契(しるし)としよ
う」と言い、太子には<大鷦鷯皇子>、大臣に子には<木菟宿禰(平群都久宿禰)>
と名付けられたと述べています。
日本書紀に記されるイヒドヨ(フクロウ・木菟)に関する記事の特徴は
① 吉祥と考えていること
② 出産に係わる場面に登場していること
では飯豊王のフクロウの名に込められた意図を推量できそうな記述が何か残されている
でしょうか?それがあるのです。「どうしてこのような記事があるの?」と誰もが思う
ような内容なのです。
日本書紀、清寧天皇3年条
秋、7月に飯豊皇女、角刺宮にして、与夫初交(まぐはひ)したまふ。人に謂(かた)
りて曰(のたま)はく「一女(ひとはしをみな)の道を知りぬ。又安(いづく)にぞ
異(け)なるべけむ。終に男に交(あ)はむことを願(ほり)せじ」(比に夫有りと
曰へること、未だ祥(つばひらか)ならず)
この解釈は
秋7月、飯豊皇女は角刺宮ではじめて男と交わり「女の道を知ったが<特にどうとい
うこともないので>もう男と交わりたいとは思わない」と述べた。(夫があったか否
かは 定かではない)と一般的には理解されている。
日本書紀の原文は漢文で書かれており<・・>の部分は「又安可異」。漢和辞典で調べ
ると「安」はいずくんぞ(何ぞ・どうして)。「可」はべし。「異」はあやしむ・めず
らしい・ことなる。の意味を持っている。
<特にどうということもない>という解釈が正しいかどうか疑問がわきました。<また、
どうしてこんな事になってしまったの>と意訳できれば次の<もう男と交わりたくない>
という心情が理解できるのですが・・・。
成人した女性なら望むと望まないに関わらず只一度の性交であっても妊娠する可能性が
ありますので、先の一文を想像たくましく解釈すれば、男性と交わった未婚の飯豊皇女
が思いがけない妊娠をし「もう男と交わりたくない」と言った可能性があるのではない
でしょうか?
私は今回の謎解きの「藤と雲雀」の結末にしようと思うものに大分前に出会っていたの
ですが飯豊王の<いひどよ=フクロウ>と結びつけることが出来ず悩んでいましたが、
この説話から飯豊王が母となったのではと考えつきました。<秋の七草の暗号>のルー
ル、言葉遊び的発想を思いだし<おフクロウ>→<おふくろ>→<母>と考えました。
<おふくろ>の語源を調べてみると文献的には室町時代からみられ、諸説ある語源の中
で「女性の子宮を<ふくろ・袋>と呼んだことから母親を<おふくろ>と言うようにな
った」とするのが妥当な説のように思いました。
日本書紀のこの記事の前には「清寧天皇3年夏4月に億計王を以て皇太子(ひつぎのみ
こ)とす。弘計王を以て皇子とす。」とありその後に突然挿入された飯豊王のまぐはひ
の記述は二王子の母が誰であるかを暗示させるもののようです。
当然ながら父親たる男がいるはずですが<夫があったか否か定かではない>とわざわざ
注記したことも相手を明かせない事情があった為でしょう。
億計、弘計の二王子の父は大泊瀬皇子(雄略)に射殺された市辺忍歯別皇子と記紀に記
されており、母が飯豊王であるとすれば古代といえども許されない兄妹婚です。当然な
がら生まれ来る子供は隠され、秘密裏に養育されたことでしょう。
二王子の名前は億計(おけ)と弘計(をけ)、現代人の私にはどのように発音し、どの
ように聞き分けたのか知りたいところですが、このokeという音は重要で市辺忍歯別皇子と繋がりがあります。
市辺忍歯別皇子は安康天皇3年に淡海の久多綿の蚊屋野で大泊瀬皇子(雄略)と狩りに
出かけましたが、馬上から矢を射かけられ帳内(とねり)の佐伯部仲子と共に射殺され
ます。古事記によると遺体を切り刻んだ上に、ひとつの飼馬桶に入れられ土と等しく地
中に埋められたとあり、遺族にとってはなんとも痛ましい事件であり、その無念さから
okeという名を残す結果になったのではないかと思われます。
この事件の後、二王子は後難を恐れて播磨の志自牟(縮見)に逃れたと記されています。
この記事は事実でしょう。しかし、それ以前飯豊王は秘密の子らを忍海角刺宮で産む訳
にはいかないでしょうから、若狭の御名代のご料地である青郷で出産し、幼き二王子を
実質的に養育したのが丹波国造・海部阿知らと思われ、そこを安宮といい、その後与謝
郡の眞鈴宮に移し奉ったという経緯を『丹後風土記残欠』などは記録していたものと思
われます。
(顕宗天皇)億計(仁賢天皇)の二王子を守ったのは叔母である忍海飯豊青尊が丹波
との絆があったためと思われ、それは尊称の<忍海>や<青>に込められていました。
しかし彼女の尊称の中で最も知られている飯豊(いひどよ)とは何でしょうか?
イヒドヨ(以比止与・伊比止与)とは鳥の名でフクロウのことです。
日本書紀では皇極3年3月条に休留(イヒドヨ)が豊浦大臣(蘇我蝦夷)の大津の
宅(いへ)の倉に子産(う)めり(瑞祥のひとつとして)
天武10年8月条に伊勢国が白茅鴟(白フクロウ)を貢れり(貢物)
の記事がありますが、古くは木菟(つく・ミミズク)とも言い、仁徳天皇元年条に興味
深い誕生説話があります。
父である応神天皇が大臣(武内宿禰)に語るには、仁徳天皇が生まれる日、産殿に木
菟が飛び込んで来た「是、何の瑞ぞ」と問うと、大臣は「吉祥なり。また昨日私の妻
が出産にあたり、鷦鷯(さざき・みそさざい)が産屋に飛び込んできました。」と申
しあげました。天皇は我が子と大臣の子が同日に生まれた事を瑞祥と考え「是天の表
(しるし)なり、お互いに鳥の名を換え子に名づけて、後の世の契(しるし)としよ
う」と言い、太子には<大鷦鷯皇子>、大臣に子には<木菟宿禰(平群都久宿禰)>
と名付けられたと述べています。
日本書紀に記されるイヒドヨ(フクロウ・木菟)に関する記事の特徴は
① 吉祥と考えていること
② 出産に係わる場面に登場していること
では飯豊王のフクロウの名に込められた意図を推量できそうな記述が何か残されている
でしょうか?それがあるのです。「どうしてこのような記事があるの?」と誰もが思う
ような内容なのです。
日本書紀、清寧天皇3年条
秋、7月に飯豊皇女、角刺宮にして、与夫初交(まぐはひ)したまふ。人に謂(かた)
りて曰(のたま)はく「一女(ひとはしをみな)の道を知りぬ。又安(いづく)にぞ
異(け)なるべけむ。終に男に交(あ)はむことを願(ほり)せじ」(比に夫有りと
曰へること、未だ祥(つばひらか)ならず)
この解釈は
秋7月、飯豊皇女は角刺宮ではじめて男と交わり「女の道を知ったが<特にどうとい
うこともないので>もう男と交わりたいとは思わない」と述べた。(夫があったか否
かは 定かではない)と一般的には理解されている。
日本書紀の原文は漢文で書かれており<・・>の部分は「又安可異」。漢和辞典で調べ
ると「安」はいずくんぞ(何ぞ・どうして)。「可」はべし。「異」はあやしむ・めず
らしい・ことなる。の意味を持っている。
<特にどうということもない>という解釈が正しいかどうか疑問がわきました。<また、
どうしてこんな事になってしまったの>と意訳できれば次の<もう男と交わりたくない>
という心情が理解できるのですが・・・。
成人した女性なら望むと望まないに関わらず只一度の性交であっても妊娠する可能性が
ありますので、先の一文を想像たくましく解釈すれば、男性と交わった未婚の飯豊皇女
が思いがけない妊娠をし「もう男と交わりたくない」と言った可能性があるのではない
でしょうか?
私は今回の謎解きの「藤と雲雀」の結末にしようと思うものに大分前に出会っていたの
ですが飯豊王の<いひどよ=フクロウ>と結びつけることが出来ず悩んでいましたが、
この説話から飯豊王が母となったのではと考えつきました。<秋の七草の暗号>のルー
ル、言葉遊び的発想を思いだし<おフクロウ>→<おふくろ>→<母>と考えました。
<おふくろ>の語源を調べてみると文献的には室町時代からみられ、諸説ある語源の中
で「女性の子宮を<ふくろ・袋>と呼んだことから母親を<おふくろ>と言うようにな
った」とするのが妥当な説のように思いました。
日本書紀のこの記事の前には「清寧天皇3年夏4月に億計王を以て皇太子(ひつぎのみ
こ)とす。弘計王を以て皇子とす。」とありその後に突然挿入された飯豊王のまぐはひ
の記述は二王子の母が誰であるかを暗示させるもののようです。
当然ながら父親たる男がいるはずですが<夫があったか否か定かではない>とわざわざ
注記したことも相手を明かせない事情があった為でしょう。
億計、弘計の二王子の父は大泊瀬皇子(雄略)に射殺された市辺忍歯別皇子と記紀に記
されており、母が飯豊王であるとすれば古代といえども許されない兄妹婚です。当然な
がら生まれ来る子供は隠され、秘密裏に養育されたことでしょう。
二王子の名前は億計(おけ)と弘計(をけ)、現代人の私にはどのように発音し、どの
ように聞き分けたのか知りたいところですが、このokeという音は重要で市辺忍歯別皇子と繋がりがあります。
市辺忍歯別皇子は安康天皇3年に淡海の久多綿の蚊屋野で大泊瀬皇子(雄略)と狩りに
出かけましたが、馬上から矢を射かけられ帳内(とねり)の佐伯部仲子と共に射殺され
ます。古事記によると遺体を切り刻んだ上に、ひとつの飼馬桶に入れられ土と等しく地
中に埋められたとあり、遺族にとってはなんとも痛ましい事件であり、その無念さから
okeという名を残す結果になったのではないかと思われます。
この事件の後、二王子は後難を恐れて播磨の志自牟(縮見)に逃れたと記されています。
この記事は事実でしょう。しかし、それ以前飯豊王は秘密の子らを忍海角刺宮で産む訳
にはいかないでしょうから、若狭の御名代のご料地である青郷で出産し、幼き二王子を
実質的に養育したのが丹波国造・海部阿知らと思われ、そこを安宮といい、その後与謝
郡の眞鈴宮に移し奉ったという経緯を『丹後風土記残欠』などは記録していたものと思
われます。














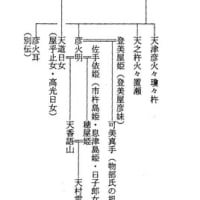








ように聞き分けたのか知りたいところですが、……
小生は、昭和8年生まれで2歳年上の兄に、犬の「い」と井戸の「ゐ」、鉛筆の「え」と絵具の「ゑ」の発音が区別できるようになれと、練習させられたことがあります。
今思えば、それは、ワ行を「わ=ウア、ゐ=ウイ、う=ウウ、ゑ=ウエ、を=ウオ」と発音する練習だったような気がします。
こんなことをいうのは、小生がある時期まで、「お」と「を」の発音の区別は誰でも当たり前にしていると感じていたからです。
このたび、「秋の七草・山上憶良」で検索し、全然古典に通じていない私が、貴ブログに出逢い、
> 二王子の名前は億計(おけ)と弘計(をけ)、現代人の私にはどのように発音し、どのように聞き分けたのか知りたいところですが、……
とあるのを拝見し、高校1年の時に作った短歌を思い出したのです。
実は、私は誰でも「お」と「を」の発音は区別をしていると思っていたので、ある時、クラスでそのことをいったところ、女生徒の一人から、「まあ、あきれた」といわれました。
そのことがきっかけとなり、私は、「安からぬ心に遠く海鳴りを聞きつつ思う夜更けて君を」という歌を作って、一回きりですが、地方紙の土屋文明撰の歌壇に投稿し掲載されました。