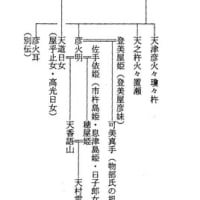秦河勝が自らを毘沙門天になぞらえている説話は河勝の子孫と伝えられている世阿弥が著した
『風姿花伝』や仏教の受容を巡って崇仏派(蘇我氏や厩戸皇子等)と排仏派(物部守屋等)の
烈しい戦いをしたというその場所に建てられた「大聖勝軍寺」の縁起によっている。この丁未
の乱の後、戦勝した聖徳太子は誓願通り四天王寺を難波に建てている。それから約200年後
(794年)桓武天皇によって奈良から山背の葛野へ都が遷される。
新しい都となった山背は渡来氏族の秦氏が入植、開墾し財政的にも豊かな秦氏の拠点だったと
思われ、8世紀末にはすでに上賀茂、下鴨神社、松尾神社、広隆寺、八坂神社、伏見稲荷神社
西芳寺、鞍馬寺、比叡山延暦寺等が建てられていたが、平安京が成立してからは、内裏の南面
に羅城門、東寺と西寺ふたつの護国寺が建てられるが、秦氏の開山した寺々には都となる前か
ら毘沙門天像が安置されており、遷都後には内裏南面の羅城門上、平安京の鬼門に当たる比叡
山延暦寺、北方守護の鞍馬寺には兜跋毘沙門天像が祀られるようになった。東方の清水寺では
蝦夷征伐した征夷大将軍・坂上田村麻呂は毘沙門天の化身と讃えられている。
寺には当然ながら他の仏像も祀られているので誰も秦氏と毘沙門天の関係を問題視していない
ようですが、秦河勝の時代から200年も経過している時に秦氏が毘沙門天を守護神とする謂
れを探したいと思いました。
平安京と秦河勝が深く関わっている興味深い伝承があります。
『拾芥抄』引くところの『天歴(平安中期・村上天皇の元号)御記』によると、「今の平安
京の大内裏はもと秦河勝の邸宅の跡である。また紫宸殿の階の前の橘の木は元河勝の屋敷に
あったもので旧跡によってこれを植えたもの。」とし、右近の橘の由来が秦河勝と結びつい
ている。
また、秦氏の氏寺である広隆寺について
「旧広隆寺(蜂岡寺、野寺)は平安京と隣接していたという事実があり、平安京域と秦氏と
の関わりの深さは歴然であろう。」と井上満郎著『平安京と渡来人』では述べている。
秦氏がその造営に深く関わっていたと思われる平安京の大内裏がもと河勝の屋敷跡という伝承
は以前から知っていましたが、紫宸殿の階段の前にある「右近の橘・左近の桜」の<橘>が河
勝宅に植えられていたものがそのまま移植されたものとは知らなかったので<橘>が秦氏の謎
解きのヒントとして重要な役割を担っていると思いました。なぜなら橘は<秋の七草>に始ま
る暗号解読でもキーワードとして登場していました。
私のブログのテーマは『万葉集』巻八山上憶良詠「秋の七草」の花の名に律令国家・日本誕生
に関わった民族または国の名を託した暗号歌であると考え、その謎解きから出発しました。
「秋の七草」の中で最後の「朝顔」を推理した過程で<橘>がキーワードではないかと思った
のです。大分昔の事なので、その推理過程を要約します。
ブログ「古代からの暗号・秋の七草・朝顔」から
①朝顔を中国では「牽牛子(ケニゴシ)」と言い種を薬用としていた。
牽牛(けんぎゅう)は七夕の星=鷲座の主星・アルタイル=中国名・牛郎=日本名・彦星
・犬飼星と呼んでいる事から<県犬飼橘三千代>を連想した。
②朝顔の語感から朝は朝廷をイメージし、朝廷の顔の意味ではないかと考えた。、奈良朝廷
の顔といえば藤原不比等とその妻の三千代。三千代は宮廷の女官として活躍した功績が認
められ、元明天皇から<橘>の姓を賜ったと『続日本紀』に記されている。
ブログ「古代からの暗号・古今伝授の三木三鳥・下がり苔」から
①朝顔に対応するものは下がり苔と考えた。「下がり」は藤原氏の藤を連想し、「下がり
後家」か「下がり五家」ではと思った。県犬飼橘三千代の前夫は美努王。不比等に嫁した
三千代を「お下がりの後家」とした可能性がある。
また不比等の息子は南家、北家、式家、京家の四家に分かれるが三千代の前夫との子が
<橘>を名乗るので藤家の五家目となり「下がり五家」と考えた。
②『日本書紀』垂仁天皇条では常世国に遣わされた田道間守が持ち帰った非時香果(ときじく
のかくのみ)を<橘>としている。
③『日本書紀』皇極天皇条には橘の樹になるという蚕に似た虫を常世神として祭れば「貧し
き人は富をなし老いたる人は若返る」と人々を惑わせた大生部多を秦河勝が打ちこらした
という常世神事件を伝えている。
垂仁紀の田道間守が常世国から持ち帰った非時香果は橘としており、橘と常世の結びつきをはっ
きりと示していますが、常世国の場所が何処かを類推させる田道間守のセリフがあります。
「命(おほみこと)を天朝(みかど)に受(うけたまは)りて、遠くより絶域(はるかなるくに)
に往(まか)る。万里浪を踏みて、遥かに弱水(よわのみづ)を渡る。この常世国は、仙人
(ひじり)の秘区(かくれたるくに)、俗のいたらむ所にあらず。ここを以て、往来(ゆきか
ふ)間に、自からに十年に経(な)りぬ。豈期(あにおも)ひきや、独峻(ひとりたか)き浪
を凌ぎて、更本土(またもとのくに向(まうでこ)むといふことを。然(しか)るに聖帝の神
霊に頼りて、わずかに還り来(まうく)ること得たり。後略」
弱水とは
玄中記に「天下之弱者、有2 崑崙之弱水1、・・・・」
史記に 「弱水在2 大泰西1」
漢書に 「弱水、謂2 西域絶遠之水1,乗2 玉車1 以度者」
等とみえ、位置は定かではないが弱水を渡って常世に至ったと述べ、西域を思わせる表現をしてい
る。
橘姓は708年元明天皇即位の大嘗祭の折に天武朝以来後宮に仕えた功績を認められて県犬飼橘三千代
と名乗る事を許されるが、橘は聖徳太子周辺に特に多くみられる。
*聖徳太子の誕生地と伝わる<橘寺>
*父の<橘豊日天皇(用明天皇)>
*聖徳太子の妃のひとりで推古天皇の孫である<橘大郎女>

彼女は穴穂部間人皇女と聖徳太子の死を悼み<天寿国繡帳>を作らせていますが、その制作者は
東漢氏、高麗人、漢人が下絵を描き、監督官は椋部・秦久麻であり秦氏が差配しています。

この繡帳の女性の着衣とホータンで発掘された寺院の残存壁画の供養者像の着衣がほぼ同じスタイル
である事をみつけました。。(2014年6月19日謎解き詠花鳥和歌ー48 天武天皇の褶禁止令)

また(2014年7月24日藤と雲雀ー50 西域とつながる板絵、法隆寺金堂消失壁画)のブログ中に天
寿国繡帳のみに見られ、わが国では実体不明の<天寿国>の文字が書かれている書が敦煌写本にあり
ました。ただこれの紹介者・玲児氏は<无寿国>ではと指摘されております。
もうひとつ、秋の七草の<朝顔>から秦氏の名前を導きだすことが出来る考えが浮かびました。中世
に流行した、<謎々>の題<朝顔>にたいする解が<朝つ間>。花の咲くのが<朝の間>というトン
チですが、<朝つ間>は<朝津間>に通じ渡来氏族の秦氏が最初に居住した地名と伝えられています。
『新撰姓氏録』の秦忌寸条(山城国諸蕃)には
太秦公宿祢と同じき祖、秦始皇帝の後なり。功智王、弓月王、誉田(応神)天皇の14年に来朝り
て、表を上り、更、国に帰りて百二十県の伯姓を率て帰化り、また金銀玉帛種々の宝物を献き。天皇
めでたまひて、大和の朝津間の掖上の地を賜ひて居らしめたまひき。
と記しています。
万葉集の秋の七草の朝顔と古今伝授・三木三鳥の下がり苔から導きだせたものは<橘>。橘から<秦
氏><秦氏の仕えた上宮王家><天寿国><常世(常世虫・常世神)><西域><ホータン>へと誘
導されてきました。
さらに当ブログでは聖徳太子と西域のホータン(于闐・和田)につながる数々のものを紹介してきま
した。そして秦河勝自身を毘沙門天になぞらえよというメッセージが発せられていると考える事によ
ってこの謎解きは完結しそうです。続きは次回に
『風姿花伝』や仏教の受容を巡って崇仏派(蘇我氏や厩戸皇子等)と排仏派(物部守屋等)の
烈しい戦いをしたというその場所に建てられた「大聖勝軍寺」の縁起によっている。この丁未
の乱の後、戦勝した聖徳太子は誓願通り四天王寺を難波に建てている。それから約200年後
(794年)桓武天皇によって奈良から山背の葛野へ都が遷される。
新しい都となった山背は渡来氏族の秦氏が入植、開墾し財政的にも豊かな秦氏の拠点だったと
思われ、8世紀末にはすでに上賀茂、下鴨神社、松尾神社、広隆寺、八坂神社、伏見稲荷神社
西芳寺、鞍馬寺、比叡山延暦寺等が建てられていたが、平安京が成立してからは、内裏の南面
に羅城門、東寺と西寺ふたつの護国寺が建てられるが、秦氏の開山した寺々には都となる前か
ら毘沙門天像が安置されており、遷都後には内裏南面の羅城門上、平安京の鬼門に当たる比叡
山延暦寺、北方守護の鞍馬寺には兜跋毘沙門天像が祀られるようになった。東方の清水寺では
蝦夷征伐した征夷大将軍・坂上田村麻呂は毘沙門天の化身と讃えられている。
寺には当然ながら他の仏像も祀られているので誰も秦氏と毘沙門天の関係を問題視していない
ようですが、秦河勝の時代から200年も経過している時に秦氏が毘沙門天を守護神とする謂
れを探したいと思いました。
平安京と秦河勝が深く関わっている興味深い伝承があります。
『拾芥抄』引くところの『天歴(平安中期・村上天皇の元号)御記』によると、「今の平安
京の大内裏はもと秦河勝の邸宅の跡である。また紫宸殿の階の前の橘の木は元河勝の屋敷に
あったもので旧跡によってこれを植えたもの。」とし、右近の橘の由来が秦河勝と結びつい
ている。
また、秦氏の氏寺である広隆寺について
「旧広隆寺(蜂岡寺、野寺)は平安京と隣接していたという事実があり、平安京域と秦氏と
の関わりの深さは歴然であろう。」と井上満郎著『平安京と渡来人』では述べている。
秦氏がその造営に深く関わっていたと思われる平安京の大内裏がもと河勝の屋敷跡という伝承
は以前から知っていましたが、紫宸殿の階段の前にある「右近の橘・左近の桜」の<橘>が河
勝宅に植えられていたものがそのまま移植されたものとは知らなかったので<橘>が秦氏の謎
解きのヒントとして重要な役割を担っていると思いました。なぜなら橘は<秋の七草>に始ま
る暗号解読でもキーワードとして登場していました。
私のブログのテーマは『万葉集』巻八山上憶良詠「秋の七草」の花の名に律令国家・日本誕生
に関わった民族または国の名を託した暗号歌であると考え、その謎解きから出発しました。
「秋の七草」の中で最後の「朝顔」を推理した過程で<橘>がキーワードではないかと思った
のです。大分昔の事なので、その推理過程を要約します。
ブログ「古代からの暗号・秋の七草・朝顔」から
①朝顔を中国では「牽牛子(ケニゴシ)」と言い種を薬用としていた。
牽牛(けんぎゅう)は七夕の星=鷲座の主星・アルタイル=中国名・牛郎=日本名・彦星
・犬飼星と呼んでいる事から<県犬飼橘三千代>を連想した。
②朝顔の語感から朝は朝廷をイメージし、朝廷の顔の意味ではないかと考えた。、奈良朝廷
の顔といえば藤原不比等とその妻の三千代。三千代は宮廷の女官として活躍した功績が認
められ、元明天皇から<橘>の姓を賜ったと『続日本紀』に記されている。
ブログ「古代からの暗号・古今伝授の三木三鳥・下がり苔」から
①朝顔に対応するものは下がり苔と考えた。「下がり」は藤原氏の藤を連想し、「下がり
後家」か「下がり五家」ではと思った。県犬飼橘三千代の前夫は美努王。不比等に嫁した
三千代を「お下がりの後家」とした可能性がある。
また不比等の息子は南家、北家、式家、京家の四家に分かれるが三千代の前夫との子が
<橘>を名乗るので藤家の五家目となり「下がり五家」と考えた。
②『日本書紀』垂仁天皇条では常世国に遣わされた田道間守が持ち帰った非時香果(ときじく
のかくのみ)を<橘>としている。
③『日本書紀』皇極天皇条には橘の樹になるという蚕に似た虫を常世神として祭れば「貧し
き人は富をなし老いたる人は若返る」と人々を惑わせた大生部多を秦河勝が打ちこらした
という常世神事件を伝えている。
垂仁紀の田道間守が常世国から持ち帰った非時香果は橘としており、橘と常世の結びつきをはっ
きりと示していますが、常世国の場所が何処かを類推させる田道間守のセリフがあります。
「命(おほみこと)を天朝(みかど)に受(うけたまは)りて、遠くより絶域(はるかなるくに)
に往(まか)る。万里浪を踏みて、遥かに弱水(よわのみづ)を渡る。この常世国は、仙人
(ひじり)の秘区(かくれたるくに)、俗のいたらむ所にあらず。ここを以て、往来(ゆきか
ふ)間に、自からに十年に経(な)りぬ。豈期(あにおも)ひきや、独峻(ひとりたか)き浪
を凌ぎて、更本土(またもとのくに向(まうでこ)むといふことを。然(しか)るに聖帝の神
霊に頼りて、わずかに還り来(まうく)ること得たり。後略」
弱水とは
玄中記に「天下之弱者、有2 崑崙之弱水1、・・・・」
史記に 「弱水在2 大泰西1」
漢書に 「弱水、謂2 西域絶遠之水1,乗2 玉車1 以度者」
等とみえ、位置は定かではないが弱水を渡って常世に至ったと述べ、西域を思わせる表現をしてい
る。
橘姓は708年元明天皇即位の大嘗祭の折に天武朝以来後宮に仕えた功績を認められて県犬飼橘三千代
と名乗る事を許されるが、橘は聖徳太子周辺に特に多くみられる。
*聖徳太子の誕生地と伝わる<橘寺>
*父の<橘豊日天皇(用明天皇)>
*聖徳太子の妃のひとりで推古天皇の孫である<橘大郎女>

彼女は穴穂部間人皇女と聖徳太子の死を悼み<天寿国繡帳>を作らせていますが、その制作者は
東漢氏、高麗人、漢人が下絵を描き、監督官は椋部・秦久麻であり秦氏が差配しています。

この繡帳の女性の着衣とホータンで発掘された寺院の残存壁画の供養者像の着衣がほぼ同じスタイル
である事をみつけました。。(2014年6月19日謎解き詠花鳥和歌ー48 天武天皇の褶禁止令)

また(2014年7月24日藤と雲雀ー50 西域とつながる板絵、法隆寺金堂消失壁画)のブログ中に天
寿国繡帳のみに見られ、わが国では実体不明の<天寿国>の文字が書かれている書が敦煌写本にあり
ました。ただこれの紹介者・玲児氏は<无寿国>ではと指摘されております。
もうひとつ、秋の七草の<朝顔>から秦氏の名前を導きだすことが出来る考えが浮かびました。中世
に流行した、<謎々>の題<朝顔>にたいする解が<朝つ間>。花の咲くのが<朝の間>というトン
チですが、<朝つ間>は<朝津間>に通じ渡来氏族の秦氏が最初に居住した地名と伝えられています。
『新撰姓氏録』の秦忌寸条(山城国諸蕃)には
太秦公宿祢と同じき祖、秦始皇帝の後なり。功智王、弓月王、誉田(応神)天皇の14年に来朝り
て、表を上り、更、国に帰りて百二十県の伯姓を率て帰化り、また金銀玉帛種々の宝物を献き。天皇
めでたまひて、大和の朝津間の掖上の地を賜ひて居らしめたまひき。
と記しています。
万葉集の秋の七草の朝顔と古今伝授・三木三鳥の下がり苔から導きだせたものは<橘>。橘から<秦
氏><秦氏の仕えた上宮王家><天寿国><常世(常世虫・常世神)><西域><ホータン>へと誘
導されてきました。
さらに当ブログでは聖徳太子と西域のホータン(于闐・和田)につながる数々のものを紹介してきま
した。そして秦河勝自身を毘沙門天になぞらえよというメッセージが発せられていると考える事によ
ってこの謎解きは完結しそうです。続きは次回に