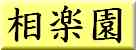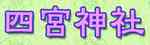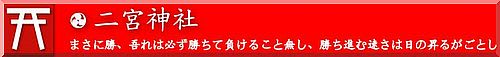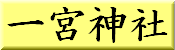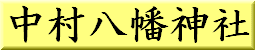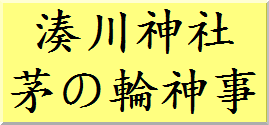本願寺神戸別院(モダン寺)
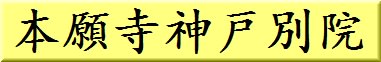
(ほんがんじ こうべべついん)
神戸市中央区下山手通8-1-1
通 称
モダン寺

JR神戸駅と元町駅の中間に立つ「モダン寺」。車窓からも望むことが出来ます。
〔宗派〕
浄土真宗本願寺派
〔御本尊〕
阿弥陀如来像
(あみだにょらいぞう)
JR神戸駅と元町駅のちょうど中間にある花隈は、戦国時代には織田信長公旗下の武将・荒木村重公が城主を務めた花隈城が建てられていた場所でもあります。この地下には阪急電車の花隈駅(正確には神戸高速鉄道の駅舎)があり、東出口を出ると花隈城址へと至りますが、反対側の西出口を出て少し歩くと、エスニックな雰囲気の美しい建物が異彩を放って建っている事に気付きます。ここは特徴ある外観から「モダン寺」と呼ばれて市民に親しまれている寺院で、正式名称を「本願寺神戸別院」といいます。

以前のモダンなイメージを生かしつつ1995(平成7)年に改築された美しい本堂。
天正年間(1573~1592年)、本願寺の第11代門主・顕如上人に帰依して「教祐」という法号を賜った甲斐国の武田信久公が摂津国八部郡二ツ茶屋村に寺舎を営みます。小庵だったこの寺舎は1639(寛永16)年に入り二ツ茶屋村市場の地に道場を建立、第13代門主・良如上人から寺号を授与され、「善福寺」と名付けられる事となりました。この寺院が本願寺神戸別院の前身となったといわれています。その後、この辺りに鉄道が敷設されることになって1871(明治4)年に現在地へと移されました。さらに1908(明治41)年には本願寺の執行長で後に貴族院議員にもなった大谷尊由上人を住職に迎え、別格別院善福寺となりました。
元々は木造寺院でしたが、1917(大正6)年1月に発生した火事によって本堂が全焼したため、我が国の寺院では最初となる鉄筋コンクリートでの本堂再建が進められました。1930(昭和5)年10月に完成した建物はインド仏教様式の美しく斬新なデザインだったために大きな話題を呼び、「モダン寺」という呼び名で信徒の方々のみならず多くの人々に親しまれる事となりました。1960(昭和35)年8月には西本願寺直属の別院となり、寺号も「本願寺神戸別院」と改められます。年月を経て老朽化が進んだ本堂は全面改築される事になり、それまでのモダン寺の印象を残す形で阪神・淡路大震災後の1995(平成7)年9月に竣工し、最大400名が収容できる本堂や600名まで収容できるホール、宿泊なども可能な28畳と26畳の書院などを備えた建物として生まれ変わりました。

本堂前の広場に立てられている親鸞聖人の銅像。
アクセス
・神戸高速鉄道「花隈駅」下車、西へ徒歩1分。
・神戸高速鉄道「西元町駅」下車、北へ徒歩3分。
・JR神戸線「神戸駅」下車、東へ徒歩10分。
・JR神戸線「元町駅」下車、西へ徒歩10分。
 本願寺神戸別院(モダン寺)地図 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
本願寺神戸別院(モダン寺)地図 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・境内無料
拝観時間
・9時~16時30分
公式サイト












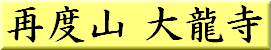


















 」
」