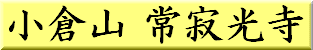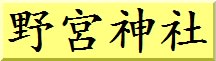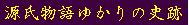衣笠山 地蔵院

(きぬがさざん じぞういん)
京都市西京区山田北の町23
通 称
竹の寺

衣笠山の山麓、閑静な住宅街の奥に静かに佇む地蔵院。
〔宗派〕
臨済宗
〔御本尊〕
地蔵菩薩像
(じぞうぼさつぞう)
「苔寺」の呼び名で有名な西芳寺の周辺には、緑豊かな境内を持つ古刹が点在しています。そんな寺院のひとつ、西京の衣笠山麓にある古刹・地蔵院は、小鳥のさえずりや風に鳴る竹林の音に包まれ、町なかの喧騒から解き放たれて自然の息吹を感じることの出来る静かな別世界。新三十六歌仙にも選ばれた鎌倉時代前期の歌人・衣笠内大臣藤原家良卿もこの地を愛し、山荘を営んだといわれています。
地蔵院は、後小松天皇の後落胤といわれ、TVアニメ「一休さん」のモデルになったことでも有名な反骨・風狂の禅僧・一休宗純が、6歳で京都・安国寺に入って仏門修行の道を歩むまでの幼少期を過ごした場所としても知られています。


竹林と苔庭に包まれた参道(左)と、その奥に建てられた本堂・地蔵堂(右)。
地蔵院は、室町幕府の管領として第3代将軍・足利義満公の補佐役を務め、和歌にも才を発揮するなど文武両道に優れた名将・細川頼之公が1367(貞治6)年に創建した寺院です。名僧・夢窓疎石国師に帰依していた細川頼之公は、地蔵院の創建にあたってはその高弟の碧潭周皎(宗鏡禅師)を迎えましたが、宗鏡禅師は既に1351(観応2)年に入寂されていた恩師・夢窓疎石国師に開山の名誉を譲り、みずからは第2世となって伽藍の充実に尽力しました。
創建以降、地蔵院は北朝の光厳天皇・光明天皇・崇光天皇・後光厳天皇・後円融天皇の勅願寺に準じられて栄え、17万㎡(甲子園球場の約13倍)にも及ぶ広大な境内と25の末寺、そして全国各地に54もの寺領をもつ大禅刹として隆盛を極めましたが、京都全域を舞台に繰り広げられた応仁の乱の兵火に巻き込まれたために伽藍は灰燼に帰してしまいました。


本堂の手前に立つ細川頼之公の碑(左)と、本堂の左奥にある墓所(右)。
墓所には細川頼之公と宗鏡禅師が弔われています。
その後の地蔵院は往時の面影を失い、江戸時代にはわずかに子院である竜済軒と延慶軒を遺すのみという寂しい状態でしたが、細川家の支援などによって第14世住持の古霊和尚が再建を進め、1704(宝永元)年にようやく境内伽藍が整えられました。
1935(昭和10)年に再建された本堂・地蔵堂には、伝教大師最澄の作といわれる延命安産の御本尊の地蔵菩薩像を中心に、左に細川頼之公、右に夢窓国師と宗鏡禅師の木像が安置されており、1686(貞享3)年に建てられた方丈の前には細川頼之公がこよなく愛したといわれる「十六羅漢の庭」が広がっています。宗鏡禅師が作庭したという説もありますが、実際に誰がいつ作ったのかは分かっていません。しかしながら、植栽に溢れ、散りばめられて屹立する石組み見事な庭に相対していると、思わず時の経つのを忘れ、自らも羅漢とともに悟りを求めて瞑想する思いに引き込まれてしまいます。


本堂の右手に立つ開福稲荷大明神(左)と、庭園へと続く参道(右)。

植栽に包まれた「十六羅漢の庭」。3月には美しい椿を愉しむことが出来ます。
アクセス
・阪急電車嵐山線「上桂駅」下車、西へ徒歩12分
 地蔵院地図 【境内図】 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
地蔵院地図 【境内図】 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・大人:400円、小人:200円
拝観時間
・9時~17時











































 臨在禅・黄檗禅公式サイト 天龍寺
臨在禅・黄檗禅公式サイト 天龍寺