
豊国神社

(ほうこくじんじゃ)
滋賀県長浜市南呉服町6-37
近江長浜6瓢箪巡り霊場・第1番札所

豊国神社の鳥居。脇には「豊國神社」と「長浜恵比須宮」の碑が立っています。
〔御祭神〕
事代主大神
(ことしろぬしのみこと)
豊臣秀吉公
(とよとみひでよし)
加藤清正公
(かとうきよまさ)
木村重成公
(きむらしげなり)
卑賤の身からその才智と強運で立身出世し、ついには天下人となった戦国時代の英雄・豊臣秀吉公。その人気は死後も衰えることはなく、「豊国大明神」と神格化されて各地に威徳を称える神社が建てられました。聚楽第を建てて政務を執るなど馴染みの深かった京都をはじめ、豊臣秀吉公と親交の厚かった前田利家公が治めた加賀国や天下の巨城・大坂城など、ゆかりの場所に建てられた神社は「豊国神社」の名で人々の厚い崇敬を集めていますが、浅井長政公攻略の功によって織田信長公より初めて領国を与えられた記念すべき土地である近江国・長浜にも豊国神社が建立されています


江戸時代中期の建立といわれる豊国神社の社殿(左)と、出世稲荷神社(右)。
豊臣秀吉公の3回忌を迎えた1600(慶長5)年、京都ではその遺徳を偲ぶために豊国社が建立され、前年に後陽成天皇から正一位の神階と「豊国大明神」という神号を贈られて神となった豊臣秀吉公が御祭神として祀られることとなりました。それに合わせて長浜でも神社が創建され、京都のものと同じく豊国社と名付けられました。これが豊国神社の始まりです。しかし、1615(元和元)年の大坂夏の陣によって豊臣秀頼公が自決して豊臣家が滅亡した後、すでに江戸幕府を開いて全国統治を推し進めていた徳川家康公は豊臣秀吉公の遺徳の象徴として人心の集まるところであった豊国社に対して不快感をあらわにし、存続を認めずに破却することで太閤信仰を徹底的に排除しようとしました。


豊臣秀吉公が愛したといわれる「虎石」(左)と、境内に立つ天満宮(右)。
しかし人々の豊臣秀吉公への追慕の念は根強く、徳川政権への反発もあって御祭神は破却される前に密かに運び出され、しばらく町年寄の家に祀られることとなります。そして、1792(寛政2)年に長浜八幡宮の御旅所が出来たのを契機にその敷地の片隅にお堂を建て、翌年になって長浜八幡宮の恵比須命を勧請して「恵比須宮」としました。人々は、商売の神様である恵比須命を祀るということを方便にして、実際は奥社に豊臣秀吉公の御神像を安置して密かに御霊への祭祀を続けようとしたのです。こういう経緯があるため、恵比須命と同一神とされる事代主命が今もなお御祭神として祀られています。
江戸幕府が倒れて徳川の世が終わり、明治新政府が発足すると恵比須宮は「豊神社(みのりじんじゃ)」と名を変え、1892(明治25)年には現在の鎮座地に移転されました。そして1898(明治31)年の豊臣秀吉公300回忌の際には社殿が造営されて現在の姿となり、1920(大正9)年には晴れて「豊国」の名が復活し豊国神社と呼ばれるようになりました。


福万年亀といわれる石と瓢箪池があります。


加藤清正公像(左)と、長浜開町を祝って竹中半兵衛が歌った詩文を刻む石碑(右)。
「君が代も わが代も共に 長濱の 真砂のか須の つき屋らぬまで」
アクセス
・JR北陸本線「長浜駅」下車、北へ徒歩3分。
 豊国神社地図 【境内MAP】 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
豊国神社地図 【境内MAP】 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・境内無料
拝観時間
・常時開放
 | 近江の城下町を歩く (近江旅の本)淡海文化を育てる会サンライズ出版このアイテムの詳細を見る |















































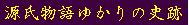




















































 公式サイト
公式サイト

 本家鶴喜そば本店
本家鶴喜そば本店


