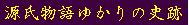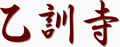雨宝山 放生院 常光寺

(うほうざん ほうじょういん じょうこうじ)
京都府宇治市宇治東内11
通 称
橋 寺

〔宗派〕
真言律宗
〔御本尊〕
地蔵菩薩像
(じぞうぼさつぞう)
古代より、北陸道から奈良・平城京を繋ぐ道として多くの旅人たちを見守ってきた奈良街道。宇治川に架かる宇治橋は、宇治を抜ける奈良街道を繋ぐ交通の要衝として重要な役割を果たしてきました。その宇治橋の東、京阪電車「京阪宇治駅」から歩いてすぐのところに、「宇治橋の守り寺」として人々の崇敬を集めてきた寺院があります。正式名称を「雨宝山放生院常光寺」というこの寺院は、通称「橋寺」もしくは「橋寺放生院」という名で広く親しまれている真言律宗の寺院です。

1631(寛永8)年の火災ののち再建されたといわれる本堂。
橋寺の創建に関しては2つの説が伝えられています。ひとつは、優秀なブレーンとして聖徳太子から厚い信頼を寄せられていた秦河勝が、604(推古天皇12)年に聖徳太子の念持仏である地蔵菩薩像を祀る寺院として宇治川のほとりに建てた常光寺地蔵院が橋寺の前身だという説。もうひとつは、646(大化2)年に大和国・元興寺(当時は法興寺と呼ばれていた)の僧侶・道登上人が初めてこの地に宇治橋を架けた際、工事の安全祈願のために川の傍に立っていた地蔵院の建物を造り替えたのを創建とする説です。
当時は治水技術などもまだまだ十分なものではなく、大雨などのたびに激しい洪水に見舞われて何度も橋が流されるなどの被害が続き、宇治川のほとりにあった地蔵院も徐々に衰退していきました。そんな地蔵院の再興を行ったのが、鎌倉時代後期の真言律宗の高僧・叡尊上人です。大和国・西大寺の僧侶だった叡尊上人は、地蔵院の本尊・地蔵菩薩像が激しく損傷していたことに心を痛め、1281(弘安4)年に新たに大きな地蔵菩薩像を造り、傷ついていたそれまでの地蔵菩薩像をその胎内に納めて地蔵院を再興しました。
さらに叡尊上人は、1286(弘安9)年に行われた宇治橋の再建に際し、宇治川の氾濫などで命を落とした人馬・魚介類などすべての菩提を弔うため、中州にある浮島に高さ約15mの巨大な十三重石塔を建立して供養のための盛大な放生会を営みました。このことに因んで地蔵院のことを「放生院」と呼ぶようになり、さらに叡尊上人の慈悲に溢れた思いに感銘を受けた後宇多天皇によって300石の寺領を与えられ、宇治橋や十三重石塔の管理を一任されたことから、「橋寺」とも呼ばれるようになりました。


国の重要文化財に指定されている宇治橋断碑(左)と、境内に立つ橋掛け観音像(右)。
境内には、瀬田川に架かる「瀬田の唐橋」、淀川を跨いで架けられていた「山崎橋」と並び、「日本三古橋」の一つである宇治橋の創建当時の経緯を刻んだ宇治橋断碑が立っています。天平時代に造られたといわれている宇治橋断碑は、もともと宇治橋の傍に立てられていたそうですが、宇治川の氾濫などでいつしか地中に埋没していました。この碑が境内の地中から発見されたのは、1791(寛政3)年のことでした。残念ながら、上の1/3の部分しか見つかりませんでしたが、鎌倉時代に記された史書「帝王編年記」にあった原文をもとに復元が行われ、1793(寛政5)年に現在の姿に修復されました。
碑文には「名は道登と曰う。山尻恵満の家より出づ。大化2年丙午の歳、此の橋を構立す」と刻まれてあり、宇治橋が646(大化2)年に架けられていたことが分かります。この宇治橋断碑は、群馬県で発見された「多胡碑(たこのひ)」、宮城県で発見された「多賀城碑」とともに日本三古碑の一つといわれ、国の重要文化財に指定されたことから木造の覆屋の中に納められて保護されています。


石段を登った正面にある十二支守本尊像(左)と、近年建てられた石塔(右)。
アクセス
・京阪電車「京阪宇治駅」下車、南東へ徒歩2分
・JR奈良線「宇治駅」下車、東へ徒歩10分
 橋寺放生院地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
橋寺放生院地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・境内無料(仏像観賞:300円、断碑観賞:200円) ※断碑の公開は3~5月、9~11月のみ
拝観時間
・9時~16時30分(冬季は9時~16時まで)