
小野八幡神社

(おのはちまんじんじゃ)
神戸市中央区八幡通4-1-37

社域のすぐ背後に神戸市役所が見えます。まさに神戸の中心に鎮座する神社です。
〔御祭神〕
応神天皇
(おうじんてんのう)
神戸市役所から少し東にいくと、オフィスビルに囲まれて鎮座する神社があります。そこが小野八幡神社です。社務所に掲げられた表札には「新渡戸」とありました。小野八幡神社の宮司さんは、前の五千円札に描かれていた新渡戸稲造氏の御親戚にあたるのだそうです。宮司の娘さんも小野八幡神社の権禰宜で、日本の神道を世界に広めるべくアメリカの地で活躍されています。鳥居の脇には宮司のお子さんの活躍ぶりが載った記事が誇らしげに掲示してあり、微笑ましいものを感じました。オフィス街という立地、娘さんたちの若い感性もあるのでしょうか、近隣の企業の協力を受けて秋祭に「ギャルみこし」を企画するなど、なかなか面白い神社だという印象を受けます。

交通安全厄除け祈願でも有名な小野八幡神社の社殿。
小野八幡神社は887(仁和3)年に創建されたと伝えられており、9世紀末の寛平年間(889~898年)には神前の七草を宮中に献上したという記録が残されています。それから時代は下って平安末期の源平争乱期のこと。平知盛公率いる平家軍は、神戸を拠点に守りを固めて源範頼公を総大将とする源氏軍を迎え討ちます。平家軍は西は須磨・一の谷の守りを固め、北は夢野に防衛線を張り、そして東から攻め寄る源氏軍に対しては生田川を防衛ラインとして生田の森に拠って堅い守りを固めていました。両軍が対峙する中、武蔵国から参陣した河原太郎高直公と河原次郎盛直公という兄弟が、勇敢にも平家の大軍の中に先陣を切って斬りこみます。これがきっかけで両軍は激突、連動するように各地で戦端が開かれ、有名な「鵯越の逆落とし」によって総崩れになった平家軍は海へと敗走していきます。
平家の滅亡後、勝利のきっかけを作るも敢え無く敵の矢に射られて戦死した河原兄弟の功績を称えた源頼朝公が、2人の菩提を弔うために現在の大丸元町店の北に報恩寺を建立します。そのときに報恩寺の鎮守の神とされたのが小野八幡神社です。「小野八幡神社を報恩寺の鎮守にした」という話と「報恩寺の鎮守とするために小野八幡神社を建てた」という話があるので創建の時期はどれが正しいのか分かりませんが、少なくとも800年以上の歴史を持つ由緒ある神社であることは間違いありません。(大丸北側の地から現在地に遷ったのは戦後になってからです)


社殿左には白玉國高稲荷と巳神社(左)、右には金刀比羅社が鎮座しています(右)。
拝殿の左に建つ白玉國高稲荷の鳥居の傍らに、小さな慰霊碑が建てられています。この慰霊碑は、1945(昭和20)年3月の神戸大空襲で宿直勤務中に殉職した7名の電話交換手の慰霊のために建てられたものです。御幸通にあった神戸中央電話局葺合分局に勤務していた皆さんは、「通信を確保せよ」という軍令を受け、何があっても職務から離れないよう義務付けられていたため、空襲の爆音が鳴り響いて周囲が火の海と化していたにも関わらず、必死に電話を繋ぎ続けて犠牲になったといいます。交換手たちが犠牲になった地に新しいビルが建てられた際に慰霊碑が建立されましたが、阪神淡路大震災のためにそのビルが全壊したために小野八幡神社の境内に移されたそうです。こんな町なかにも、戦争の傷跡はひっそりと残されています。


大空襲で殉職された電話局員の方々の慰霊碑(左)。右は震災で折れた鳥居。
アクセス
・JR「三ノ宮駅」下車、南へ徒歩7分
・阪急電車「三宮駅」下車、南へ徒歩8分
・阪神電車「三宮駅」下車、南へ徒歩7分
・神戸市営地下鉄「三宮・花時計前」下車、南へ徒歩3分
拝観料
・無料
拝観時間
・常時開放
 | 神戸の神社兵庫県神社庁神戸市支部神戸新聞出版センターこのアイテムの詳細を見る |



















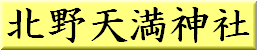







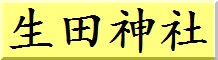













 神戸空港・夜バージョン
神戸空港・夜バージョン






















































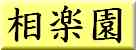















 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』にも同様の内容を投稿させていただきました。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』にも同様の内容を投稿させていただきました。










