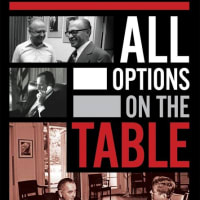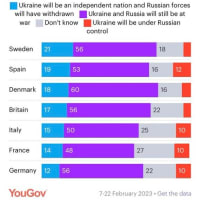マイケル・ウォルツァー(萩原能久監訳)『正しい戦争と不正義な戦争』風行社、2008年を読みました。原著のJust and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 2nd Edition (Basic Books, 1992), 361 pp は、実は、約30年ほど前に、大学院のある授業で指定されたテキストだったため、その時に読了していました。書棚の同書を手に取ってみると、ページのあちこちに当時の書き込みがあり、紙も劣化して茶色がかっており、なんだか懐かしく感じます。Amazonで検索してみたら、私が読んだ原著第2版は、もう取り扱いがないようでした。新しい第5版が購入可能でした。ウォルツァー氏は、同書を改訂するたびに、新しい前書きを追加していますので、第5版では、どのような議論を提供しているのか、気になります。ちなみに、私が持っている第2版では、前書きで、湾岸戦争の正義が論じられていました。

なぜウォルツァー氏の正戦論を再訪したかというと、勤務先での授業で戦争の道義性を扱うコマの予習のためということです。かれのJust and Unjust Wars は360ページ近くある「大著」ですので、いくら既に読んだといっても、再読するのは時間と労力がかかります。それらを出来るだけ節約するために、今回は同書の邦訳を読むことにしました。ただし、訳書も600ページを超えるボリュームであり、しかも、監訳者の荻原氏が「訳者あとがき」で解説するように、ウォルツァー氏は「決疑論」という方法論をとって入り組んだ議論しているために、全体として分かりにくく、読み終えるまでには、かなりの時間がかかりました。
ここで採用されている「決疑論」とは、経験的で実証的な政治学に親しんでいる私のような研究者には、馴染みのある方法ではありません。上述の萩原氏によれば、これは「(倫理や道徳の)ルールの適用にあたって誰からも異論のないような典型的事例から議論をはじめ、徐々に白黒のはっきりしない確定の難しい臨界事例にたいして、類推をもとに論をすすめていく」(「訳者あとがき」604ページ)方法です。こうした方法に依拠して展開される議論を理解するのは、私にとって、かなり大変な作業でした。
ウォルツァー氏は、道徳的に正当な戦争を擁護する「正戦論」を主張する第一人者の1人とみなされています。かれの学問的立ち位置は、「国家中心的道義主義者」あるいは「コミュニタリアン(共同体論者)」とされています。前者は、国際政治を主権国家から成る社会の営みと捉え、そこには一定の規則が存在すると考える立場をとります(ジョセフ・ナイ、デイヴィッド・ウェルチ、田中明彦・村田晃嗣訳『国際紛争』有斐閣、2017年、42ページ)。後者は、共同体としての国家がもつ価値を重視する立ち位置をとります。
そして、ウォルツァー氏は、こうした道義的基盤から、戦争の正義と不正義を緻密かつ例証的に論じています。正戦論は、「戦争への正義」を規定するユス・アド・ベルム(「開戦法規」とも訳されます)と「戦争における正義」を定めるユス・イン・ベロ(「交戦法規」とも訳されます)からなります。これらを簡潔に説明すれば、前者は、主権国家が持つ不可侵の権利を侵害する「侵略」は「犯罪」にほかならないので、これに対して軍事力を使って自衛することは、「正義の戦争」であり正当なものであるということです。後者は、戦争において(それがたとえ自衛のための正当な戦争であっても)、「無辜の市民」を攻撃してはならないと説きます。こうした道徳的規準にしたがい、かれは歴史の諸事例をひきながら、重厚で濃密な議論を展開しています。
ここでウォルツァー氏の議論を要約するには、あまりにスペースが少ないので、上記書を読んで私が印象に残ったことを数点だけ指摘したいと思います。第1に、こうした道義的な正戦論への素朴な疑問は、なぜ、そして何を根拠に、かれのような「政治理論家」の主張が正しいと言えるのかという、根源的なものです。すなわち、道徳論は究極的にはさまざまな立場をとる者たちの果てしない対話ではないか、という懐疑的な問いです。これに対するウォルツァー氏の解答は、実に堂々たるもので、学者としての矜持が感じられます。曰く「私がずっと行ってきているように、権威を持った声になろうと努力し、ある特定の『重み』が自分自身にあると主張しないなら、正義と戦争に関して論じることなどできない」(『正しい戦争と不正な戦争』522ページ)と。おそらく、戦争の道義性を論じる「権威」を自分に認めなければ、このような発言はできないということでしょう。もちろん、ウォルツァー氏は戦争の正義を論じる際には、内省的な自問自答を繰り返しながら、慎重に議論を展開しています。こうしたスタイルは、自分を誇示する「権威主義」とはかけ離れたものであり、また、論じるテーマの性質がさまざまな価値が入り組んだ道徳をめぐるものである以上、不可避なのかもしれません。
第2に、ウォルツァー氏の正戦論をアメリカの「アフガニスタン戦争」に適用した場合、はたして、この戦争は正義なのかどうか、気になりました。主権国家間の戦争を主として論じる正戦論は、「対テロ戦争」という、攻撃対象の根源的な主体が非国家主体であるテロリストに対する武力の行使をどう道徳的に判断するのか、ということです。その答えは、上記書ではなく、かれの別の著作である『戦争を論ずる—正戦のモラル・リアリティ—』駒村圭吾・鈴木正彦・松元雅和訳(風行社、2008年〔原著2004年〕)に見つけることが出来ました(もちろん、『正しい戦争と不正な戦争』でも、テロリズムを扱っています。第12章が、それにあたります)。かれの解答は、以下のように意外なほどストレートでした。
「9.11に責任あるテロリスとネットワークが正確に把握され、その結果タリバン政府が実際にそのパトロンであり保護者であると判明するならば、アフガニスタンでの戦争は確かに正しい戦争である」(『戦争を論ずる』195ページ)。
再度、英書のJust and Unjust Wars をペラペラめくってみると、当時のこのような書き込みが目に留まりました。道徳的立場を整理した4象限のマトリックスにおいて、ウォルツァー氏は、「ルール志向」の「普遍主義者」に位置づけられていました。それから4半世紀以上たった今、『正しい戦争と不正な戦争』を読み直してみると、かれがなぜ、このような学問的位置づけになるのかが、より鮮明に理解できた気がしています。「功利主義的な」実証政治学のリアリスト・アプローチ(リアリズム=「結果志向」の「特定主義(particularist)」)にどっぷり漬かっている私にとって、「『リアリズム』に抗して(Against "Realism")」から始まるウォルツァー氏の『正しい戦争と不正な戦争』は、重いテーマを扱っているものですが、とても新鮮に感じました。

なぜウォルツァー氏の正戦論を再訪したかというと、勤務先での授業で戦争の道義性を扱うコマの予習のためということです。かれのJust and Unjust Wars は360ページ近くある「大著」ですので、いくら既に読んだといっても、再読するのは時間と労力がかかります。それらを出来るだけ節約するために、今回は同書の邦訳を読むことにしました。ただし、訳書も600ページを超えるボリュームであり、しかも、監訳者の荻原氏が「訳者あとがき」で解説するように、ウォルツァー氏は「決疑論」という方法論をとって入り組んだ議論しているために、全体として分かりにくく、読み終えるまでには、かなりの時間がかかりました。
ここで採用されている「決疑論」とは、経験的で実証的な政治学に親しんでいる私のような研究者には、馴染みのある方法ではありません。上述の萩原氏によれば、これは「(倫理や道徳の)ルールの適用にあたって誰からも異論のないような典型的事例から議論をはじめ、徐々に白黒のはっきりしない確定の難しい臨界事例にたいして、類推をもとに論をすすめていく」(「訳者あとがき」604ページ)方法です。こうした方法に依拠して展開される議論を理解するのは、私にとって、かなり大変な作業でした。
ウォルツァー氏は、道徳的に正当な戦争を擁護する「正戦論」を主張する第一人者の1人とみなされています。かれの学問的立ち位置は、「国家中心的道義主義者」あるいは「コミュニタリアン(共同体論者)」とされています。前者は、国際政治を主権国家から成る社会の営みと捉え、そこには一定の規則が存在すると考える立場をとります(ジョセフ・ナイ、デイヴィッド・ウェルチ、田中明彦・村田晃嗣訳『国際紛争』有斐閣、2017年、42ページ)。後者は、共同体としての国家がもつ価値を重視する立ち位置をとります。
そして、ウォルツァー氏は、こうした道義的基盤から、戦争の正義と不正義を緻密かつ例証的に論じています。正戦論は、「戦争への正義」を規定するユス・アド・ベルム(「開戦法規」とも訳されます)と「戦争における正義」を定めるユス・イン・ベロ(「交戦法規」とも訳されます)からなります。これらを簡潔に説明すれば、前者は、主権国家が持つ不可侵の権利を侵害する「侵略」は「犯罪」にほかならないので、これに対して軍事力を使って自衛することは、「正義の戦争」であり正当なものであるということです。後者は、戦争において(それがたとえ自衛のための正当な戦争であっても)、「無辜の市民」を攻撃してはならないと説きます。こうした道徳的規準にしたがい、かれは歴史の諸事例をひきながら、重厚で濃密な議論を展開しています。
ここでウォルツァー氏の議論を要約するには、あまりにスペースが少ないので、上記書を読んで私が印象に残ったことを数点だけ指摘したいと思います。第1に、こうした道義的な正戦論への素朴な疑問は、なぜ、そして何を根拠に、かれのような「政治理論家」の主張が正しいと言えるのかという、根源的なものです。すなわち、道徳論は究極的にはさまざまな立場をとる者たちの果てしない対話ではないか、という懐疑的な問いです。これに対するウォルツァー氏の解答は、実に堂々たるもので、学者としての矜持が感じられます。曰く「私がずっと行ってきているように、権威を持った声になろうと努力し、ある特定の『重み』が自分自身にあると主張しないなら、正義と戦争に関して論じることなどできない」(『正しい戦争と不正な戦争』522ページ)と。おそらく、戦争の道義性を論じる「権威」を自分に認めなければ、このような発言はできないということでしょう。もちろん、ウォルツァー氏は戦争の正義を論じる際には、内省的な自問自答を繰り返しながら、慎重に議論を展開しています。こうしたスタイルは、自分を誇示する「権威主義」とはかけ離れたものであり、また、論じるテーマの性質がさまざまな価値が入り組んだ道徳をめぐるものである以上、不可避なのかもしれません。
第2に、ウォルツァー氏の正戦論をアメリカの「アフガニスタン戦争」に適用した場合、はたして、この戦争は正義なのかどうか、気になりました。主権国家間の戦争を主として論じる正戦論は、「対テロ戦争」という、攻撃対象の根源的な主体が非国家主体であるテロリストに対する武力の行使をどう道徳的に判断するのか、ということです。その答えは、上記書ではなく、かれの別の著作である『戦争を論ずる—正戦のモラル・リアリティ—』駒村圭吾・鈴木正彦・松元雅和訳(風行社、2008年〔原著2004年〕)に見つけることが出来ました(もちろん、『正しい戦争と不正な戦争』でも、テロリズムを扱っています。第12章が、それにあたります)。かれの解答は、以下のように意外なほどストレートでした。
「9.11に責任あるテロリスとネットワークが正確に把握され、その結果タリバン政府が実際にそのパトロンであり保護者であると判明するならば、アフガニスタンでの戦争は確かに正しい戦争である」(『戦争を論ずる』195ページ)。
再度、英書のJust and Unjust Wars をペラペラめくってみると、当時のこのような書き込みが目に留まりました。道徳的立場を整理した4象限のマトリックスにおいて、ウォルツァー氏は、「ルール志向」の「普遍主義者」に位置づけられていました。それから4半世紀以上たった今、『正しい戦争と不正な戦争』を読み直してみると、かれがなぜ、このような学問的位置づけになるのかが、より鮮明に理解できた気がしています。「功利主義的な」実証政治学のリアリスト・アプローチ(リアリズム=「結果志向」の「特定主義(particularist)」)にどっぷり漬かっている私にとって、「『リアリズム』に抗して(Against "Realism")」から始まるウォルツァー氏の『正しい戦争と不正な戦争』は、重いテーマを扱っているものですが、とても新鮮に感じました。