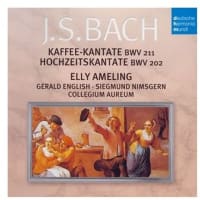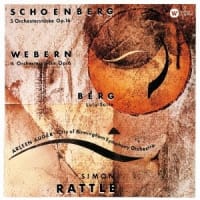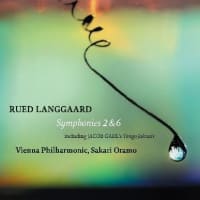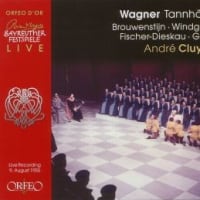しばらく前から気になりだしたフレーズがある。
ブラームスの、それもオーケストラ作品で聴けるモチーフ----あるいは楽想。
そこに潜むのは、心の奥底から湧き出てくる、抑えようとしても抑えきれない「感情」。
基本はリズム(最初の譜例)。このパターンは複数回繰り返され、1つのまとまりとなる。
ブラームスの作品分析において、音の動き(音程)に注目されることが多い。
たとえば2番目の交響曲の冒頭の3音(D-Cis-D)。
ブラームスが範としたベートーヴェンでは、あの「運命」のモチーフ([ン]タタタ・ターン)と
ヴァイオリン協奏曲の冒頭ティンパニの4つのレ(タンタンタンタン)が同じところから
生まれているといわれている。これは音程ではなくリズム面で捉えたもので、これと
同様のことがブラームスにおいてあってもおかしくはない。
ブラームスは、この「パターン」に施す音程の跳躍や、「パターン」に入る前にシンコペーションを組み合わせたりすることで、同じ形から様々な貌---葛藤、あるいは焦燥、憤怒、時には悲哀といったもので、その強度も様々---を描いてみせた。
例えば悲劇的序曲の場合(1880年完成)。
ブラームスが、交響曲2番(1877年)、ヴァイオリン協奏曲(1878年)、哀悼歌(1881年)、交響曲第3番(1883年)など充実した作品群を生み出していたころの作品の1つ。
このモチーフは、ヘ短調からヘ長調、そしてイ短調へとめまぐるしく調が変わる部分に出現するのだが、まさにブラームスの生の声、心の軋み、焦燥感が聴こえてこないだろうか。

同じモチーフを使い、悲劇的序曲と同じような表情は、3番の最終楽章にも感じ取れる。この部分には、大きく上へ跳躍する音程が与えられており、あたかも飛び立とうとするかのようだ。しかし、その飛び立とうという願望は適わない.....
この2例ほどにはパターンが繰り返されないが、大学祝典序曲でもこのモチーフが聴ける。もちろん、前の2曲ほど悲痛な表情はないが。
この曲は、その平明さが魅力だが、書いた本人には、その「明るさ」だけでは
満たされない感情があり、平衡を求めて悲劇的を作ったとすら思える。
もう1つ、このモチーフが生の形で使われている例をあげなければならない。
上の段は音価を変えたもの、下の団が元の音価。つまり交響曲4番の冒頭のテーマだ。この曲を構成する最も重要な、そして1度聴いたら忘れられることができない印象を残すこの部分は、同じパターンから派生していることがわかる。音価は倍となることで、悲劇的序曲のような激しい葛藤そのものではなく、それを通り越して到達した物悲しいさ、諦念といった境地に到達している。
大きな起伏をもった音の動きは、まさにこのパターンを様々な形で試したなかで生まれてきたと予想されるくらいだ。
悲劇的序曲にはリズムの他にもう一つ大きな特徴がある。それは冒頭に響く2つの和音。

その響きの不思議さ。
そしてこの2つの和音が、ソナタ形式のこの曲において展開部、再現部と3回出現するがすべて同じ構成音となっている。
仮にニ短調とした場合、主和音の第1転回形(バスが第3音)そして属和音と思しき和音となる。ただ、普通に属和音とするなら第3音Cisが書き込まれるであろうが、意図的に省略されている。実際にCisが加わった和音は11小節目に出現するのだから、ブラームス(最初の交響曲を作るのに20年以上も時間をかけた人であることを忘れてはならない)が、最初の和音の構成音の選択において、Cisを気まぐれに抜いたとは考えられない。この2つの和音に続く湧き上がるような音型は明らかに平行調のヘ長調のもの。つまり、この不思議な響きを持つ和音は、あえて調をぼかすかのように選択されたと考えるべきなのであろう。このヘ長調のフレーズは、そのまま焦燥のフレーズの構成音としても配置されている(2番目の譜例を参照)。
手元にあるCDから悲劇的序曲をいくつか聴いてみた。
ウィーン・フィル(この曲を初演している)を指揮したベームそしてバルビローリの盤では、6小節目の付点のリズムにおいて共通した表情---やや前のめりに弾かれ、ほのかな明るさえ伴い、そこには意志をもって前へ進もうという気持ちを感じさせる---を持っている。
他の盤(セル、ボールトなど)では荘重なテーマとしてただ重く弾かれるのに対して、ベームそしてバルビローリ盤---ウィーン・フィル盤と書いたほうが正確かもしれない---で聴くこの部分(ほんのわずかな瞬間でしかないが)をそのような表現をすることで、作品をより深いものにしている。
この曲が描く像は、どこかアルベール・カミュが「シーシュポスの神話」で描いた主人公を類推させる。
ドイツ・レクイエムやミサ曲3番で想像をはるかに超える音楽を聴かせてくれたシュナイトさんが、13日の神奈川フィル定期公演で悲劇的序曲のほかに、ブラームスそしてブルックナーの合唱作品を取り上げる。どちらも宗教的な内容をもった作品なのだが、その性格は、全く異なる。どのようなブラームス、ブルックナーが聴けるのだろうか.....