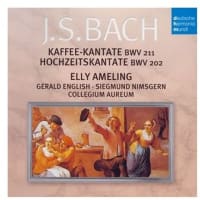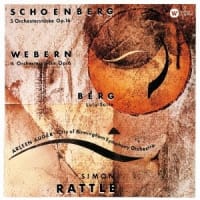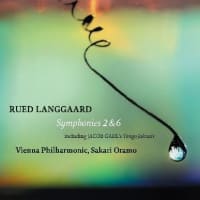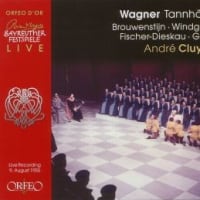年が明けてから届いたCDを聴いて考えたことを書いてみる。
「ああ、日本に帰ってきたのだな、まだこういうことをやっている」と思わずひとりごとをいったのは1980年7月8月とヨーロッパを回って帰国した吉田秀和。
「こういうこと」とはラジオで聴いた日本人演奏家の演奏であり、その音楽は、「音楽家の神経がすみずみまでこまかく行きわたっており、あるふれるばかりの情感に満ちている」ものであったと「犬に食われた話」(「時の流れのなかで」に収録)で書いている。
その対比として
西洋人の演奏をきいて、時々、その理知的で、かわいている行き方に、好き嫌いを越えて、「ああ、ヨーロッパに住んでいる人間の音楽だな」
と考えずにいられなくなった、と続けている。
なかなか含蓄のあるこの文章---読んだのもうはずいぶん前---のことがずっと気になって、というか引っかかり続けていた。
書かれてからすでに30年以上たっているが、「こういうこと」は変わったのだろうか?とあらためて自分なりに問うてみると「変わっていない」と思う。さらに付け加えるならば「あふれるばかりの情感」とはまた別に「説明あるいは解説」を聴かされている演奏もあるといえるのではないか。
レッスンで習った、あるいは指示された弾き方---例えば「ここからクレッシェンドしながら少しずつテンポ上げてゆく」というような---をしっかりと守り、それを忠実に実行する、そんな演奏が。
だからこのような演奏からは、奏者は「何が面白くて」---というと表現としては分かりやすいけど、微妙にずれるので「何がいいたくて」と付け加えておこう----演奏しているのだろうか?まるで曲の説明じゃないか?というような印象を受けることも多い。
前置きが長くなってしまった。
届いたCDは五島史誉さんのピアノによるベートーヴェンの作品集。
これを仕事への往き帰りに5回、それと部分部分を抜き出して数回聴いた。「説明のような演奏」なら通して1回----酷ければ途中で止めてしまう---聴いてお仕舞いとなるのだから、この演奏は「ただもの」ではないのだ。
どちらかといえば少し遅めのテンポ設定だが、演奏には推進力がある。つまり音楽に動きがあり---「説明」タイプにはない---前へ、前へ進もうという意思を感じさせる。
とはいっても、単に弾き飛ばされるというものではなく、むしろ楽句ごとにピアニストが入念に考え抜いた(と思われる)アゴーギク(とデュナーミク)が施される。
例えていうと、車を運転するときのギアの選択するセンスに近いかも----もちろんオートマチックではない。道路、路面の状態を読み取り、それらに対して、どのギアを選択するかにドライバーのセンスと意思が込められる。だから「走っている」といっても、滑らかに走っているのか、あるいはエンジンの回転をタイヤにしっかり伝え、あたかも路面に貼りつくかのような、といった様々な感じが生まれる。
これらが緻密に組み合わされて音楽が構築される。だから、体の芯にズンと響いてくるような、意思的な、存在感をもった音楽として受け止めることになる。
推進力は《熱情》第3楽章の後半のPrestoのところでよくわかるだろう。ここにきてさらに熱を帯びて音楽が突き進むことになるのだが、単にここにきたからPrestoにした、というのではなく、この部分---10小節、それを反復するので20小節分の時間がある----のなかでテンポがさらに加速される。CD付属の解説では「憑依」という言葉が使われているが、音楽がピアニストの意思を越え、さらに別の次元に誘った、まさにその瞬間が記録された、といえるだろう。
《熱情》が終わると《エリーゼのために》が始まる。これもテンポは遅く、4分23秒かけて演奏される。ピアノを習う女の子が弾きたいと憧れる、乙女チックなアンコール・ピースではない《エリーゼ》。
この後、選帝侯ソナタと続く。最初の《熱情》と同じへ短調というところにピアニストの「考え」が伺われる。
淑やかな容姿がCDの写真に使われているが、ピアニストの手はしなやかで強靭そう。
ともあれこれからが楽しみな、そしてコンサートで聴いてみたいと思わせるピアニスト。
L.v. ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調作品 op.57 《熱情》
バガテル《エリーゼのために》
選帝侯ソナタ第2番 ヘ短調 WoO.47
ピアノ:五島 史誉
このCDついてはアリアCDサイトを参照ください。