研修会レポです。
昨日、三木記念ホールで開催された、おかやまスポーツプロモーション研究会(SPOC研究会)のシンポジウムに参加してきました。まずは、今朝の山陽新聞朝刊に「スポーツによる地域活性化探る 岡山でシンポ、事例報告や講演」というタイトルの記事です。以下、抜粋して紹介。

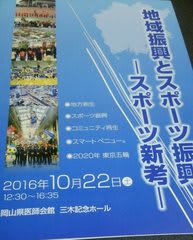
スポーツを生かしたまちづくりについて考えるシンポジウム「地域振興とスポーツ振興―スポーツ新考」(SPOC研究会、山陽新聞社主催)が22日に岡山市内で開催。約100人が参加し、事例報告などを通じてスポーツによる地域活性化の可能性を探った。
「地域に対してスポーツが果たす役割とは何か?」をテーマにしたパネルディスカッションでは、群馬県神流町観光アドバイザーの細谷啓三氏が、過疎高齢化が進む町に活力を生んだトレイルランの大会を紹介。島根県のNPO法人・出雲スポーツ振興21事務局長の矢田栄子氏は、体育施設の管理運営で得た財源でスポーツ教室の開催などに取り組んでいることを説明。本紙で今年1~6月に連載した企画「スポーツ新考 地域戦略を探る」を担当した久万真毅記者は、取材の成果を報告。
コーディネーターである岡山大大学院教育学研究科の高岡講師は「スポーツそのものに即効性があるのではなく、スポーツを起点に住民同士がつながり、意識が変わることで地域が変わる」と総括。細谷、矢田両氏は「自分たちは裏方に回り、多くの住民を頼って巻き込むことが重要」と強調。おかやまスポーツプロモーション研究会の梶谷代表や日本体育・スポーツ経営学会会長の柳沢和雄筑波大教授による講演も開催。シンポは県内の産学官民の有志でつくる同研究会の発足2周年記念事業。
山陽新聞該当記事:http://www.sanyonews.jp/article/435455/1/?rct=okayama_sports
三木記念ホールという事で、名前で検索して出た地図を元に岡山衛生会館へ行ってみるが、県民局の工事中のビルしかなく、こりゃおかしいと再度細かく調べてみると、岡山県医師会の方の三木記念ホールで西口でした。大幅な移動ロスで、少し遅刻して会場入り。梶谷会長さんの開会挨拶の真っ最中でした。できてまだ日が浅いのか、キレイなホールでしたね。このホールでも前座席の背中を出すとテーブルになり、セミナーにはうってつけの座席です。周りを見渡してみても、余り知った顔は無し。SPOC研究会のメンバーさんばかりなのかな。以前の時に行った時は、サッカー関係の方見かけましたが、今回はいなかったなぁと。人数もあの時の半分くらいでした。次はもう少し周知されてもいいのではと。
まずは梶谷代表からそのまま、オープニングセッションとして、「SPOC研究会の2年間とこれから」というタイトルで、2014年10月に発足してから2年間の活動報告です。いただいた立派なリーフレットにいろいろと書かれてありました。おかやま円卓会議とおかやま地域発展協議体という2つの組織の支援も受けるようです。この辺りはよくわかりません。
「同士の会」でご一緒する方がおられるので、こっそり行ったつもりでしたが、早速にMN氏に見つかってしました(苦笑)。何度も、「同士の会でAT氏と出会えて良かった。ありがとう」と言われております。やはり、マンパワーの結集がパワーを生み出すのですね。それは11年前の「一木会」の時からわかっている事です。読者の皆さんのほとんどは訳わからない話と思いますが、自己満足なのでわからなくていいです(笑)。


第2部はパネルディスカッションです。当ブログでもお馴染みの岡大T岡講師がコーディネータ役で、以下の3人のパネリストと演題です。
①「特集 スポーツ新考の取材を通して見出された地域とスポーツの幸せな関係」 講師:山陽新聞社特集班 久方真毅氏
②「神流マウンテンラン&ウォークが町にもたらした変化」 講師:群馬県神流町観光アドバイザー 細谷啓三氏
③「自立した組織が展開する地域スポーツ振興」 講師:出雲スポーツ振興21事務局長 矢田栄子氏
コーディネーター 高岡敦史氏
パネルディスカッションというよりは、個人的には3つの講演会という印象でした。3つの先進事例を聞いた格好ですね。出雲の団体はスポーツ庁が先進モデルと設定している規模の大きい総合型地域SCのようです。確かに大人数の雇用があるそうです。山陽新聞の話は確かに当ブログでも連載時はよく読んでいましたが、最後の方は行政側にかなりシフトした内容だったと記憶しています。マウンテンランの話を聞いていたら、去年だったかTVドラマで放送されていた「ナポレオンの村」を思い出してしまいました。最後に高岡コーディネーターが総括して、キーワードとしては「スポーツを拠点として、人がつながり変わっていく」という事を言われていました。


第3部の特別講演は、「<スポーツの振興>と<スポーツによる振興>の関係-生活者論の視角から-」という演題で、日本体育・スポーツ経営学会会長、筑波大の柳沢和雄教授のお話でしたが、これが一番面白かったです。前半ですが。
スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことでは、文化度が問われるようですね。そして、「鹿島の経験」という事でJ1鹿島がどのようにしてできていったかを詳しく解説されました。県立カシマサッカースタジアムの周辺20キロ圏人口は約27万人と、等々力競技場の1/50なのに、ホーム入場者数は'98年平均で約1万7千人で等々力よりも7千人多い状態。来場率は1万人対で636人で、等々力の10人の60倍だそうです。
J1鹿島の成り立ちは、まず貧困からの解放で工業地帯が作られ、開発が旧住民と新住民の格差を生んだ。街づくり懇談会が組織されたタイミングで、Jリーグから住友金属にプロリーグ参加意向の打診があった。地域と工業地帯で「サッカーによる町おこし」が生まれて、専スタを建設。その後田舎のままの道路事情の改善を図るために、日韓W杯で開催地に立候補して、インフラ整備を行ったとか。


なかなか堅苦しい内容で難しかったです。その柳沢教授の話の中で、一つだけ耳に留まった言葉があります。「中央と周辺の格差」です。スポーツ振興を図るのはいいが、中央だけ部分的に進めてはいけない、格差が生まれていい結果につながらないという内容。「岡山でも岡山駅西口でスポーツ振興を図ろうとされていますが、同じ話に思える」と、そういう言い方をされました。おやっと思いました。
つまり、岡山総合グラウンドのおひざ元である岡山駅西口、奉還町商店街の活性化を図っているが、東口も含めて全体で活性化を図るべきという話でしょう。当ブログでも「支援の第4の極である「商店・商店街」に対して、理想は奉還町だけでなく、岡山市商店会連合会等を通じて、表町など市全体の商店街を相手にするべき」とコメントしております。そういえば、この日も東口を歩いていた時に、「東口にはノボリとか、ファジの何も無いよなぁ」と思ってはいました。まあ、何が正解なのかは正直わかりません。


第2部にありましたが、スポーツによる地域振興、総合型地域スポーツクラブづくりも、民間主導型と行政主導型があると思います。今回のお話はどちらかといえば後者でした。スポーツによる地域振興ばなしは、当ブログも読者の方にとって範囲が広いと思って書いていますが、この日のパネリストのお話は更に広かったです。プロチームによる専門的なところから、一般市民のちょっとした軽運動まで切り口があると思いますが、どちらかといえば後者。当ブログでは切り口として、やや手の届きにくさを感じました。この辺りの部分はT岡講師とSPOC研究会の皆さんにしっかりお任せしたいと思います。当ブログではJリーグ百年構想など、もう少し専門的な切り口で関わっていきたいと思います。お疲れ様でした。
SPOC研究会(チーム岡山)関連⑪:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20160702
〃 ⑩:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150423
〃 ⑨:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150316
〃 ⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150214
〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141207
〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141107
〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141030
〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091213
〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090819
〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090818
〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090227
今日、Cスタでファジのホーム金沢戦がありました。その模様は明日。














