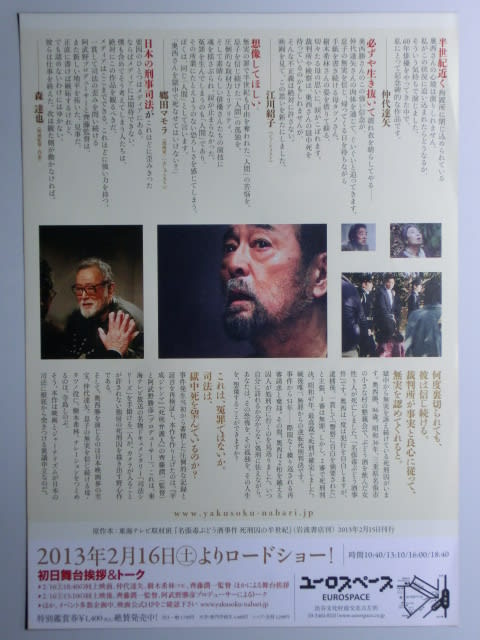朝日新聞「ニュースの本棚」で、テレビ60年をテーマに書かせていただいたら、各地にいる友人や知人から「読んだよ」の連絡がありました。
たとえば・・・
「テレビが大きく変わったのが80年代以降」とのご指摘に、私自身の場合は「変わった」以降のテレビを見て過ごしてきた時間の方が長いのかと気づきました。フジテレビが「軽チャーっぽい」などというスローガンを流していたのを思い出します。
それから、1969年に出た
「お前はただの現在にすぎない」について、触れているメールが多かったです。
この本は、70年代にテレビを目指した若者たちにとって、読んでいない者はいないくらいの、いわばバイブルのような存在でしたが、長く絶版になっていました。
近年、朝日文庫で復刊されたわけですが、その功労者は、かつてテレビマンユニオンで先輩だった石井信平さん(ユニオンに参加する前は筑摩書房の編集者)です。
石井さんは残念ながら2009年に亡くなってしまいましたが、その前年に、「お前はただの現在にすぎない」の40年ぶりの復刊を実現しました。
さまざまな縁につながる一冊であり、今回、文中で紹介できたことは、私にとっても感慨があります。
以下、全文です。
テレビ60年
価値と意味、考える好機に
上智大学教授(メディア論)
碓井広義
日本の放送史におけるテレビ元年は1953年。2月1日にNHKが、8月28日に日本テレビが放送を開始した。もちろん当時はテレビのプロなど存在しない。人材は映画や演劇などからの流入組とラジオからの転籍組、そこに新卒が加わった。
TBSでドラマ「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎(りんご)たち」を手がけた大山勝美も新卒組の一人だ。その大山が、朝日放送出身の澤田隆治などと行った鼎談(ていだん)が
『テレビは何を伝えてきたか』である。ロケを可能にした小型カメラ、国内外からの衛星中継といった技術の進化。バラエティー番組の井原高忠やドラマの和田勉など大胆な制作者の出現。たとえば萩本欽一のような国民的タレントの存在。それらに支えられてきたテレビの軌跡を追体験することができる。
●視聴率の肥大化
社会が学園紛争やベトナム戦争反対運動に揺れた68年に起きたのがTBS闘争だ。ドキュメンタリー「日の丸」の萩元晴彦と、「ハノイ・田英夫の証言」の村木良彦を制作現場から外す配置転換に、成田闘争報道で反対派農民をロケバスに乗せたことへの処分も絡んで、表現の自由や報道の手法をめぐる闘いとなった。萩元と村木、そして村木の同期・今野勉が69年に上梓(じょうし)した
『お前はただの現在にすぎない』(朝日文庫・1155円)はこの闘争の記録であると同時に、テレビに何が可能かを考え抜いた報告であり宣言だ。翌年、萩元たちはTBSを退社し、日本初の番組制作会社テレビマンユニオンを創立する。
その後、テレビが大きく変わったのは80年代だ。右肩上がりの経済を背景に、「楽しくなければテレビじゃない」を標榜(ひょうぼう)したフジテレビが躍進した。他局も追随したことでテレビは明るく楽しく軽くなり、ドキュメンタリーは削減、報道番組さえエンターテインメント化していく。90年代以降、各局の視聴率至上主義は当たり前のものとなった。テレビの両輪であるはずの創造とビジネス。その一方を肥大化させたまま20年が経過したのだ。
還暦を迎えたテレビだが、祝ってばかりもいられない。ネットの台頭。視聴者のテレビ離れ。広告収入の減少。それ以上に問題なのがテレビへの不信感だ。特に一昨年の原発事故以来、テレビは視聴者(国民)が本当に知りたい、また知るべき情報を伝えていないのではないかという思いが視聴者側に広まった。今年1月に出た
『テレビはなぜおかしくなったのか』では、報道現場を体験してきた3人と政治学者が従軍慰安婦問題から原発報道までを鋭く分析。自戒を込めてテレビジャーナリズム再生への道を探っている。
●多様化する見方
現在最も刺激的な論客の一人内田樹がテレビに言及しているのが
『街場のメディア論』である。これまで挙げた本の著者はテレビの送り手側中心だが、内田はより客観的な立場だ。「知っていながら報道しない。その『報道されない出来事』にメディア自身が加担している、そこから利益を得ているということになったら、ジャーナリズムはもう保(も)たない」と手厳しい。
録画視聴をはじめテレビの見方が多様化した現在、リアルタイム視聴を前提としたビジネスモデルは見直す必要がある。「若者層」を視聴者の中心に置く発想も然(しか)りだ。放送開始60周年は、テレビならではの価値と伝えることの意味を原点に立ち返って考えるチャンスである。
◇うすい・ひろよし 55年生まれ。テレビマンユニオン、慶応大などを経て現職。著書に『テレビの教科書』など。