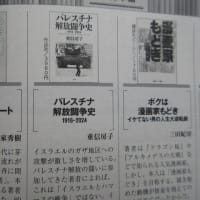「静岡新聞」「熊本日日新聞」「沖縄タイムス」などに掲載された書評です。
選択一つで歴史を傾ける
アンナ・アスラニアン著、小川浩一訳著
『生と死を分ける翻訳』
草思社 2750円
多くの人が、日々当たり前のように翻訳と接している。よほど語学が堪能でない限り、海外文学を日本語訳で読み、洋画を字幕付きで見るのは普通のことだ。
本書は翻訳と通訳の文化史である。読み進めるうちに、翻訳が、ある国の言葉や文章を単純に他の国のそれに変換するだけではないこと。
また通訳とは、異なる言語を話す人たちの間に入り、言葉を訳して話を通じさせるだけではないこともわかってくる。
例えば1962年にキューバでのソ連ミサイル基地建設をめぐって米ソが対立した、いわゆる「キューバ危機」。
米国は「海上封鎖」という対抗策をソ連に通告する。だが、その電文では「blockade(封鎖)」ではなく、「quarantine(隔離、検疫)」という語が使われた。
もし「封鎖」を使用していたら、ソ連側は独ソ戦におけるレニングラード包囲戦を想起し、緊張は一層高まったはずだ、という。
またフルシチョフは一連のやりとりの中で、「貴国が攻撃的とみなす兵器の解体」を約束すると書き送った。この「攻撃兵器」の定義を米国に突かれ、最終的にソ連はミサイルだけでなく爆撃機も撤退せざるをえなくなる。
「世界が深刻な危機に瀕した状況においては、翻訳(通訳)という行為そのものが激しい文化衝突として歴史の表舞台に立ち現れる。そこでは、訳語の選択一つで歴史の天秤が傾いてしまう」と著者は述べている。
さらに、文芸の翻訳についても興味深い考察が並ぶ。ペルシャのオマル・ハイヤーム作とされる詩集「ルバイヤート」の英語訳者は、エドワード・フィッツジェラルドだ。
世界中で読まれてきたが、その翻訳は原文にはないペルシャの事物に満ちている。ある四行詩では原文と共通するのは一語だけ。原作を自分のものと呼びたくなるほどほれ込んだからだ。
翻訳者の役割に関して長く議論の的だった、「翻訳者の主体性」という問題は今も生きている。
(碓井広義・メディア文化評論家)
/ANNA・ASLANYAN ジャーナリスト、翻訳家。英紙ガーディアンや「タイムズ文芸付録」などに書籍やアート関連の記事を寄稿