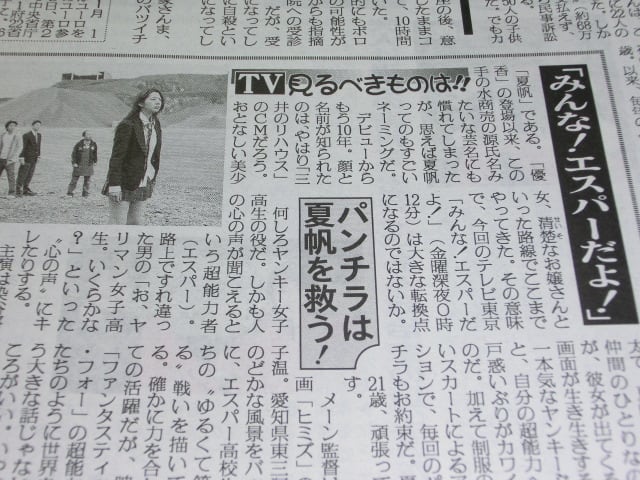「4人目のYMO」松武秀樹さんとセミナースタッフの皆さん
昨日のセミナーに参加された佐々木康彦さん(CMパンチ代表取締役)が、ご自身のブログに感想を書いてくださった。
読ませていただき、あらためて感じることが多かったので、紹介させていただきます。
佐々木さん、ありがとうございました。
この時代に
「NO FUTURE A SEX PISTOLS FILM」
を観て思うこと
「NO FUTURE A SEX PISTOLS FILM」
を観て思うこと
このセミナーに参加して、どうしてもこのブログに書いておきたいと思ったので今夜は自分の時間を確保しました。
日本の下請け制度は戦時経済下で発達したこと、1940年体制の特徴に「競争の否定」という特徴があったという野口悠紀夫氏の指摘は以前にも紹介した通りですが、今日の碓井 広義氏の話しの中でテレビ業界が生まれてからこれまでの流れの中で構築されてきた下請けシステムについての指摘がありました。
テレビ番組のエンドロールを見ると、その殆どの番組の著作権はテレビ局が持っていることが分りますが、その実際の制作は番組制作会社が行っています。
番組によってはキャスティング専門、ロケ専門、スタジオ収録専門のような下請け構造の中で更に分業化が行われ、非常にシステマチックに制作が行われているわけですが、最終的な著作権を局が持っているということは、この下請け構造が変革する要因はまず無いということです。
ということは、実際の番組作りでいくら頑張っても、制作会社はポジショニングとして局と同じにはなれないということです。
この事について碓井氏は「何十年も一緒にやってきたがパートナーのような存在になる訳でもなく、下請け状態が続いている」と指摘、それが結果として制作業界の魅力を半減させていることと、サクセスストーリーがないところに良い人材が集まる訳がないと警鐘を鳴らします。
そして松武氏も、いまは音楽業界で食べて行くのが凄く大変になってしまい、ミュージシャンになろうという人が激減していて、この状況では業界に良い人を集め、育てていこうと思ってもそれがままならない現状に危機感を持っていることを発言されていました。
自分が関わったことがある、テレビ、音楽の業界。昭和の時代には勤めたい人がそれこそわんさか居て、薄給や激務で人がやめても入れ替え利くし、新人時代はボロ雑巾扱いで10~20人くらいとって1年後は1人が残るみたいな雰囲気が、あの当時ほどではないにしろ、イマでも少しはあるだろうと推測します。
ちなみに音楽、テレビ、マスコミ・出版など業界は多かれ少なかれ、似たようなところがあるような気がしますが…
局に勤められなければ結局下請けだよね…というのは分っていた事ではありますが、本当にごく一部の人たちが、多くの人たちの頑張りに支えられながら、非常に恵まれた環境を手にする。だがそこを支える立場の人間は、ずっと支えっぱなしで実質的な制作をしているにも関わらず著作権は局のモノ…まさにこの資本主義を表わす構図そのもの。
つい先日、政府が「職務発明」の帰属を見直す方針を示しましたニュースに“頭脳”流出リスクが指摘されていましたが、日本の会社の最大特徴であった終身雇用を放棄して、更に発明の帰属も企業にというのは、もともと形のないアイデアなどにカネを払いたがらない日本企業がこれを言い出すというのは虫が良すぎ。
デジタル時代はビジネスモデルもコピー可能な時代です。音楽やデザインなども優れたオリジナルが出現し、それを一度コピーしてしまえばあとは企業がどう売るかという話しになってきます。
これは優れたオリジナルは商売になるけれど、その利益が行き渡るのは非常に限られた範囲になることを意味しており、ギャラの設定や契約方法を後から後悔しても手遅れという話しなります。
この手の話しでやはり忘れられないのは「およげたいやきくん」のギャラが買い取り契約だった話しな訳ですが、、、
前向きにまとめるなら、多くの企業が永続的な発展を目指して戦略的な取組みをしている訳ですが、会社が生き残る仕組みの構築にばかり熱心ですが、そこには個が活きるサクセスストーリーが本来は必要なんではないのか…と。
強固な社会の仕組みの中で自分達なりの生き方を見いだすというところでふと思い出したことがあります。
先週末セックスピストルズの「NO FUTURE A SEX PISTOLS FILM」を見て何か忘れている事ないか、、、と凄く突き動かされた感じがしてました。
ロカビリー、グループサウンズにロックやフォークって昔は不良のやるもので、のけ者扱いという時代もすでに昔話(苦笑)。この映画で描かれているように歌詞やその音楽とライフスタイルから社会から排除されてしまう時代もあり、ピストルズは労働者階級の不満をぶちまけながら、パンクというスタイルを確立して、それまでの音楽シーンを一変させてしまいました。
今日のセミナーで業界的な斜陽化の話しが出てましたけど、社会全般としても時代的な閉塞感がかなり積もり積もった感じになっているだけに、セックスピストルズみたいなシンボルが生まれる可能性ありかなと思ったりしたのでした。
(ブログ「平凡でもフルーツでもなく、、、」
http://blogs.itmedia.co.jp/yasusasaki/
2013.06.11)